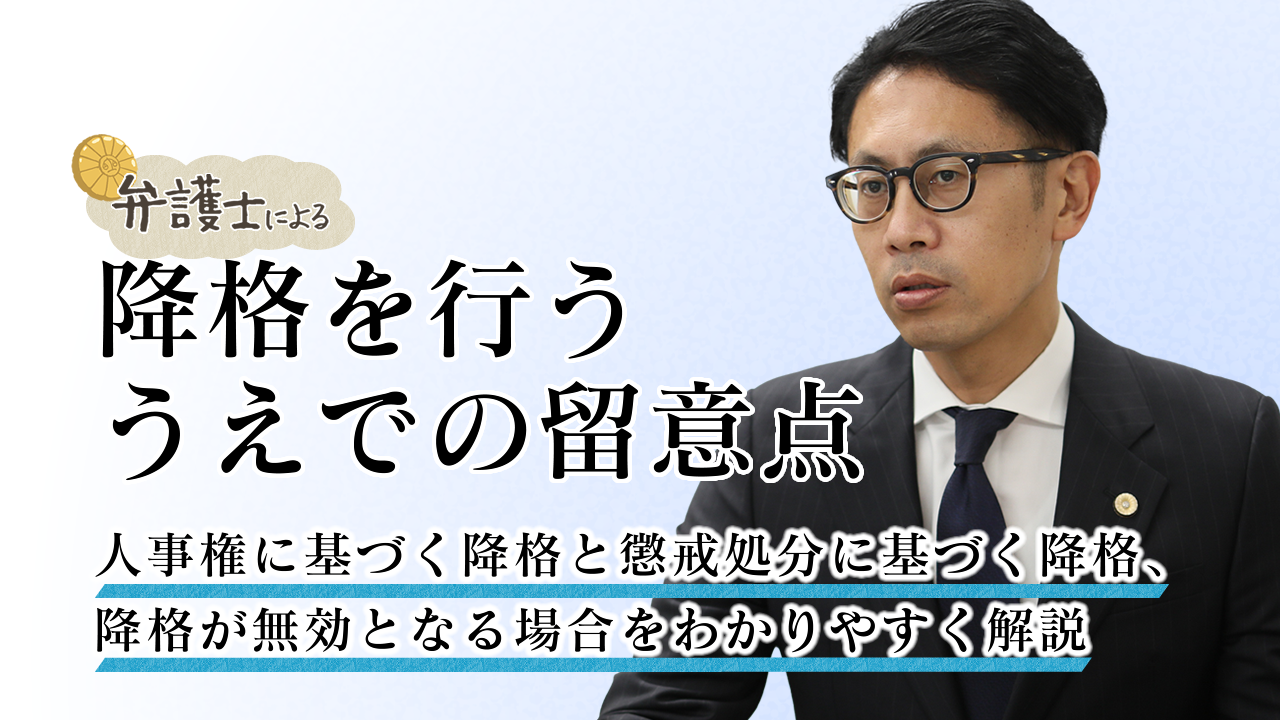監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員
「降格処分」は、能力や成績、勤務態度などに問題がある従業員の職位や等級を引き下げる処分です。
問題社員を放置することは、職場の雰囲気を悪くするだけでなく、重大なミスを招き、経営に打撃を与えるリスクもあるため、迅速に対処することが重要です。
本記事では、降格処分を行う際の注意点、降格処分の対象となる問題社員の例、降格処分が違法となるケースなどについて詳しく解説していきます。
目次
降格処分とは
「降格」処分の方法は、主に以下の2つがあります。
- ① 職位や役職を引き下げるもの
- ② 職能資格制度上の資格・等級や、職務・役割等級制度上の等級を引き下げるもの
また、「降格」処分の根拠も、以下の2パターンが考えられます。
- (ア)懲戒処分としての降格(いわゆる“降職”)
- (イ)業務命令による降格(人事権に基づく降格)
「懲戒処分としての降格」を行う場合、就業規則で懲戒事由を定め、懲戒処分のひとつに「降格」があることを明記しておく必要があります。
一方、「業務命令による降格」については、会社の人事権に基づく措置なので、就業規則に規定がなくても処分することは可能です。ただし、後に労働トラブルに発展した場合に備え、就業規則で降格の要件や範囲について定めておくのが望ましいでしょう。
なお、職能資格制度上の資格・等級の引き下げについては、基本的に就業規則上の根拠が必須とされています。これは、職能は年数と経験に比例して向上するものであり、一度認定された資格・等級が下がることは想定されていないためです。
問題社員を降格処分とする際の留意点
降格処分を行う際は、就業規則の規定に基づき、適切な手順に沿って対応することがポイントです。安易な判断は会社の「権利濫用」にあたり、処分が無効となったり、従業員とトラブルになったりする可能性があるため注意しましょう。
具体的には、以下の4点に留意する必要があります。
- 問題点を改善する機会を与える
- 就業規則に根拠規定を設けておく
- 降格処分を裏付ける証拠を集める
- 減給処分には限度額がある
懲戒処分全般の流れや注意点は、以下のページで解説しています。
問題点を改善する機会を与える
問題社員の態度に改善の余地がある場合、問題点を具体的に指摘したうえで、改善の機会を与えることが重要です。
例えば、「業務改善指導書」を交付し、従業員に自身の問題行為を自覚させることで、主体的に改善に取り組む効果が期待できます。また、業務上のミスや能力不足が原因の場合、改めて教育や研修を行うことも検討すべきでしょう。
このような対応を一切せず、直ちに降格処分を下した場合、手続きの相当性を欠き、“会社の権利濫用”と判断されるリスクが高まるため注意が必要です。
就業規則に根拠規定を設けておく
「懲戒処分としての降格」を行う場合、就業規則上の根拠が必須となります。懲戒事由や懲戒処分の種類を明確に定め、従業員に周知しておきましょう。
一方、「人事権に基づく降格」のうち、“役職や職位を解くもの”については、基本的には就業規則に規定がなくても処分が可能です。しかし、降格に合理性や相当性が認められない場合は“人事権の濫用”にあたり、無効となるおそれがあるため、就業規則に一定の規定を設けておくのが望ましいでしょう。
就業規則については、以下のページで詳しく解説しています。
降格処分を裏付ける証拠を集める
降格処分の有効性をめぐり、裁判などに発展した場合、従業員の問題行為を裏付ける客観的な証拠が必要となります。例えば、以下のようなものが証拠になり得ます。
- 問題社員の営業成績
- 勤怠不良を示すタイムカードの記録
- 人事考課の内容や根拠
- 面談の議事録(業務改善命令に関するもの)
- 注意や指導を繰り返し行った記録 など
裁判所は、当事者から提出された証拠をもとに事実認定を行うため、証拠が不十分だと会社に不利な結果になりかねません。
懲戒権や人事権の濫用が認められた場合、降格が無効になるだけでなく、慰謝料の支払いなどを命じられる可能性もあるため、有効な証拠をできるだけ多く集めると良いでしょう。
降格処分で減給する場合の限度について
降格に伴って給料を減らす場合、法律で明確に「ここまでしか減らしてはいけない」といったルールは定められていません。
労働基準法には、減給処分に関する制限(第91条)がありますが、これは「懲戒としての減給」に関するものであり、「降格による減給」には直接適用されません。
労働基準法
第91条(制裁規定の制限)
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
ただし、実際の裁判では、降格によって給料を減らすことが法律に違反していないかが争点になることがあります。判例では、役職手当などの「役職に応じた部分の給料」は減らしても認められやすい一方で、「基本給」などの生活に直結する部分の給料を減らすことは、認められにくい傾向があります。
懲戒処分による「減給」については、以下のページで詳しく解説しています。
降格処分が有効とされる問題社員の例
降格処分の対象となる問題社員について、具体例を交えて紹介していきます。降格処分の根拠によって対象者も異なるため、きちんと区別する必要があります。
懲戒処分の場合
懲戒処分は、重大な規律違反をした従業員に対する“制裁”として行われる処分です。
そのため、問題行為のなかでも悪質性が高いものや、注意や指導を繰り返しても改善されない場合に適用されるのが一般的です。
例えば、以下のような行為は降格処分が認められる可能性があります。
- 就業規則などの社内規則違反
- 悪質なセクハラやパワハラ
- 横領や窃盗などの犯罪行為
- 情報漏洩など会社に多大な不利益をもたらす行為
- 著しい勤怠不良や長期間の無断欠勤
人事権行使の場合
人事権の行使による降格は、従業員の“能力不足”や“成績不良”を理由に行われるのが一般的です。
本人の能力が、現在の役職・職位に不適格だと判断できる場合、基本的に会社の裁量で職位を解任することができます。
ただし、降格に伴い賃金も減額する場合、就業規則や労働契約上の根拠が必要となります。
例えば、就業規則で“職位”と“役職手当の金額”が連動している場合、降格に伴う賃金減額(手当の減額)も可能と考えられます。
一方、基本給そのものを減額する場合、その有効性は厳しく判断される傾向があるため、従業員に十分説明したうえで、同意を得るのが望ましいでしょう。
「降格処分通知書」の書き方
降格処分を行う旨は、「降格処分通知書」の交付によって通知するのが一般的です。降格の通知は口頭でも可能ですが、トラブル防止の観点から書面で行うのが基本です。
通知書への記載事項は、「懲戒処分」と「人事権行使」によって以下のように異なります。
〈懲戒処分〉
- 従業員名
- 社名と代表者名
- 処分日
- 降格処分とする旨
- 処分の内容(〇年〇月〇日付で営業部長の任を解き、営業部事務課での勤務を命じる など)
- 降格処分事由
- 就業規則上の根拠条文(就業規則第〇条に定めるパワーハラスメントに該当するため など)
〈人事権行使〉
- 従業員名
- 社名と代表者名
- 処分の内容(〇年〇月〇日付で営業部長の任を解き、営業部事務課での勤務を命じる など)
なお、人事権行使の場合、通知書の題名は「辞令」などとし、懲戒という文言は使わないよう注意しましょう。
降格処分が違法となるケースとは?
降格処分が違法となるのは、以下の2つのケースです。
違法性が認められると、基本的に処分は無効となるため注意が必要です。
- ① 降格処分の根拠(就業規則等)がないとき
- ② 降格処分が会社の権利濫用と認められるとき
つまり、降格処分には基本的に就業規則上の根拠が必要であり、かつ正当な理由と手段によって実施することが必要です。
なお、人事権行使に基づく降格処分のうち、一定の“役職を解く降格”は会社の裁量で決定できるため、就業規則に規定がなくても処分することは可能とされています。
ただし、処分に合理性や相当性が認められない場合は「権利濫用」にあたり、違法となるため慎重に判断することが重要です。
また、労働トラブルに発展した場合の備えとしても、降格処分のルールはすべて(懲戒処分・人事権行使いずれのケースも)就業規則に明記しておくのが望ましいでしょう。
問題社員の降格処分に関する裁判例
降格処分の有効性が争われた事例として、以下の裁判例を取り上げます。
事件の概要
【昭和63年(ワ)第12116号 東京地方裁判所 平成7年12月4日判決、バンク・オブ・アメリカ・イリノイ事件】
Y銀行の在日支店で管理職として勤務していたXが、会社の新経営方針に積極的な理解・協力を示さなかったことを理由に“降格”させられ、その後「総務課の受付」に配置転換された事案です。
当時Y社は厳しい経営難に陥っており、組織改編が急務とされていたことから、新体制に同意しない管理職を多数降格させていました。
Xは、本件の「降格」及び「配転」は、Xら中高年管理職を退職に追い込むための嫌がらせ(不法行為)にあたるとして、Yに慰謝料の支払いなどを請求しました。
裁判所の判断
裁判所は、以下の事実を踏まえ、Xら管理職の降格は「権利濫用にはあたらない」と判断しました。
- Yの経営難を踏まえると、新経営方針の推進・徹底が急務であり、これに積極的に協力しない管理職を降格する業務上・組織上の高度な必要性が認められること
- Xと同様に降格させられた他の管理職については、いずれも降格に異議を唱えておらず、本処分はやむを得ないものと受け止めていたと推認されること
→Xの降格をもって、Yが人事権を濫用したものとは認められないため、降格処分は有効である。
一方、総務課の受付への配転については、Xの名誉や自尊心を深く傷つける措置であり、職場内での孤立や勤労意欲の喪失、退職に追いやること等が目的であると推認できるため、人事権の濫用にあたり“無効”であると判断しました。
ポイントと解説
降格は会社の人事権に基づく措置ですが、合理性や相当性が認められない場合は“権利濫用”にあたり、無効になります。一般的に、降格処分の適法性については以下の点から判断されます。
- 不当な目的の有無
- 業務上の必要性の有無や程度
- 労働者の能力や適性
- 労働者の受ける不利益の程度
本件の場合、会社の新経営方針に非協力的な管理職を降格する「業務上の高度な必要性」が認められること等から、降格処分は有効と判断されました。
一方、総務課の業務は、「Xの能力や適性を踏まえると到底ふさわしい業務とはいえない」として、配転については無効と判断されています。
よって、事業者は、経営上の必要性だけでなく、処分の妥当性なども十分検討したうえで降格処分を下すことが求められます。
問題社員の降格処分についての不明点は弁護士にご相談ください
問題社員を放置することは様々なリスクを伴うため、会社としては早めに対処することが重要です。
しかし、降格処分は労働者にとって不利益が大きく、紛争に発展するリスクも高いことから、慎重な判断が求められます。
弁護士であれば、事案に応じて妥当な処分を検討し、適正な流れで処分を下すことができます。また、スピーディーに手続きを進められるため、問題の早期解決も期待できます。
弁護士法人ALGは、問題社員への対応をはじめ、労務問題に精通した弁護士が揃っています。お悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ
企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※
企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)
会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません
※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)
執筆弁護士

- 弁護士法人ALG&Associates
この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)
執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。
近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある