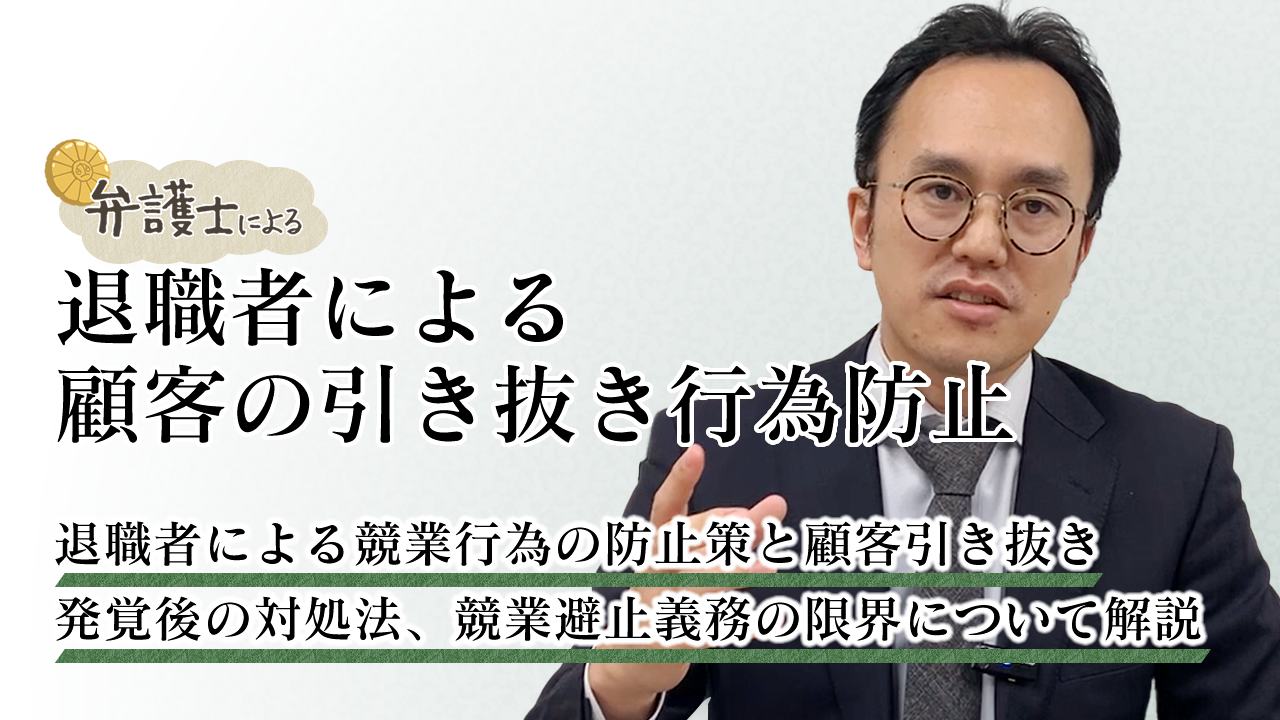監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員
退職者による顧客の引き抜きが行われると、企業は取引先を失い、売上減少などの損害を受ける可能性があります。そこで、あらかじめ顧客の引き抜きを禁止するルールを整え、退職時に誓約書を取り交わすなど対策が必要です。
本記事では、退職者に顧客を引き抜かれるリスク、引き抜きを未然に防ぐ方法、引き抜きが発覚した場合の対応などについて詳しく解説していきます。
目次
退職者によって顧客の引き抜きが行われるリスク
退職者による顧客の引き抜きが行われると、企業は以下のようなリスクを負います。
- 本来得られる予定だった売上(利益)が減少する
- 顧客リストが持ち出され、個人情報が流出するおそれがある
- 退職者が企業の悪評を広め、企業イメージが悪化する
- 厳正に対処しないと、他の従業員の不信感を招く
引き抜きが発覚した場合、退職者に対して損害賠償請求を行うことも可能ですが、具体的な損害額は会社側で立証しなければなりません。また、裁判に発展すればさらに時間やコストがかかるため、顧客の引き抜きは未然に防ぐことが重要です。
なお、引き抜き行為については「従業員の引き抜き」にも注意を払う必要があります。詳しくは以下のページをご覧ください。
顧客の引き抜き行為を防止する方法とは?
顧客の引き抜きを防ぐには、あらかじめ以下のような対策をしておくことが重要です。
- 退職後の競業行為を禁止する
- 顧客との取引を禁止する
- 顧客情報の持ち出しを禁止する
従業員に競業行為の禁止(競業避止義務)を課しているケースは多いですが、退職後の引き抜き行為も禁止する場合、別途誓約書や合意書を交わす必要があります。
退職後の競業行為を禁止する
競業避止義務とは、在籍する企業と競業するような行為を行ってはならないという義務です。例えば、同業他社への転職や、同じ事業を営む会社の設立などを禁止することをいいます。
本来、競業避止義務は労働契約に付随して発生するものなので、すでに退職した者はこの義務を負わないのが基本です。そのため、退職後の競業行為を禁止するには、退職時に改めて「競業避止義務」に関する合意書や誓約書を交わす必要があります。
また、就業規則でも退職後の競業避止義務について定め、違反した場合の措置なども明記しておくとなお良いでしょう。
競業避止義務の詳細は、以下のページで解説しています。併せてご覧ください。
在職中に担当していた顧客との取引を禁止する
顧客との取引を無制限に認めると、自社の顧客が転職先の会社に流れ、売上が大きく減少するおそれがあります。そこで、退職者との間で顧客との「取引禁止条項」を定め、引き抜きを未然に防ぐことが重要です。
なお、厳格な競業避止義務は裁判で“違法”と判断されることも多いですが、「取引禁止条項」のみであれば、労働者の職業選択の自由を過度に制限するものではないため、比較的有効と判断されやすい傾向があります。
ただし、顧客との取引を一切禁止すると、制限が大きすぎるとして無効となるおそれがあります。そのため、取引禁止の範囲や期間には一定の上限を設けるのが望ましいでしょう。
顧客範囲や期間の定め方
顧客との取引を全面的に禁止すると、制限が過度と判断され、無効とされる可能性があります。そのため、顧客範囲や期間には、以下のような上限を定めておくのが望ましいといえます。
- 顧客範囲
「企業の全顧客」にすると範囲が広すぎるため、取引を禁止するのは「退職者が在職中に担当していた顧客」のみとするのが一般的です。 - 期間
顧客との取引禁止期間は、2年以内とするのがひとつの目安とされています。業種や職種にもよりますが、一般的に2年を超える取引禁止条項は無効と判断される傾向があります。
また、取引禁止条項では、「顧客への営業活動」だけでなく「取引全般」を禁止しておくことが重要です。取引は相手方(顧客)から連絡を受けて成立することもあるため、取引自体を禁止しておくとなお効果的です。
顧客情報の持ち出しを禁止する
担当していた顧客との取引を禁止するだけでは、担当外の顧客への営業活動は許容されることになるため、結果的に自社の顧客が引き抜かれるリスクは拭いきれません。
顧客情報(名簿やリスト)の持ち出しを禁止することで、退職者が担当外の顧客に接触するリスクを抑え、引き抜きを未然に防ぐことができます。
具体的には、退職者との間で「秘密保持契約」を締結し、在職中に得た情報を外部に持ち出さないよう約束させるのが一般的です。
また、持ち出しを禁止する顧客情報の内容も明確に定めることで、トラブル防止につながります。
秘密保持契約書の作成方法は、以下のページをご覧ください。
情報の範囲や期間の定め方
持ち出しを禁止する顧客情報の内容は、できるだけ具体的に定めておく必要があります。例えば、「業務上で知り得た顧客の情報」のみだと、範囲が不明瞭でありトラブルを招くおそれがあります。
そのため、情報の範囲は以下のように具体的な項目を列挙しておくことをおすすめします。
- 顧客の氏名、住所、連絡先
- 顧客との取引内容
- 取引価格に関する情報
- 顧客から提出された資料
なお、秘密保持義務は企業の利益を守るための基本的な義務なので、期間の定めは不要とされています。つまり、顧客情報の持ち出し禁止期間について、「退職後〇年」といった上限を設ける必要はありません。
顧客情報は不正競争防止法上の「営業秘密」にあたるか?
不正競争防止法上の「営業秘密」とは、次の3要件を満たすものをいいます。
- ①秘密として管理されていること
- ②事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること
- ③公然と知られていないものであること
顧客情報についても、これらの3要件を満たせば、不正競争防止法違反として責任追及できる可能性があります。ただし、営業秘密の該当性については個別具体的に判断されるため、必ずしも該当するとは限りません。
判断に迷われる場合、弁護士に相談してみるのもおすすめです。
不正競争防止法については、以下のページも併せてご覧ください。
退職者による顧客の引き抜き行為は違法なのか?
退職者はすでに雇用契約が終了しているため、競業避止義務は負わないのが基本です。そのため、顧客の引き抜きについても違法性が認められる可能性は低くなります。
また、労働者には営業の自由があるため、企業が退職者の行為を制限するのは難しいのが通常です。
ただし、退職時の誓約書の有無や、引き抜き行為の態様によっては、退職者による顧客の引き抜きであっても違法と判断されることがあります。
顧客の引き抜きが違法になるケース
- 一斉かつ大量に顧客を引き抜いた場合
転職前の顧客を一斉かつ大量に引き抜いた場合、企業は多大な損害を負うことが想定されます。そのため、退職後の引き抜き行為であっても、社会的相当性を逸脱しているとして違法となる可能性があります。 - 退職時に誓約書を締結していた場合
退職時に、顧客の引き抜きを禁止する旨の誓約書を締結していた場合、合意内容に反する引き抜きは基本的に違法となります。 - 営業秘密を持ち出した場合
顧客情報の持ち出しを伴う場合、顧客の氏名や住所、取引内容などは営業秘密に該当する可能性があります。その場合、不正競争防止法違反として違法性を問うことが可能です。 - 企業を誹謗中傷した場合
退職者が顧客を引き抜く際に、「あの会社は倒産間近だ」「社長が不正をしている」などの虚偽または中傷的な発言をしていた場合、不法行為にあたり違法となる可能性があります。
顧客の引き抜きを禁止する際の注意点
禁止条項は就業規則と誓約書の両方に規定する
顧客の引き抜き禁止については、「就業規則」と「誓約書」の両方で定めておくのが望ましいといえます。就業規則の定めのみでも法律上は問題ありませんが、以下のようなリスクもあるため注意が必要です。
- 労働者代表への意見聴取や社内周知など、作成手続きに不備があると効力がなくなる
- 就業規則の内容を従業員が十分理解しているとは限らない
これらのリスクを踏まえると、就業規則だけでなく、個別の誓約書も締結しておくことが重要といえます。
不当な禁止条項を定めると無効になる場合がある
目安として、引き抜き禁止の期間は1~2年とし、対象顧客の範囲は「在職中に担当していた顧客のみ」とするのが良いでしょう。
引き抜き行為を今後一切禁止したり、企業の全顧客を取引禁止の対象にしたりすると、違法となるリスクが高まります。
退職者による顧客の引き抜きが発覚したらどうする?
退職者による顧客の引き抜き行為が発覚した場合、企業は以下のような法的措置を取ることができます。
- 損害賠償請求
顧客の引き抜きによって企業の利益(売上)が減少した場合、売上相当分の損害賠償金を請求できる可能性があります。 - 差止請求
競業避止義務違反などが認められる場合、裁判所に「差止請求の申立て」を行い、引き抜き行為の差止めを求めることができます。また、緊急性が高い場合は、「仮処分の申立て」を行うことで一時的に引き抜き行為を停止させることも可能です。 - 退職金の返還請求
支給済みの退職金の返還を請求できる可能性があります。就業規則や雇用契約書において、競業避止義務違反は退職金の減額または不支給の対象となる旨を定めておくと良いでしょう。 - 刑事告訴
営業秘密の持ち出しを伴う場合、不正競争防止法違反にあたり、刑事告訴できる可能性があります。ただし、刑事告訴の目的は「刑事罰を与えること」なので、損害賠償請求とは別の手続きとなります。
退職金を減額・不支給とする際の注意点は、以下のページをご覧ください。
顧客の引き抜きによる損害賠償請求が認められた判例
【平成2年(ワ)4912 東京地方裁判所 平成5年1月28日判決、チェスコム秘書センター事件】
〈事件の概要〉
電話代行などの秘書業務を行う会社の従業員2名(Y1、Y2)が、以前勤務していた会社Xの顧客リストを利用して相手宅を訪問し、より廉価な料金を提示したうえで自社への契約切り替えを持ち掛けた事案です。
会社Xは、Y1、Y2の競業避止義務違反(債務不履行)を理由に、両名に対して損害賠償請求を行いました。
〈裁判所の判断〉
裁判所は、以下の事情を踏まえ、Y1とY2による顧客の引き抜きは競業避止義務違反にあたると認定しました。
- 労働契約継続中に獲得した顧客に関する情報を利用し、使用者が取引継続中の者に働きかけをして競業を行うことは許されないと解するのが相当である
- Y1とY2は、顧客がすでにXから転送機を購入済みであることを知ったうえで、より廉価な料金を提示し、自社への契約切り替えを勧誘していると認めることができる
- Y1とY2は、意図的に原告の営業上の秘密を得る目的でXに入社していると推認され、その義務違反の態様は極めて悪質なものといわざるを得ない
これらの理由から、Y1とY2の行為はXとの労働契約上の債務不履行にあたるとして、賠償金500万円の支払いを命じました。
〈判決のポイント〉
本来、退職済みの労働者については、営業の自由の観点からも労働契約上の義務は負わないのが基本です。
しかし、本件の場合、被告が原告と取引継続中の顧客に営業活動を行っており、また、被告がもとより顧客情報の獲得を目的に原告に入社していることから、悪質性が極めて高いと指摘されています。
このような事情がある場合、特別の約束がなくとも、退職後の競業避止義務が認められる可能性があります。
退職者の顧客の引き抜きについては弁護士にご相談ください
退職者については、合理的な範囲で顧客の引き抜き行為を禁止し、個別の誓約書や合意書を締結しておくなどの対策が必要です。しかし、業種や職種によっても判断基準は異なりますし、誓約書の作成には専門的知識も求められます。
弁護士であれば、引き抜き禁止の要件や適切な上限を定めたうえで誓約書を作成できるため、より有効な取り決めを行うことが可能です。禁止事項が明確であれば、退職者の同意も得やすくなるでしょう。
また、万が一裁判に発展した場合も、有効な証拠や主張を揃え、企業側に有利な結果となるようしっかりサポートできます。
退職者による顧客の引き抜きについてお悩みの方は、ぜひ一度弁護士法人ALGにご相談ください。
企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ
企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※
企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)
会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません
※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)
執筆弁護士

- 弁護士法人ALG&Associates
この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)
執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。
近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある