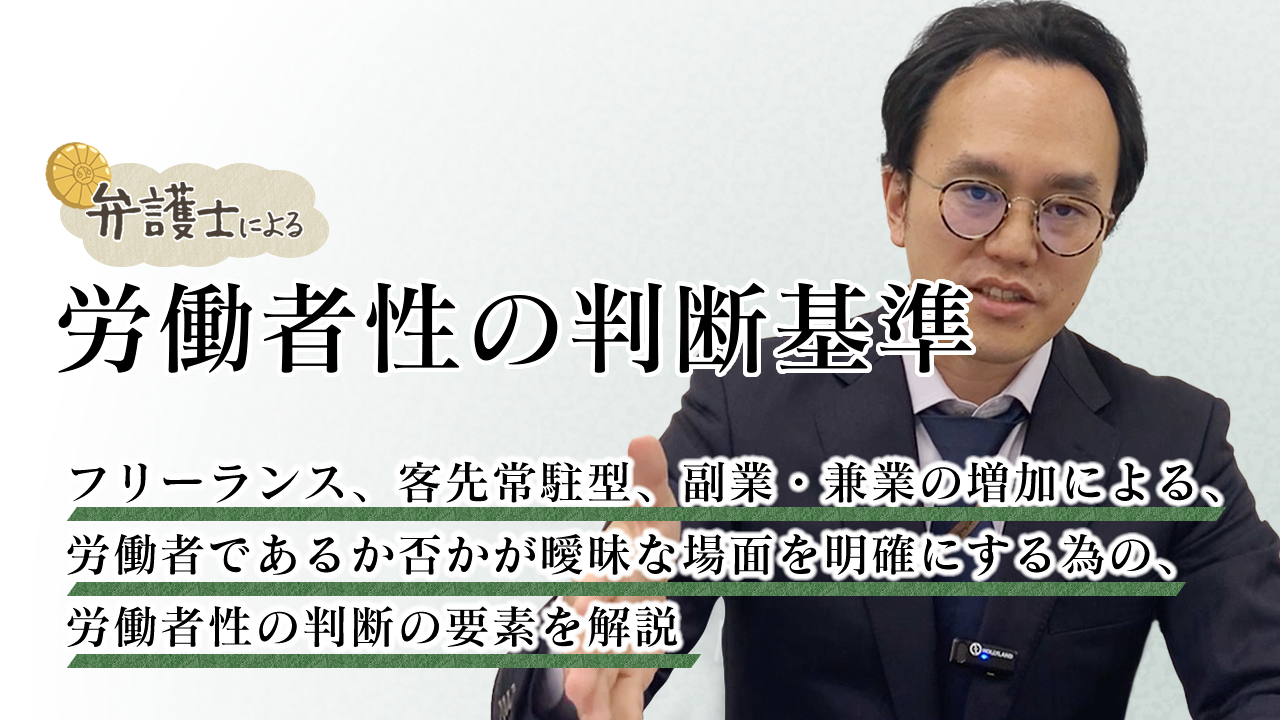採用基準の決め方|5つのポイントや注意点などわかりやすく解説

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員
採用を成功させるためには、明確な採用基準を設けることが重要です。求めるスキルを持つ応募者を見極め、必要な人数の採用を成功させるためにも、自社に合った採用基準を定めることは不可欠といえます。
また、採用基準を設ける際は、応募者の基本的人権を侵害しないようにするなど注意すべき点が多数あります。採用担当者はこれらの注意点を十分理解し、採用活動に臨む必要があります。
本記事では、採用基準を定める重要性やメリット、採用基準を定める際のポイント、注意点などを詳しく解説していきます。
採用基準を設ける重要性と目的
採用基準とは、自社に適した能力や人格を有する応募者を採用するための基準です。
基準を作成する目的として、主に次のものが挙げられます。
- ①入社後のミスマッチを防ぐ
- ②選考の公平性を保つ
- ③採用活動の効率化
入社後のミスマッチを防ぐ
企業が適切な採用基準を定めることで、自社とマッチする人材を採用しやすくなります。
採用基準が不明確だと、自社の仕事や社風に適していない応募者を採用してしまい、短期間での離職につながるおそれがあります。その結果、人手不足に陥ったり、コストをかけて再び採用活動をしたりと、企業は大きなダメージを受ける可能性もあります。
そのため担当者は、採用基準を明確に定めたうえで選考活動を行うことが重要です。
選考の公平性を保つ
一律の採用基準を用いることで、公平に選考を行うことができます。
採用基準が曖昧だと、面接官の主観によって選考結果が左右され、自社に適した人材を取りこぼしてしまうおそれがあります。
誰が面接したかで選考結果が変わるのは企業にとってもリスクが大きいため、採用基準は明確に定め、面接官全員に徹底させることが重要です。
採用活動を効率化できる
採用基準を決めておけば、応募者ごとに社内の意見をすり合わせる必要がなくなるため、採用活動を効率化することができます。
事前に採用基準を決めておかないと、応募者が社風に合っているかなどを個別に検討しなければならないため、時間がかかり、辞退者の増加につながるおそれがあります。
適切な採用基準を設けることにより、一定の基準をクリアした人材だけを効率よく確保して、早いレスポンスも可能となります。
採用基準の決め方・5つのポイント
採用基準を決める際は、以下の5つのポイントを押さえましょう。
- ①就活・転職市場のトレンドの把握
- ②各部署が必要とするスキルの確認
- ③コンピテンシーモデルの作成
- ④求める人物像の明確化
- ⑤必要条件の優先順位を決める
それぞれのポイントについて、次項から詳しくみていきます。
①就活・転職市場のトレンドの把握
就活や転職の市場は、時代の流れによって年々変化しています。そのため、企業は現在のトレンドに合わせた採用戦略を練ることが重要です。
例えば、以下のようなケースは見直しが必要でしょう。
- テレワークや副業が推進される中、「出社必須」「副業は厳禁」とする
- 異業種への挑戦指向が高まる中、「未経験者不可」「〇年以上の経験必須」と応募者を限定する
- 物価高騰が続く中、賃上げや労働条件の改善を一切行わない
このように、トレンドを無視して自社の理想だけを押し出すと、応募者が集まらず採用活動が難航するおそれがあるため注意が必要です。
採用活動の際には、応募者の視点に立った求人を出すことが大切です
②各部署が必要とするスキルの確認
現場が求める人材を洗い出し、採用基準のベースを確立します。具体的には、以下のような事項を確認しましょう。
- 業務上不可欠なスキル
- 必要資格
- 求められる経験や能力
- 職場に合った特性(リーダーシップやチームワークなど)
これらを特定する際は、管理職や現場の社員に直接ヒアリングを行うのが効果的です。
また、人材獲得だけを目的とせず、企業全体の成長にもつながるよう、事業計画も踏まえた戦略的な採用基準を定めることが重要です。
このように、必要条件をあらかじめ確認しておくことは、効率的でスムーズな採用へとつながります。
③コンピテンシーモデルの作成
コンピテンシーモデルとは、自社で高い成果を上げている社員をピックアップし、その人の思考や行動パターンをモデル化することです。つまり、こんな人材が欲しいという「理想の人物像」を定める方法です。
具体的には、対象となる社員にヒアリングを行い、「仕事で気を付けていること」や「意識している行動」などを聞き出します。
複数人から聞き取りを行うことで、多くの共通点が見つかり、採用基準を定めやすくなります。
④求める人物像の明確化
ヒアリングやコンピテンシーの作成によって、採用したい人物像を明確化していきます。複数の面接官に、自社で採用したい人物像の共通認識を持たせることによって、早期離職などを防止します。
面接官がイメージしやすいように、「どんな性格なのか」「何を意識しているのか」といったなるべく細かい人物像を言語化することで、解釈の違いが生じないようにしましょう。
⑤必要条件の優先順位を決める
| 能力 | 学力、コミュニケーション能力、論理的思考力など |
|---|---|
| スキル | 営業力、マネジメント能力、保有資格など |
| 経験 | 実務経験年数、ブランクの有無など |
| 社会適合性 | 規律を重んじる姿勢、協調性、共感性、忍耐力、責任感など |
各部署にヒアリングした結果やコンピテンシーモデルをもとに、必要条件に優先順位をつけていきます。すべての条件を完璧に満たす求職者を見つけるのは難しいため、何を優先すべきかは非常に重要です。
例えば、以下のような振り分けが考えられます。
保有資格などの必須条件や、性格や特性といった資質の部分などに分類する点がポイントです。
| 必須条件 | 保有資格、実務経験 |
|---|---|
| 希望条件(あると望ましい) | マネジメント能力、リーダーシップ、コミュニケーション能力などのスキル |
| 優先度が低い条件 | ・営業力 ・マナーや所作 |
特に、入社後に育ちにくい「性格」や「特性」、「最低限備えるべき資格」などを重視することがポイントです。優先順位を明確にすることで、選考をスムーズに進めることができるでしょう。
採用基準を決める際の注意点
採用担当者は、応募者の基本的人権を尊重し、応募者の適正・能力に基づいた基準を用いた「公正な採用選考」を行う必要があります。具体的には、以下の2点を遵守することが重要です。
- 性別や年齢等を理由とする差別の禁止
- 厚生労働省の「公正な採用選考の基本」に則る
2つのルールについて、次項から詳しくみていきます。
性別や年齢等を理由とする差別の禁止
労働者の均等な雇用の機会と待遇の確保という観点から、次のように、一定の理由で応募者を募集・採用から排除することが法律に違反する差別として禁止されています。
- 募集又は採用にあたって、「男性歓迎」「女性向きの職種」などの表示を行うこと(男女雇用機会均等法5条)
- 募集又は採用にあたって、特別な理由なく年齢に制限を設けること(労働施策総合推進法9条)
- 障害があることを理由に不採用とすること(障害者雇用促進法第34条)
障害者雇用について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
厚生労働省の「公正な採用選考の基本」に則る
公正な採用活動を実現するため、厚生労働省は「公正な採用選考の基本」を提示しています。この考え方によると、企業は採用活動において以下の2点を遵守しなければなりません。
- 応募者の基本的人権を尊重すること
- 応募者の適性や能力に基づいた基準により行うこと
具体的には、家庭環境や生活状況など、本人の適性・能力とは無関係の事項によって合否を判断しないことが重要です。
合否に影響しないとしても、これらの事項は面接で質問しない、応募用紙に記入させないなど十分な配慮が求められます。
また、信仰している宗教や思想、社会活動への参加の有無など、“本来個人の自由であるべき事項”にも配慮する必要があります。
新卒と中途で採用基準を変える
最適な人材を採用するために、新卒採用と中途採用では異なる採用基準を定めましょう。
新卒採用では将来性のある人材を採用し、中途採用では即戦力となる人材を採用するように努めることが一般的です。
新卒採用の場合
新卒採用では人柄重視の選考活動を行いましょう。実務経験がない以上、性格や人間性、思考などをもとに合否を決めるのが基本です。例えば、以下のような事項が参考になります。
これらの事項等を参考に、応募者の雰囲気が自社の社風にマッチするか検討します。
- 熱意やモチベーション
- 面接でのコミュニケーションスキル
- アルバイト経験や課外活動
- 適性検査の結果
- 将来のキャリアビジョン
中途採用の場合
中途採用の場合、即戦力となる人材の確保が主な目的となります。そのため、人柄だけではなく、保有資格、実務経験、前職での成果なども重要な判断材料となります。
また、労働者の潜在能力を重視する“ポテンシャル採用”の場合も、完全に未経験の新卒採用とは区別する必要があります。ポテンシャル採用では、人柄に加えて、社会人としてのマナーや素質、明確なキャリアビジョン、将来性などを備えた人材を選ぶのが良いでしょう。
採用基準を明確にする
適切な採用基準として、なるべく「可」「不可」の区別ができる基準にしましょう。
【採用基準の例】
〇履歴書
必要不可欠:四年制大学卒以上、普通自動車運転免許
あればなお良い:弁護士資格、司法書士資格、社会保険労務士資格、行政書士資格
〇実技試験
必要不可欠:Wordタイピング200文字(5分以内)
あればなお良い:Wordタイピング300文字(5分以内)、文字サイズの変更、文字色の変更
〇面接
- 志望動機が明確である
- 話す内容に一貫性がある
- 当社の事業について調べている
- 当社のサイトに目を通している
- 学業以外について、1つの作業に長時間集中した経験がある
採用基準の開示義務
企業には、採用基準を開示する義務はありません。そのため、不採用とした応募者について、理由を明示することなく通知を行っても問題ありません。
採用活動をしていると、応募者から「不採用の理由を教えてほしい」といった問い合わせを受けることがあります。しかし、採用基準は会社にとって重要な情報ですので、詳細を開示するのは望ましくないと考えられます。
ただし、採用・不採用の効力を巡って裁判で争われる事例は存在します。トラブルを予防するためにも、明確な採用基準のもとに、不採用の理由を社内で記録・保存しておくことは必要でしょう。
採用基準の見直しについて
採用基準は、社内の状況や社会情勢などにより、定期的に見直すことが望ましいでしょう。応募者の選考通過率が低い場合には、採用基準が厳しくなりすぎていると考えられます。
また、有効求人倍率や、就活・転職市場のトレンドを調査することで、採用の成功率を高められるでしょう。昔ながらの価値観を大事にすることは間違いではありませんが、現代の若者とはまったく異なる人物像を想定して採用活動をしてしまうと、いつまで経っても希望する応募者が現れないおそれがあります。
企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ
企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※
企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)
会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません
※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)
この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)
執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。
近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある