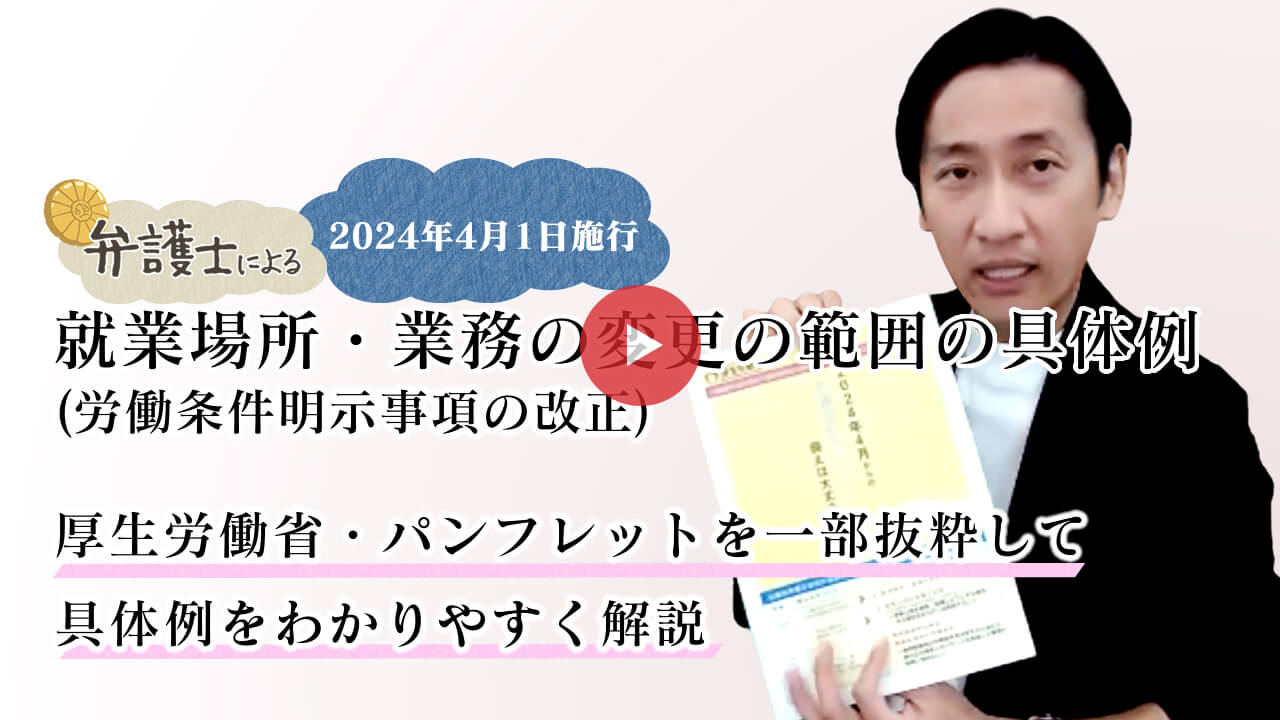労働条件の明示義務とは|明示事項やルール改正をわかりやすく解説
労働条件明示の改正概要についてYouTubeで配信しています。
2024年4月1日以降、就業の場所について、「雇い入れ直後」のみならず「変更の範囲」についても労働契約の締結時に明示することが必要となります。また、従事すべき業務の内容についても、「雇い入れ直後」のみならず「変更の範囲」についても労働契約の締結時に明示する必要があります。
動画では、改正法の施行後にこれらの「変更の範囲」について明示しなかったリスクも含めて解説しています。

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員
企業は、労働者と労働契約を締結する際、労働者に対して一定の労働条件を明示することが義務付けられています。主に労働者の保護を目的とした義務で、違反すれば罰則を受ける可能性もあります。
また、2024年4月からは明示すべき労働条件が追加されたため、事業主は漏れなく明示することが必要です。
本記事では、労働条件の明示義務がある項目、2024年4月からの改正点、明示のタイミングや方法などについて詳しく解説していきます。
目次
労働条件の明示義務とは
労働条件の明示義務とは、労働者の雇い入れ時などに、賃金や労働時間などの労働条件を本人に明示しなければならないという義務です(労働基準法15条)。正社員だけでなく、契約社員や派遣社員、パート・アルバイトなどの非正規労働者も明示の対象となります。
この義務の目的は、労働条件の引き下げを防いで労働者を保護したり、労働者の思い込みによるトラブルを回避したりすることにあると考えられます。
労働条件の明示義務に違反した場合の罰則
労働条件の明示義務に違反した場合、事業主は30万円以下の罰金が科される可能性があります(労働基準法120条1号)。また、パートタイマーや有期雇用労働者への明示を怠ると、10万円以下の過料に処されることもあります(パートタイム・有期雇用労働法31条)。
なお、罰則以外にも以下のようなリスクが想定されます。
- 労働基準監督署による行政指導の対象になる
- 労働者に未払い賃金や慰謝料を請求される
- 労働者から労働契約を解除される
- 悪質な場合は企業名が公表され、企業イメージの低下につながる
労働条件の明示事項
明示すべき労働条件は、次の2種類に分けられます。
- 法律上必ず明示しなければならない事項(絶対的明示事項)
- 使用者が定めをした場合には必ず明示しなければならない事項(相対的明示事項)
絶対的明示事項
絶対的明示事項に該当するのは、以下のものです。
- ①雇用契約の期間に関する事項
- ②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
- ②就業の場所、従事すべき業務に関する事項
- ③始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
- ④賃金(退職金、賞与を除く)の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切・支払いの時期、昇給に関する事項
- ⑤退職に関する事項
これらの労働条件については、適切なタイミングで必ず労働者に明示する必要があります。
なお、シフト勤務の場合も、始業時刻や終業時刻、休日などの決め方について、基本的なシフトパターンと併せて記載するのが望ましいとされています。
単に「労働時間はシフトにより決定する」などの記載では不十分なため注意が必要です。
相対的明示事項
相対的明示事項に該当するのは、以下のものです。
- ①退職金(労働者の範囲、退職手当の決定・計算・支払の方法及び支払いの時期)に関する事項
- ②臨時の賃金や賞与及び最低賃金額
- ③労働者に負担させる食費や作業用品の費用
- ④安全及び衛生に関する事項
- ⑤職業訓練に関する事項
- ⑥災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
- ⑦表彰及び制裁に関する事項
- ⑧休職に関する事項
退職金や賞与の支給など、上記に関わる制度を実施している企業では、該当する事項について労働者に明示する必要があります。
【2024年4月】労働条件明示ルールの改正
2024年4月の法改正に伴い、以下4つの労働条件も明示義務の対象に追加されました。
【全労働者が対象】
・就業場所、業務の変更の範囲
【有期雇用労働者が対象】
・更新上限の有無と内容
・無期転換申込機会
・無期転換後の労働条件
それぞれ具体的に解説していきます。
就業場所・業務の変更の範囲
雇い入れ直後の就業場所や業務だけでなく、将来的に変わり得る就業場所や業務の範囲まで明示することが義務付けられました。例えば、配置転換によって移る可能性のある部署や支店、出向の可能性がある企業や業務内容などを具体的に定めなければなりません。
なお、これは正社員だけでなく“パートタイム”や“契約社員”なども対象なので、異動の可能性がある場合は忘れずに明示しましょう。
就業場所や業務の範囲が明確になることで、労働者は自身のライフプランを立てやすくなります。また、想定外の異動を命じられ、労働トラブルに発展するといったリスクを防ぐことも期待できます。
更新上限の有無と内容
有期雇用労働者に対しては、契約更新の期間や回数の上限についても明示することが義務付けられました。例えば、上限に達したあとの契約更新は行わない場合、「通算契約期間の上限は4年とする」「契約更新の回数は最大3回までとする」などと具体的に明示する必要があります。
この明示義務は、雇用期間に定めのある「有期雇用労働者」が対象となります。
すでに在籍している者についても、更新上限を新たに設ける場合や、従来の上限を短縮する場合は、事前に対象労働者へ説明することが必要です。書面やデータに変更点をまとめ、労働者と一緒に確認していくのが良いでしょう。
無期転換申込機会
無期転換とは、契約期間が通算5年を超える有期雇用労働者から無期雇用契約の申込みがあった場合、当該労働者を「無期雇用」とすることに使用者が承諾したものとみなすというルールです。
企業は、たとえ本人が無期転換を希望していなくても、契約更新時に「無期転換の申込みができること」や「無期転換後の労働条件」について説明する必要があります。
なお、以下の労働者には「特例措置」が適用されるため、無期転換申込権が発生するタイミングが異なります。
| 対象者 | 無期転換申込機会 |
|---|---|
| 大学などの研究者・教員など | 通算契約期間が10年を超えた場合 |
| 高度な専門的知識等を有する者(5年を超える一定期間に完了が予定されている業務に就く者) | |
| 適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた事業主の下で、60歳以上の定年後に、有期契約で継続雇用されている者 | 無期転換申込権は発生しない |
無期転換ルールの詳細は、以下のページで解説しています。
無期転換後の労働条件
企業は、有期雇用労働者が無期転換を申し込めるタイミングで、転換後の労働条件についても明示する義務があります。
転換後の労働条件については、「同一労働同一賃金」を念頭に置き、正社員の待遇とのバランスを考慮して決定することが重要です。例えば、正社員と業務内容や職務の範囲、責任の程度、配置転換の可能性が同じである場合、待遇も正社員と同じにするのが基本です。
もっとも、無期雇用労働者は「同一労働同一賃金」の対象外なので、正社員との間に待遇差を設けても違法とはなりません。しかし、不当な待遇差は労働トラブルを招き、裁判沙汰になる可能性もあるため、バランスの取れた適切な労働条件を定めることが重要です。
労働条件の明示はいつ行うのか
労働条件の明示のタイミングは、「労働契約を締結する際」と定められています(労働基準法15条1項)。なお、明示のタイミングは、以下のそれぞれの場合で異なります。
- 有期雇用契約を更新する場合
- 定年後に再雇用する場合
- 在籍出向の場合
- 新卒採用の場合
それぞれ具体的に解説していきます。
有期雇用契約を更新する場合
有期雇用労働者が契約を更新する際も、労働条件の明示が必要です。例えば、1年の契約期間が満了し、そのまま契約期間を延長するようなケースです。また、1回目の契約更新時だけでなく、契約更新の度に労働条件を明示する必要があります。
労働条件は既存のものを引き継ぐのが一般的ですが、更新時に見直すことも可能です。
定年後に再雇用する場合
定年後に労働者を再雇用する場合も、労働条件の明示が必要です。
再雇用契約を締結するタイミングで、再雇用後の労働条件についてもしっかり説明しましょう。
なお、再雇用の場合、定年前の労働条件を維持する義務はありません。
そのため、短時間勤務にしたり、出勤日数を週3日に減らしたりすることも可能です。
ただし、再雇用後の雇用形態がパートやアルバイト、契約社員の場合、「同一労働同一賃金」が適用されるため、正社員との間で不合理な待遇差を設けることはできません。
在籍出向の場合
労働者を自社に在籍したまま他社に出向させる「在籍出向」では、出向元・出向先2つの企業と雇用契約を締結することになります。そのため、出向先は労働者を受け入れる際、労働基準法15条に基づく“労働条件の明示”を行う必要があります。
ただし、通常出向元は、事前に出向先の労働条件を把握しているケースが多いです。そのため、厚生労働省のハンドブックでは、出向元が出向先に代わり、労働者に労働条件の明示を行っても問題はないとされています。
新卒採用の場合
新卒採用者については、通常、労働契約が成立するとされる採用内定時に労働条件を明示することとなると考えられます。
内定通知書に労働条件を網羅することも可能ですが、できるだけ詳細に伝えるため、別途「労働条件通知書」などを交付する例が多いです。
一方、内定を経ずに即日入社となる場合、労働条件の明示は入社時に行うことになります。
採用内定時の注意点などは、以下のページで解説しています。
労働条件の明示方法
労働条件の絶対的明示事項のうち、昇給に関する事項を除いては、口頭ではなく書面での明示が必要です。主に「労働条件通知書」や「雇用契約書」で定めるケースが多いです。書式にきまりはありませんが、厚生労働省がフォーマット※を公表しているため、活用すると良いでしょう。
また、就業規則の該当箇所をコピーして提示する方法も認められています。
なお、労働者が希望する場合は、書面の交付ではなく“メール”や“FAX”で明示することも可能です。
一方、相対的明示事項については、口頭での明示でも問題ないと考えられますが、トラブルを防ぐため雇用契約書などに記載しておくと安心です。
就業規則の写しを交付する場合
労働条件の明示は、就業規則をコピーして交付する方法も可能です。ただし、就業規則の内容に合理性があり、かつその内容が労働者に周知されていることが前提となります。
また、就業規則の該当箇所を明確にしたうえで交付しなければならないため、場合によっては余計手間が増える可能性があります。
さらに、就業規則では具体的な賃金額などを把握できないため、別途個別の「労働条件通知書」や「雇用契約書」でも明示するのが一般的です。
FAX・メール・SNSで明示する場合
労働者が希望した場合、メールやFAX、LINEなどのSNSで労働条件を明示することも可能です。出力や保存がしやすいよう、添付ファイルで送るのが基本です。
また、労働者の希望によるものだと証明できるよう、同意書などを取り交わしておくと安心です。
なお、ブログへの掲載など、第三者が閲覧できるものは認められません。また、SMS(ショートメール)は文字数に制限があるため、望ましくないと考えられます。
また、メールやSNSでは迷惑メッセージと判断される可能性もあるため、無事に受信できたかどうか本人に確認するのが良いでしょう。
企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ
企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※
企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)
会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません
※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)
この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)
執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。
近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある