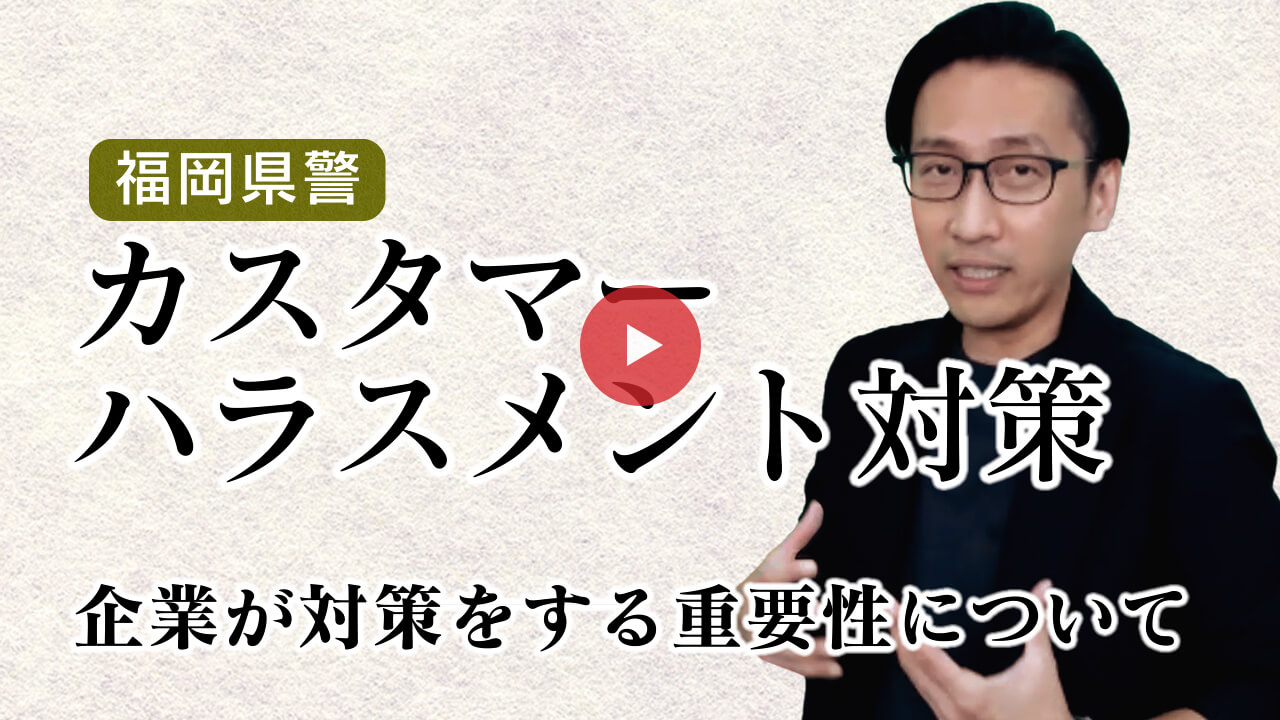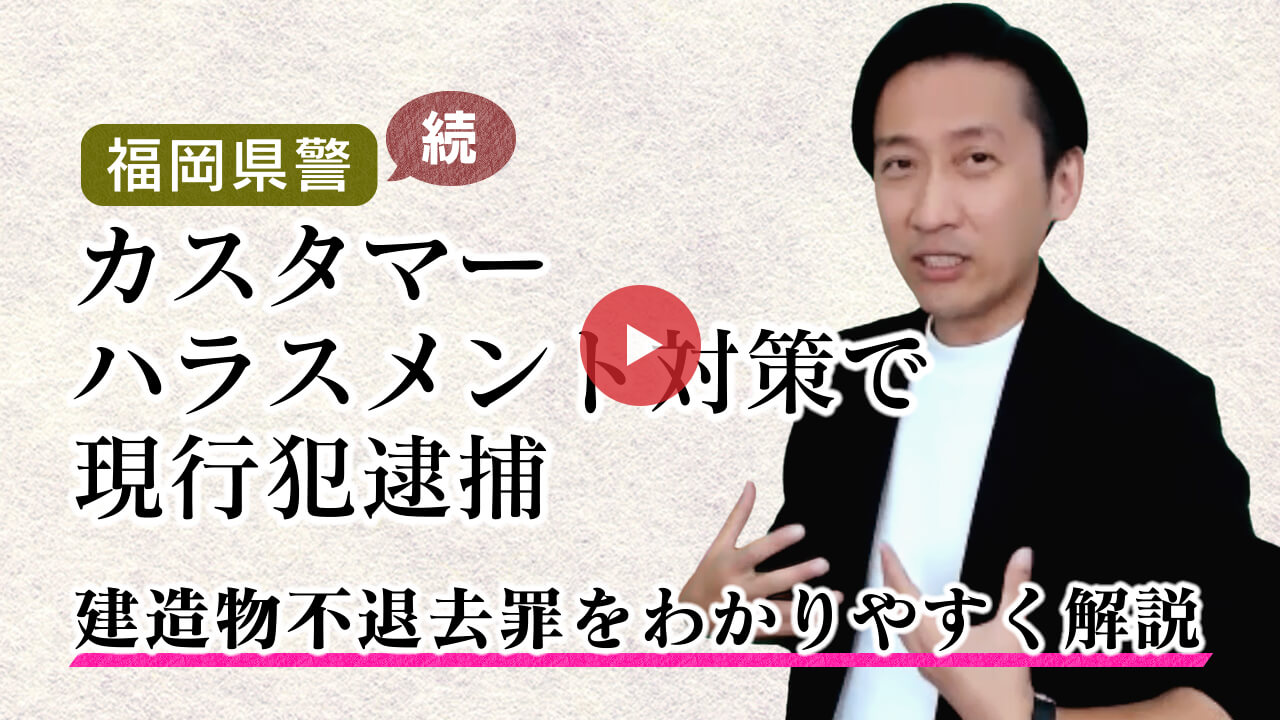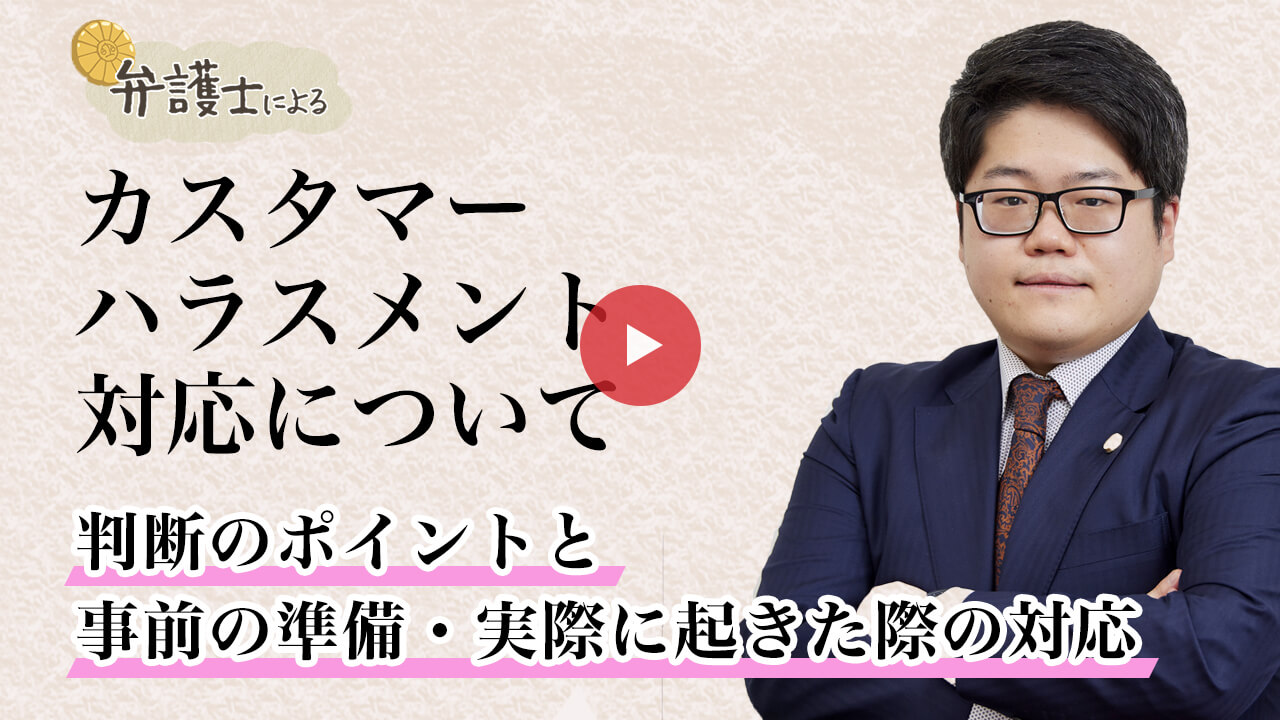福岡県警のカスタマーハラスメント対策についてYouTubeで配信しています。
福岡県警が一般企業に対してカスタマーハラスメント対策例を示したものではなく、警察官に対するカスタマーハラスメントへの対策を示しています。
動画では、福岡県警がどのような行為についてカスタマーハラスメントとして問題視しているかを取り上げた上、行き過ぎたカスタマーハラスメントがどのような刑法犯に該当しうるかを解説しています。

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員
近年、顧客などによるカスタマーハラスメント(カスハラ)が社会問題となっています。使用者は企業の「安全配慮義務」に基づき、従業員をカスハラ被害から守らなければなりません。
例えば、カスハラの典型例や対応方針を整理した「対応マニュアル」を事前に作成しておくことで、万が一発生した際にも迅速かつ適切な対応が可能になります。
そこで本記事では、カスタマーハラスメントの類型や具体例、マニュアルの作成方法、カスハラが発生した場合の流れなどをわかりやすく解説していきます。
目次
カスタマーハラスメントとは
カスタマーハラスメントとは、顧客が企業に対して“理不尽な文句”や“不当な要求”を行い、従業員の就労環境を害することをいいます。例えば、店員に土下座を強要したり、脅迫まがいの発言をしたりする行為が代表的です。
また、悪質な場合は脅迫罪や恐喝罪、威力業務妨害罪などの犯罪にあたる可能性もあります。
カスハラは従業員に身体的・精神的ダメージを与えるだけでなく、企業にも損失をもたらすおそれがあるため、早めに対処することが重要です。
厚生労働省によるカスタマーハラスメントの定義・ガイドライン
厚生労働省によると、カスタマーハラスメントは以下3つの要素を満たすものと定義されています。
- 顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行うこと
企業の顧客や施設の利用客による迷惑行為が対象となります。また、利害関係者については、法律上の利害関係だけでなく、近隣住民など実質的な利害関係を負う者も含みます。 - 社会通念上相当な範囲を超えた言動であること
言動の内容や手段・態様を踏まえ、社会的相当性を逸脱していると認められる必要があります。 - 労働者の就業環境が害されること
労働者が身体的・精神的な苦痛を負い、業務遂行に支障が生じている状態をいいます。行為が悪質な場合、1回の言動でもカスハラに該当する可能性があります。
カスタマーハラスメントとクレームの違い
カスタマーハラスメントとクレームは混同されやすいですが、目的や内容に大きな違いがあります。
「クレーム」は商品やサービスの改善を求めることが目的であり、店舗や企業への“依頼”という形で行われるのが基本です。例えば、店員の態度が不適切だった場合や、案内に誤りがあった場合、顧客から改善を求められることがあります。
これらは企業に責任があるケースも多いため、きちんと対処することでサービス向上につながると期待できます。
一方、「カスハラ」は店員への嫌がらせや不当な要求を目的に行われる迷惑行為です。早々に対処しないとますます過激化し、従業員や企業に多大な損失を与えるおそれがあるため注意が必要です。
| カスハラ | クレーム | |
|---|---|---|
| 目的 | 嫌がらせが主な目的である | 会社に改善を求めるのが主な目的である |
| 内容 | 不当な要求が含まれる場合が多い | 不満の理由が合理的である |
| 結果 | 会社にとってプラスになることが少ない | 会社が参考にするとプラスになる可能性がある |
カスタマーハラスメントの事例
カスタマーハラスメントに該当する行為は、以下のようなものです。
- 暴行・傷害などの身体的な攻撃
- 暴言・脅迫などの精神的な攻撃
- 不当な要求
- 継続的・執拗な言動
- セクシャルハラスメント
暴行・傷害などの身体的な攻撃
カスタマーハラスメントの中でも、暴行や傷害といった身体的な攻撃は、最も深刻な被害の一つです。例えば、以下のような行動は、従業員に恐怖や不安を与える重大なハラスメントです。
- 殴る、蹴る、突き飛ばす、腕を掴むなどの暴力行為
- 物を投げつける
- 机を叩く、壁を蹴る など
これらの行為は、刑法上の暴行罪や傷害罪に該当する可能性があります。
暴言・脅迫などの精神的な攻撃
暴言や脅迫などの精神的な攻撃は、従業員の尊厳を傷つけ、深刻なメンタル不調を引き起こす原因となります。例えば、以下のような言動が挙げられます。
- 「クズ」「バカ」など人格を否定する言葉
- 「殺す」「今から刺しに行く」などの脅迫的な言動
- インターネットに個人名や愚痴を投稿すること
- 容姿に対する侮辱
- 人種や国籍に関する差別的な言動 など
また、インターネット上に個人情報や誹謗中傷を投稿する行為については、名誉毀損や侮辱罪に該当する可能性があります。
不当な要求
不当な要求は、顧客の立場を利用して企業や従業員に過剰な負担を強いる行為です。例えば、以下のような言動が挙げられます。
- 土下座や謝罪の強要
- 商品に不備がないにもかかわらず、交換や金銭の支払いを要求すること
- キャンセル料の支払いの拒否
- 部屋や座席のグレードアップの要求
- 過度なサービスの要求
- 担当者を解雇するよう本部に要求すること
- 制度上不可能な要求 など
これらは業務妨害に該当する可能性があり、企業は毅然とした態度で対応し、従業員を守る体制を整える必要があります。
継続的・執拗な言動
継続的・執拗な言動は、単発ではなく繰り返し行われる迷惑行為であり、従業員の精神的負担を蓄積させます。例えば、以下のような言動が挙げられます。
- 何度も電話をかけ、同じ要求をする
- 特定の店員に対して執拗に文句を言う
- 無言電話を繰り返す
- 電話で数時間拘束する
- 炎天下のなか長時間店員を説教する など
これらの行為は、威力業務妨害罪や不退去罪に該当する可能性があり、企業は記録の保存と早期対応が求められます。
セクシャルハラスメント
セクシャルハラスメントは、性的な言動や接触によって従業員の尊厳を侵害する行為です。例えば、以下のような言動が挙げられます。
- 不必要な身体的接触(手を握る、抱きしめるなど)
- 性的な発言を繰り返す
- 盗撮行為
- 性的な関係の要求
- 執拗に食事やデートに誘う
- シフトを教えるよう強要する
- ストーカー行為
- 店内でアダルトビデオを大音量で視聴する など
これらは刑法上の強制わいせつ罪やストーカー規制法違反に該当する可能性があります。
カスタマーハラスメントが企業に与える悪影響
カスタマーハラスメントは、従業員に苦痛を与えるだけでなく、企業にも様々なダメージを与えるおそれがあります。具体的には、以下のようなリスクが想定されます。
- 離職する従業員の増加
- 企業の信用低下や業績悪化
- 従業員からの損害賠償請求
離職する従業員の増加
カスハラを受けた従業員は、身体的・精神的に大きなストレスを負います。それによって離職者や休職者が増えれば、人手不足となり、業務全体に遅れや支障が生じることが懸念されます。
また、離職者が増えた分新たな人材を雇用・育成しなければならないため、余計な手間やコストもかかります。
さらに、従業員の定着率が低い企業では、新人でも顧客対応にあたる必要があるため、クレームを招きやすいのが実情です。なかには業務に不慣れな従業員を狙ってカスハラ行為をする人もいるため、離職者の増加は企業にとって深刻な問題です。
企業の信用低下や業績悪化
近年は、ネットやSNSへの投稿によるカスタマーハラスメントも増加しています。
ネット上で企業の悪口や誹謗中傷が書き込まれると、瞬く間に拡散され、企業イメージを大きく損なうおそれがあるため注意が必要です。
たとえ投稿内容が虚偽のものであっても、一度拡散されると世間の信用を回復するには時間がかかります。その間に顧客や利用客が減り、売り上げが減少すれば、業績悪化は免れないでしょう。
また、カスハラ行為が店舗内で行われると、他の利用客にも迷惑がかかります。「巻き添えを食らうかもしれない」「ここの店を使うのはやめよう」と考え、来店を控える人も増えるでしょう。
従業員からの損害賠償請求
企業には、従業員が安心して働ける環境を整える「安全配慮義務」があります(労働契約法5条)。
カスタマーハラスメントへの対応も安全配慮義務の一環となっており、カスハラを放置したり、適切な対応を怠ったりした場合、法律違反として従業員から損害賠償請求されるおそれがあります。
使用者は日頃から顧客と良好な関係を築き、カスタマーハラスメントが発生しない職場作りに努めることが重要です。
企業の安全配慮義務については、以下のページで詳しく解説しています。
【2025年4月法改正】企業に対するカスハラ対策の義務化
2025年6月4日に可決・成立した改正労働施策総合推進法(カスハラ対策法)により、カスタマーハラスメント対策を講じることが企業の義務となりました。
具体的には、カスハラ対策を事業主の「雇用管理上の措置義務」として定め、相談窓口の設置や必要な体制の整備、カスハラ防止策の実施などに取り組むよう義務付けています。
当該義務に違反した場合、事業主は以下のような行政指導の対象となります。
- 報告徴求命令
- 助言、指導、勧告
- 企業名の公表
なお、カスハラ対策法の施行日は、2026年10月頃となる見込みです。
企業が取るべきカスタマーハラスメントの対策
カスタマーハラスメントへの対策としては、以下のようなものが効果的です。
- 基本方針の明確化と従業員への周知・啓発
- 相談窓口の設置
- カスタマーハラスメント対応マニュアルの作成
- カスハラ対応研修の実施
基本方針の明確化と従業員への周知・啓発
企業のカスハラ対策の基本方針や、取組姿勢を明確に示す必要があります。
基本方針では、主に以下のような事項について示しましょう。
- カスハラの内容
- カスハラを放置せず、従業員を守ること
- カスハラには毅然として対応すべきであること
- カスハラと思われる言動について、上司や同僚に相談してほしいこと
これらの基本方針を定めたら、従業員への周知徹底も忘れずに行いましょう。
相談窓口の設置
社内に相談窓口を設置することで、カスハラ被害の拡大を防止できる可能性があります。
具体的には、従業員がカスハラに直面した場合、速やかに相談窓口へ報告・通報する体制を整備しておくことが重要です。これにより、カスハラ被害に遭った従業員を保護できるほか、当該事案に迅速に対処することができます。
例えば、迷惑行為をした客への損害賠償請求や法的措置などを検討することも可能となります。
なお、相談窓口を設置した後は従業員にその旨を周知し、必要に応じて利用を促すことも重要です。また、外部の弁護士や機関に相談窓口を委託するのも良いでしょう。
カスタマーハラスメント対応マニュアルの作成
カスハラが発生した場合の対応について、マニュアルを作成しておきましょう。明確なマニュアルがあれば、従業員がカスハラに直面しても冷静に対処できると考えられます。
マニュアルには、カスハラ被害に遭ったときの対応フロー、注意点などをわかりやすく記載します。例えば、以下のような事項について明記しておきましょう。
- カスハラに該当する行為・言動の例
- 望ましい返答例
- カスハラの記録方法(録音や録画、メモなど)
- 相談窓口の連絡先や報告の流れ
- 緊急時の連絡先(警察署、行政機関、弁護士など)
また、マニュアル作成後は社内でしっかり周知しておくことも重要です。
企業のカスハラ対策については、以下の厚生労働省の資料もご確認ください。
カスハラ対応に関する研修の実施
従業員がカスハラ対応について理解を深めるため、定期的に研修を実施することが有効です。
使用者がマニュアルを作成しても、従業員が十分理解しているとは限りません。また、「自分には関係ない」と甘く考え、マニュアルに目を通さない者もいるでしょう。
研修の場で直接指導することで、従業員の意識が向上し、マニュアルの実効性も高まると期待できます。研修内容としては、以下のような項目について、ロールプレイなども交えながら説明すると良いでしょう。
- カスハラの判断方法
- ケーススタディ
- 苦情対応の基本的な流れ
- パターン別の対応方法
- 記録の作成方法
カスタマーハラスメントに対して企業が取るべき対応
従業員からカスハラを受けたと相談された場合、企業は以下の流れで迅速に対処する必要があります。
- 事実関係の確認
- 従業員への配慮
- 再発防止への取組
- 法的措置の検討
これらの対応について、次項より解説します。
事実関係の確認
相手の言動がカスハラに該当するかどうかを判断するため、やり取りに関する証拠を確認しなければなりません。証拠になり得るのは、以下のようなものです。
- 電話などの録音
- 防犯カメラなどによる録画
- 当事者や周囲にいた人の証言
カスハラの該当性については、必ず複数人で判断するようにしましょう。判断を誤ると相手の反感を買い、トラブルに発展するリスクが高まるためです。
また、基本的に即断は望ましくないため、その場で結論を出すのは控えましょう。
最終的にカスハラに該当すると判断した場合、カスハラ対応マニュアルに沿って対応することになります。
従業員への配慮
カスハラを受けた従業員へのケアも忘れずに行いましょう。
例えば、再び同じ顧客と対面することがないよう、担当部門を変更するなどして身の安全を確保することが第一です。また、カスハラによってメンタル不調を引き起こした場合、医師との面談や休職など精神的なケアも求められます。
被害が大きい場合、顧問弁護士や警察などへの相談も検討しましょう。
再発防止への取組
カスハラの再発を防止するために、以下のような取組が有効です。
- トラブルについての情報を社内で共有する
- トラブルを題材にして勉強会を行う
- 個人情報を隠した状態でトラブルを類型化し、ガイドラインにまとめる
- マニュアルなどの不十分だった部分を見直して、より有効なものにする
法的措置の検討
カスハラが犯罪に該当すると考えられる場合、警察への通報も検討する必要があります。そのため、通報が必要な基準や連絡先についても、マニュアルに記載しておくと良いでしょう。
カスハラで成立し得る犯罪には、以下のようなものがあります。
- 脅迫罪:生命・身体・自由・名誉・財産に対し、害を加える旨を告知して人を脅迫する
- 強要罪:生命・身体・自由・名誉・財産に害を加える旨を告知した上で、脅迫や暴行を用いて、相手に義務のないことをさせる
- 恐喝罪:脅迫・暴行を行って相手から金品を取る
- 侮辱罪:他人の人格を蔑視するような暴言を吐く
- 暴行罪:暴行を加えること(人の身体に直接接触しない有形力の行使も含む)
- 傷害罪:暴行を加えられて怪我をした
- 威力業務妨害罪:威力を用いて業務を妨害する
- 不退去罪:社屋や店舗などの私有地に居座り続けて、何度も警告しても退去しない
カスタマーハラスメントに関する裁判例
【令和2(ワ)第76号 長野地方裁判所飯田支部 令和4年8月30日判決】
〈事件の概要〉
本件は、医療機器などを販売する企業Aに勤めていた原告ら2名(以下、それぞれ「X1」・「X2」と呼称します。)が、自社の売り上げの約60%を占める顧客であった病院の企画課課長であったY2から、カッターナイフの刃を出したり引っ込めたりしながら商品の値引きを求められた事案です。原告らは、Y2及びY2を雇用する法人に対して、損害賠償を請求しました。
具体的な事実経過として、原告らは、値引きには応じなかったものの、X2が商談をまとめるためにサンプルを1個提供する旨をメモ用紙に書こうとしました。そのときに、X1は、X2が値引き額を書いてしまうと思って止めようとしたところ、Y2は苛立ち、X1の手の甲をカッターナイフで傷つけ、さらにX1の首をネックストラップで5秒から10秒ほど締めました。
なお、X1に対する暴行について、Y2は罰金15万円の有罪判決を受けており、同判決は確定しています。
〈裁判所の判断〉
裁判所は、Y2がX1に暴行を加えたことに疑いの余地はないとしました。さらに、Y2が以前にもX1に対してハンマーを振りかぶる素振りを見せており、X1がY2から日常的に暴行や脅迫などを受けていた旨を供述しているなど、原告らに対して暴行・脅迫などを日常的に繰り返していたと容易に推認できるとしました。
そして、Y2によるX1への暴行態様は、生命を脅かしかねない危険かつ悪質なものであり、X1の恐怖感や屈辱感は相当に大きかったと想像できること、Y2は有罪判決が確定してからも何ら慰謝の措置を講じていないことなどから、X1への慰謝料額は40万円が相当としました。
また、X1が傷つけられる状況を目の当たりにしたX2の恐怖感や屈辱感も相当に大きかったと容易に想像できるものの、X2はY2の暴行によって傷害を負ったことはないので慰謝料額は20万円が相当としました。
〈ポイントと解説〉
本件は、カスハラが刑事事件として立件され、有罪判決が下された事案に関連して生じた民事紛争であり、カスハラをした本人とその使用者に対する従業員の請求が一部認容されています。
本件は、カスハラが刑事事件として立件され得る悪質な行為であることを明確に示した事案であるといえます。
カスハラ対策は企業の責務であるという認識が浸透してきているため、従業員がカスハラを受けたら毅然と対応する必要があります。
加えて、採用が難しくなってきている現状においては、退職者が発生することを防止する必要性も高まってきています。
カスハラに関するよくある質問
カスハラ問題で裁判に発展した場合、カスハラの事実を裏付ける証拠にはどのようなものがありますか?
-
裁判に発展した場合、裁判官に対して「カスハラがあったこと」や「被害の大きさ」を証明する必要があります。これらの証明には客観的証拠が不可欠なので、裁判までに以下のような証拠を揃えておくことが重要です。
- 監視カメラの映像
- 電話の通話記録や録音データ
- 加害者の言動ややり取りを記録したメモ
- 目撃者の証言 など
カスハラにより従業員がメンタルヘルス不調となった場合、企業はどのような措置を取るべきでしょうか?
-
まずは上司から従業員に声をかけ、心配事や不安、トラウマなどを抱えていないか確認します。本人の精神状態に応じて、業務量の削減や勤務時間の短縮、担当部門の変更など必要な措置を検討すると良いでしょう。
上司だけで対応するのが難しい場合、産業医や産業保健スタッフなどの専門家と連携し、面談や医学的なケアも実施する必要があります。メンタル不調が深刻な場合は、一時的な休職なども検討すべきでしょう。
従業員のメンタルヘルスケアについては、以下のページで詳しく解説しています。
カスタマーハラスメント問題は弁護士にご相談ください
カスタマーハラスメントの類型を理解していないと、従業員がカスハラに直面しても適切に対処できないおそれがあります。「単なるクレームだろう」と軽い気持ちで処理してしまうと、従業員とのトラブルにも発展しかねません。
さらに、社内でカスハラ対応マニュアルを定める際も、厚生労働省のガイドラインに沿って有効なものを作成する必要があります。
弁護士は、労働法の知識だけでなく刑法の知識も有しているため、消費者のカスハラ行為により適切に対処することができます。具体的には、カスハラ対策の制度設計、相手方との交渉、損害賠償や法的措置など、事業主の方を幅広くサポートすることが可能です。
カスハラをはじめ、ハラスメント問題でお悩みでしたら、ぜひお気軽に弁護士法人ALGへご相談ください。
企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ
企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※
企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)
会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません
※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)
執筆弁護士

- 弁護士法人ALG&Associates
この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)
執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。
近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある