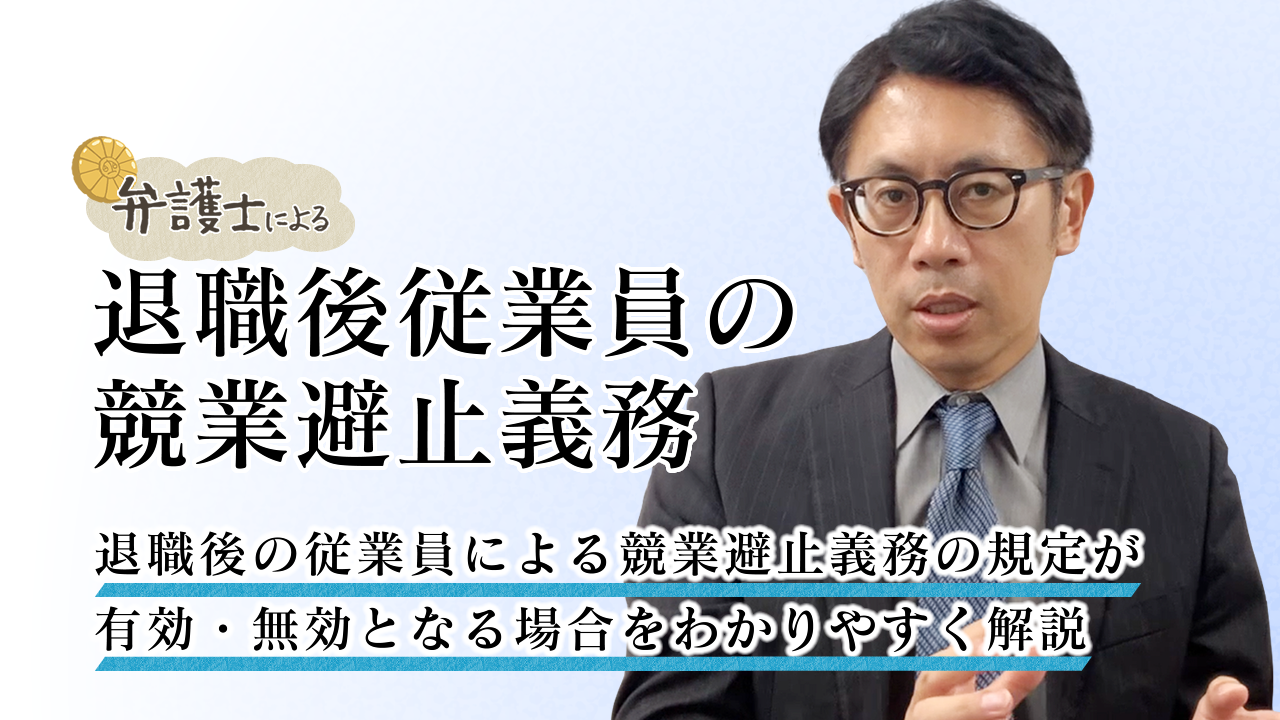監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員
競業避止義務とは、在職中や退職後の労働者に一定の競業行為を禁止するための義務です。これは企業の利益保護のために重要ですが、過度な義務を科すと違法と判断される可能性が高いため注意が必要です。
そこで本記事では、競業避止義務の有効性の判断基準、競業避止義務違反に対するペナルティ、違反行為を防ぐためのポイントなどをわかりやすく解説していきます。
目次
競業避止義務とは
競業避止義務とは、在籍中の企業と競業する他社に転職したり、自ら競業企業を設立したりしてはならないという義務です。情報漏洩防止などの観点から、使用者は労働者の競業行為を一定の範囲内で制限することが認められています。
競業避止義務の内容は、入社時の誓約書や就業規則で定めるのが一般的です。違反した労働者に対しては、損害賠償請求や競業行為の差し止めなど様々な措置を講じることができます。また、懲戒事由に該当する場合は「懲戒処分」を科すことも可能です。
競業避止義務違反があった場合の企業リスク
競業避止義務の目的は、「企業利益を不当な侵害から守ること」にあります。
競業行為をすべて容認すると、他社に自社のノウハウや企業秘密が流出し、企業利益が侵害されるおそれがあります。
また、競業企業はターゲット層が同じケースも多いため、顧客リストの持ち出しにも注意が必要です。顧客情報の流出は自社の売上に影響するだけでなく、プライバシー保護の観点からも絶対に防がなければなりません。
内部情報が外部に漏れると、情報管理があまい企業だと認識され、社会的イメージの低下にもつながります。これらのリスクを未然に防ぐため、合理的な範囲内での競業避止義務は必要なものといえるでしょう。
「職業選択の自由」を制限しないよう配慮が必要
憲法22条1項では「職業選択の自由」が保障されているため、労働者の退職後の競業は原則として自由です。退職後に競業避止義務を課すためには、職業選択の自由を損なわないよう、必要かつ合理的な範囲内で、就業規則などに明記されている必要があります。
競業避止義務の有効性を判断する6つの基準
競業避止義務の有効性については、以下の6つの基準に沿って判断されるのが一般的です。
- ①企業に守るべき利益があるかどうか
- ②競業避止義務を課す必要がある社員かどうか
- ③競業避止義務が適用される地域の定義
- ④競業避止義務の適用期間
- ⑤競業避止義務における定義の定め
- ⑥競業避止義務の代替措置が講じられているかどうか
また、競業避止義務では「副業」の可否も問題になってきます。詳しくは以下のページで解説していますので、併せてご覧ください。
1.企業に守るべき利益があるかどうか
企業に守るべき利益がある場合、競業避止義務の有効性が認められる可能性があります。
守るべき利益とは、不正競争防止法で明確に保護される「営業秘密」はもちろんのこと、それに準じるほどの価値を有する独自のノウハウ(営業方法や指導方法、集客方法など)も含むとされています。
これらの情報が競業他社に渡ると、企業に多大な損失をもたらすおそれがあるため、「競業避止義務を課してでも守るべき利益にあたる」と判断されやすい傾向があります。
2.競業避止義務を課す必要がある社員かどうか
競業避止義務の対象は、形式的な役職・職位ではなく、実際に企業が守るべき利益や情報に接していたかどうかで判断されています。そのため、正当な理由なく「従業員全員」や「特定の役職者のみ」に競業避止義務を課した場合、有効性が否定される可能性があるため注意が必要です。
例えば、管理職のみを対象とする競業避止義務でも、その者が企業の守るべき利益や情報(営業秘密やノウハウ)を取り扱っていなければ、「無効」と判断される可能性があります。
3.競業避止義務が適用される地域の定義
競業行為を禁止する地域を具体的に定めることは重要です。例えば、以下のような規定が考えられます。
- 現職の店舗から半径100メートルの範囲内
- 在職時に担当したことのある都道府県
このように地域を限定することで、労働者の職業選択の自由を過度に制限しないため、競業避止義務が有効とされる可能性があります。
ただし、禁止範囲が広すぎると「不合理」とみなされ、有効性が否定されることがあるため注意が必要です。
4.競業避止義務の適用期間
競業行為を禁止する「期間」も、合理的な範囲で定めておく必要があります。
禁止期間があまりにも長いと、労働者の職業選択の自由を過度に制約しているとして、無効と判断される可能性が高いです。
過去の裁判例をみると、「退職後おおむね1年以内」であれば有効性が認められやすい一方、禁止期間が「2年以上」になると有効性が否定される傾向があります。
ただし、具体的な期間は“業種”や“守るべき利益の程度”などによって異なるため、判断に悩む場合は弁護士に相談することをおすすめします。
5.競業避止義務における行為の定め
「禁止する競業行為の内容」も明確に定めておく必要があります。単に競業他社への転職を一般的・抽象的に禁止するのみでは、合理性がないと判断されやすいです。
一方、「在職中に知り得た顧客との取引」を禁止する、などのように禁止対象となる行為の内容を限定すれば、有効と判断される可能性があります。
例えば、
- 在職中に営業として訪問した得意先に対する営業活動
- 教育やコンサルタントを担当したクライアントへの勧誘
を禁止するという程度の限定でも、労働者の就業を過度に制約するものとはいえないとして、有効と判断した裁判例があります。
6.競業避止義務の代償措置が講じられているかどうか
競業避止義務を課す者に対しては、何らかの代替措置(みなし代替措置を含む)を講じる必要があります。つまり、競業行為を禁止する代わりに、待遇面で他の従業員よりも優遇すべきとされています。
実務上、この代替措置の有無はより重視される傾向があるため、使用者は適切な対応が求められます。例えば、以下のような措置が挙げられます。
- 高額な報酬
- 退職金の上乗せ
- 独立支援制度(資金援助やフランチャイズ契約など)
- スキルアップ支援 など
【ケース別】競業避止義務違反となる行為の例
在職中の競業避止義務違反
在職中の労働者は、労働契約を遵守しつつ、誠実に労務提供を行う義務を負っており(労契法3条4項)、この誠実義務の一環として当然に競業避止義務を負うと考えられています。そのため、仮に就業規則や雇用契約書に規定がなくても、企業に損害を与えるような競業行為は当然に禁止されます。
在職中の競業避止義務違反としては、以下のような行為が挙げられます。
- 在職中に競業会社を設立すること
- 技術職の社員が、使用者に無断で競業他社の研究開発に携わること
- 多数の社員を引き抜いて競業他社に転職すること など
在職中の労働者が競業避止義務に違反した場合、懲戒処分や損害賠償請求の対象にできる可能性があります。
退職後の競業避止義務違反
憲法22条1項で「職業選択の自由」が保障されており、労働者の退職後の競業は原則として自由です。そのため、退職後の競業避止義務が認められるためには、一定の地域や期間を定め、禁止する競業行為の内容をある程度限定したうえで、就業規則への明記や誓約書などで労働者の同意を得る必要があります。
退職後の競業避止義務違反行為の典型例としては、以下のようなものがあります。
- 企業の営業秘密やノウハウを、転職先において無断で利用すること
- 顧客リストを持ち出し、転職先で営業活動や勧誘を行うこと
- 元の職場から引き抜いた労働者に、秘密情報などを持ち出させること
これら競業行為の内容が悪質で、企業に多大な損失を与えた場合は、元従業員に損害賠償請求できる可能性があります。
取締役の競業避止義務違反
取締役とは、株主総会で選任され、会社の経営に関する意思決定を行う者をいいます。
取締役は業務執行において極めて重要な役割をもち、機密情報も多く扱うことから、競業行為が行われると企業は多大な損害を負う可能性があります。そのため、在任中の取締役の競業避止義務は会社法によって特別に規定され、一般社員とは区別されています(会社法356条)。
取締役の競業避止義務違反の例としては、以下のようなケースがあります。
- 飲食チェーンを経営する企業の取締役が、同じ事業を展開する別会社を設立すること
- 製薬会社の取締役が、同じ業種の企業の役員に就任すること
なお、取締役の競業避止義務は“在任中”に課せられるものなので、“退任後”は基本的に制約を受けません。
競業避止義務に違反した従業員への対応
有効な競業避止義務契約が成立しているにもかかわらず、同業社への転職といった競業行為が行われると、企業は様々なリスクを負います。
そこで、競業避止義務に違反した労働者に対しては以下のようなペナルティを課すことが可能です。
- 競業行為の停止
- 懲戒処分
- 退職金の減額又は不支給
- 損害賠償請求
これらのペナルティは競業行為の抑止力にもなるため、就業規則などで明示しておきましょう。
競業行為の停止
競業行為をすぐにやめるよう、労働者に交渉する方法です。
なお、労働者が交渉に応じない場合は差止め請求訴訟を提起して争うことになりますが、判決が確定するまでに1年以上かかるケースも珍しくありません。
そこで、訴訟の提起と併せて、裁判所に「違反行為の差止めの仮処分」を申し立てる方法があります。
差止めの仮処分とは、早急に行為を止めないと重大な損害が発生する可能性が高い場合に、裁判所から労働者に対して、競業行為を停止するよう命令を出してもらう手続きです。
これにより、判決が出るまでに被害が拡大するのを防ぐことができます。
懲戒処分
在職中の労働者であれば、懲戒処分の対象になる可能性があります。
懲戒処分の種類は
- 戒告
- 訓戒
- 減給処分
- 出勤停止
- 諭旨解雇
- 懲戒解雇
などがありますが、いきなり重い処分を科すと「不当な処分」だと訴えられ、無効になるおそれがあります。そのため、まずは注意や指導を徹底し、それでも競業行為をやめない場合に、軽い懲戒処分から科していくのが基本です。
労働者の態度があまりにも悪質な場合や、企業の損失が大きい場合、もっとも重い懲戒解雇も検討する必要が出てくるでしょう。
懲戒処分の内容や基準については、以下のページで詳しく解説しています。
退職金の減額または不支給
競業避止義務違反は企業に対する背信行為なので、退職金を減額または不支給にするという制裁も考えられます。また、退職後の競合行為については、退職金の一部または全部の返還を命じる方法もあります。
しかし、退職金には「賃金の後払い」や「生活保障」といった性質があるため、仮に就業規則に規定があっても、大幅な減額は認められない可能性が高いです。
一般的には、競業行為の内容や程度、企業の損失などを考慮し、著しい背信性が認められる場合にのみ退職金の減額・不支給は可能とされています。
退職金を減額・没収・不支給とする際の注意点は、以下のページで詳しく解説しています。
損害賠償請求
競業行為によって企業に損失が生じた場合、労働者に対して損害賠償金を請求できる可能性があります。具体的な金額は、以下のような損害の種類によって異なります。
●逸失利益:競業行為がなければ得られるはずだった売上などの利益
●無形損害:会社の信用棄損や社会的イメージの低下
逸失利益については、例えば過去の注文履歴から、受注の蓋然性が高い売上金額をもとに算定する方法があります。
一方、無形損害は認められにくい傾向があり、競業行為がよほど悪質な場合や、逸失利益の賠償だけでは賄えないほどのダメージを受けた場合などに限り認められています。
競業禁止義務違反を防止するための方法
競業避止義務違反を防止するためには、社内規定をしっかり整備し、労働者に周知しておくことが重要です。具体的な対策としては、以下のような方法が挙げられます。
- 就業規則に明記する
- 契約書を締結する
- 副業を許可制にする
- 社内教育を実施する
就業規則に明記する
競業避止義務の内容は、就業規則に明記し、労働者に周知しておく必要があります。具体的には、以下のような規定を定めるのが一般的です。
第○条(競業避止義務)
従業員は、在職中及び退職から6ヶ月間は、競合他社に就職すること及び競合する事業を営むことを禁ずる。
また、違反時のペナルティ(損害賠償請求、差し止め請求、懲戒処分など)も具体的に定めることが重要です。
ただし、就業規則は会社全体のルールを定めたものなので、個別的なケースにまでは対応していません。そのため、就業規則の他に個別の「誓約書」も取り交わしておくのが望ましいといえます。
また、競業避止義務規定の追加は「労働条件の不利益変更」にあたるため、基本的に労働者から個別に同意を得たうえで行う必要があります。
不利益変更を行う際の流れや注意点は、以下のページで解説しています。
また、就業規則の作成手順については以下のページをご覧ください。
誓約書を締結する
競業避止義務を課す場合、就業規則だけでなく個別の「誓約書」も取り交わすのが一般的です。
誓約書では、「禁止する競業行為の内容、期間、地域、違反時のペナルティ」などを具体的に定めます。これらは労働者の地位や役職、業務内容などによって異なるため、個別に定めることで労働者の理解を深めることができます。
なお、誓約書は“入社時”と“退職時”どちらも取り交わすケースが多いです。これにより、在職中だけでなく退職後も一定の競業避止義務を課すことが可能となります。
副業を許可制にする
副業は競業避止義務に抵触するおそれがあるため、必ず許可制にして、事前申請を義務づけることが重要です。また、許可制のルールは「副業規定」として就業規則に明記し、社内で周知しておく必要があります。
許可制にすることで、企業は副業の内容を事前に把握し、競業避止義務に違反していないかチェックできます。そのため、違反行為の未然防止のために効果的です。
社内教育を実施する
労働者に競業避止義務の重要性を理解してもらうため、定期的に教育や研修を実施すると効果的です。
競業避止義務の内容や期間、地域などを具体的に説明すると、労働者の理解が深まり、無意識のうちに違反行為をしてしまうといった事態も防ぐことができます。
また、違反時のリスクや企業への影響なども説明することで、労働者の意識を高めることができるでしょう。
競業避止義務の有効性が問われた裁判例
事件の概要
司法試験予備校講師であった者が、自らが所属していた会社より独立し、新たに司法試験・公務員試験に特化した予備校を設立したところ、所属していた会社より競業避止義務規定に反するとして営業禁止仮処分命令の申立がされた事件です。
本件においては、①競業避止義務を定める特約及び就業規則の有効性、②就業規則を変更し、労働者に対して新たに競業避止義務を課すことの有効性、③会社退職後2年の競業避止義務を定める特約の有効性が主な争点として争われました。
裁判所の判断
裁判所は、労働者が競業避止義務を課すことにつき会社と合意している場合、もしくは、会社が確保しようとしている利益に照らし、競業行為の禁止の内容が必要最小限度にとどまっており、かつ、十分な代償措置を執っていると判断できる場合には、競業避止義務を定める特約及び就業規則は有効であると判断しました。
また、裁判所は、競業避止義務規定を労働者の同意なく新たに設けることは原則的には許容されないものの、新たに作成された就業規則が合理的なものであり、その必要性及び内容の両面から見て、労働者が被る不利益の程度が大きくないと言える場合には、就業規則を変更し、労働者に対して新たに競業避止義務を課すことが認められると判断しました。
さらに、会社退職後2年の競業避止義務を定める特約の有効性については、競業行為を禁止することの合理的な説明がなされておらず、競業行為が禁止される場所的な制限がなく、かつ退職した労働者に対して支払われた退職金が僅か1000万円程度であったことを鑑みれば、競業禁止期間が2年という短期間であったとしても、当該労働者に対して、競業避止義務を課すことは、公序良俗に反し無効であると判断しました。
競業避止義務の規定やトラブルの対処法については弁護士にご相談ください
競業避止義務を課すことは企業にとって重要ですが、従業員には憲法によって「職業選択の自由」が保証されているため慎重な判断が必要です。また、競業行為を制限する適切な期間、地域なども設定しなければならないため、対応に悩まれる使用者の方も多いでしょう。
弁護士であれば、過去の裁判例なども踏まえ、適切な競業避止義務の範囲について具体的にアドバイスできます。そのため、労働トラブルや損害の発生を未然に防ぐことが可能です。
また、万が一競業避止義務をめぐってトラブルになっても、事態を悪化させないよう法的なサポートを提供できます。
「適法な範囲で競業避止義務を課したい」とお考えの方は、ぜひ一度弁護士法人ALGにご相談ください。
企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ
企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※
企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)
会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません
※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)
執筆弁護士

- 弁護士法人ALG&Associates
この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)
執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。
近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある