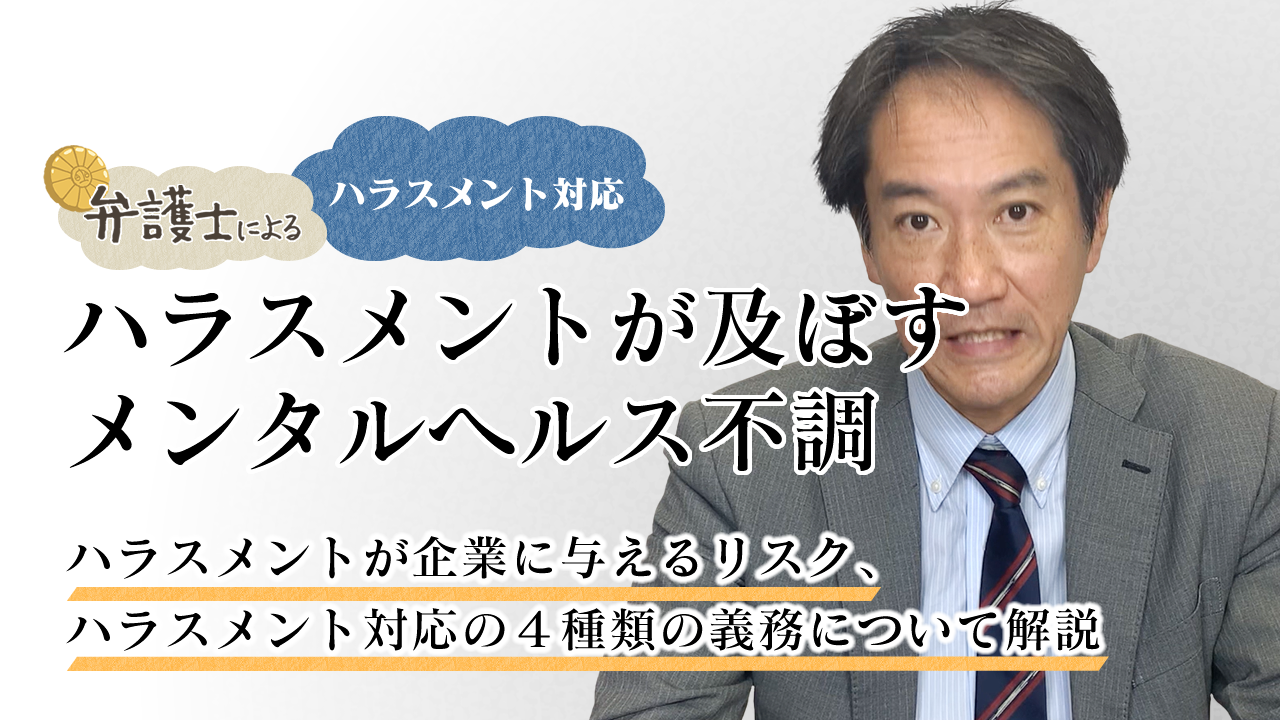監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員
上司等からのハラスメントが原因で、メンタル不調に陥る労働者は少なくありません。特に、パワハラによるうつ病の発症や自殺は後を絶たず、早急な対策が求められています。
また、メンタル不調者の増加は企業にも多大なダメージを与えるため、使用者は社内のハラスメント対策を徹底することが非常に重要です。
そこで本記事では、ハラスメントとメンタルヘルスの関連性、職場で起こりやすいハラスメントの種類、メンタル不調者が発生した場合の対応等についてわかりやすく解説していきます。
目次
ハラスメントとメンタルヘルスの関連性
メンタルヘルスとは、「心の健康状態」をいいます。例えば、「毎日が楽しい」「やる気が湧いてくる」「心が軽い」などの感覚であれば、良好なメンタルヘルスを保てているといえます。
一方、メンタルヘルスは周囲からのストレスによって崩れやすく、「ハラスメント」も大きな要因となります。例えば、上司から毎日怒鳴られる等のパワハラを受けた場合、被害者は大きなストレスを抱え、うつ病の発症等を招きやすくなるため注意が必要です。
なお、厚生労働省は「心理的負荷による精神障害の認定基準」を公表し、メンタル不調における労災認定基準を具体的に示しています。実際、近年は労働局へのハラスメントに関する相談件数が急増しており、労災が認定されるケースも増えているため、企業は一層労働者のメンタルヘルスケアに力を入れる必要があるでしょう。
職場における人間関係のストレス
職場では、自分と全く異なる性格や考え方の社員とも接しなければならないため、日々のコミュニケーション自体にストレスを感じる人もいます。そのうえ、同僚や上司からセクハラやパワハラといった悪質なハラスメント行為を受ければ、ストレスが蓄積され、心を病んでしまうのも当然といえます。
つまり、職場におけるストレスは“仕事内容”や“長時間労働”といった業務上の原因だけでなく、「人間関係」も大きく影響していることを理解する必要があります。
ハラスメントが企業に与えるリスク
社内でハラスメントが発生すると、以下のような企業リスクが起こり得ます。
- 不法行為に基づく損害賠償責任の追及(それに伴う使用者責任の追及)
- 労働契約上の安全配慮義務違反に基づく損害賠償責任の追及
- 善管注意義務及び忠実義務違反に基づく役員個人に対する損害賠償責任の追及
- 企業のイメージダウン
- 欠勤率、離職率の増加
- 生産性の低下
- 新規労働者雇用への障害
- 労災認定による金銭的、時間的損失
- 労働者からの訴訟提起
特に、ハラスメント被害を受けた労働者が自殺に至った場合、企業の金銭的・社会的リスクは甚大なものになります。遺族への損害賠償金の支払いだけでなく、事件がニュース等で報道され、社会的信用を大きく損なう可能性が高いためです。
また、損害賠償責任はハラスメントの行為者のみではなく、企業や役員個人にまで及ぶケースもあります。
ハラスメントによる企業リスクについては、以下のページでも詳しく解説しています。
メンタルヘルス不調の原因となるハラスメントの種類
メンタル不調の原因になり得るのは、以下5つのハラスメントです。
- パワーハラスメント
- セクシュアルハラスメント
- マタニティハラスメント
- カスタマーハラスメント
- その他のハラスメント
パワーハラスメント
パワーハラスメントとは、職場における地位や経験上の優位性を背景に、業務上必要な範囲を超えて相手に身体的・精神的苦痛を与える行為、または職場環境を害する行為のことです。具体的には、以下の6つのケースに分類されます。
- ①身体的な攻撃(暴行・傷害)
- ②精神的な攻撃(脅迫・侮辱)
- ③人間関係からの切り離し(無視・隔離)
- ④過大な要求(遂行不可能な業務の強制)
- ⑤過小な要求(明らかに程度の低い業務の強制、仕事を与えない)
- ⑥個の侵害(プライベートへの過度な干渉)
パワーハラスメントは、うつ病や不安症などの精神疾患を引き起こす大きな要因となります。厚生労働省の令和6年度の調査によると、精神障害による労災認定件数は過去最多を記録しており、そのうち最も多い原因が「上司などからのパワハラ」となっています。
また、パワハラは一度受けるだけでも大きなストレスがかかるため、発生を未然に防ぐことが非常に重要です。企業に求められるパワハラ対策については、以下のページをご覧ください。
セクシュアルハラスメント
セクシュアルハラスメントとは、相手方の意に反する性的言動のことです。それによって相手が不快感を抱いたり、職場に居づらいなど一定の不利益を受けたりした場合、基本的に「セクハラ」に該当するとされています。
具体的には、以下のようなパターンに分類されます。
- ①性的な発言(スリーサイズを聞く、卑猥な冗談やからかい、性的体験談を聞き出す など)
- ②性的な行動(不要な身体的接触、性的関係の要求、卑猥な写真の掲示 など)
- ③職場外での言動(酔った勢いでの性的発言、出張中に宿泊先の部屋へ呼び出す など)
セクハラは重大な人権侵害であり、発覚すれば企業の損害賠償責任も問われかねません。特に、セクハラ対策を怠った場合や、セクハラ加害者をかばうような対応をした場合、慰謝料が増額される可能性があります。
また、セクハラはセンシティブな問題なので、被害者が申告しづらいケースも多いでしょう。そのため、被害を受けてしばらく経ってから相談・通報を受けた場合も、使用者は真摯に被害者のケア等に努めることが重要です。
企業に求められるセクハラ対策や、セクハラ発生時の対応については以下のページをご覧ください。
マタニティハラスメント
マタニティハラスメントとは、女性労働者が妊娠・出産したことや、産休・育休を取得したこと等を理由に、嫌がらせや不当な扱いをする行為をいいます。具体的には、以下のような言動がマタハラに該当します。
- 妊娠したことを理由に、一方的に軽作業への転換を命じる
- 「繁忙期なのに非常識」「迷惑だから辞めた方が良い」等と嫌味を言う
- 育児休業の取得を理由に、降格や解雇する
- 産休や育休の取得を認めない
また、女性だけでなく、「男性の育児休業取得等」に対する嫌がらせもハラスメント(パタニティハラスメント)にあたるとされています。
仕事と家庭を両立する女性が増える中、マタハラの発生は企業イメージを大きく損なう原因となります。「時代遅れ」と認識され、優秀な人材の流出や応募者の減少など様々なリスクを伴います。
そのため企業は、労働者が妊娠や出産、子育てについて理解を深め、正しい知識を身に付けられるよう、研修や教育を徹底することが重要です。
企業に求められるマタハラ対策については、以下のページでも詳しく解説しています。
カスタマーハラスメント
カスタマーハラスメントとは、顧客や取引先から従業員に対して行われる、著しい迷惑行為や理不尽な苦情・クレームのことです。具体的には、以下のような言動が挙げられます。
- 従業員を殴る・蹴る、物を投げつける
- 「殺す」「家族に危害を加える」等と脅迫する
- 不当に金銭を要求する
- 土下座を強要する
- 購入後に商品を壊したにもかかわらず、返品や交換を強要する
令和7年6月の「改正労働施策総合推進法(カスハラ防止法)」の成立により、企業はカスハラについて「雇用管理上の措置」を講じることが義務付けられました。
本法の施行は2026年10月以降となりますが、“カスハラ防止策”や“カスハラ発生後の対応”については早めにルールを定めておくのが望ましいでしょう。
企業に求められるカスハラ対策については、以下のページでも詳しく解説しています。
その他のハラスメント
その他、職場で起こりやすいハラスメントには以下のようなものがあります。
- アルコールハラスメント
飲み会や懇親会の場で、お酒を飲むよう強要する行為です。また、お酒に弱いことをからかう言動等も、アルハラにあたるとされています。 - ジェンダーハラスメント
「女性はお茶くみや雑務のみ」「男性は事務職禁止」など、労働者の性別だけを理由に不当な扱いをすることです。 - エンジョイハラスメント
「仕事は楽しむものだ」という考えを周囲へ押し付けることです。例えば、仕事の楽しさを延々と語る、ネガティブな発言をした者を排除する等の行為が考えられます。
ハラスメントによるメンタルヘルス不調者への対応
ハラスメントによるメンタル不調者があらわれた場合、企業は以下の手順で適切に対応する必要があります。
- 相談を受ける
- 事実を調査する
- 適切な措置をする
- 休職と職場復帰への支援
より詳細な手順は、以下のページで紹介しています。
1.相談を受ける
ハラスメントの相談・通報があった場合、被害者への相談対応を行います。相談時は相手の話をじっくりと聞き、共感する姿勢を示すことで、被害者の不安や緊張を和らげるのがポイントです。
また、“プライバシーは守られる”旨を初めに伝えることで、より安心感を与えられるでしょう。
ただし、長時間話を聞くとかえってストレスとなるおそれがあるため、1回の相談時間は50分以内が目安とされています。
2.事実の調査をする
相談者から聞き取った内容を踏まえ、速やかに事実確認を行います。ハラスメントは放置するとより過激になり、被害が拡大するおそれがあるため、迅速に対応する必要があります。
また、行為者へのヒアリングは中立的な第三者が行いましょう。万が一被害者の認識や主張に誤りがあったとしても、報復行為は許されないことをしっかり伝えることが重要です。
被害者と行為者の主張に食い違いがある場合、部署のメンバー等にもヒアリングを行いながら当時の状況を把握することになります。
3.適切な措置を講じる
ハラスメントの態様や頻度、被害状況などを踏まえ、行為者への措置(処分)を検討します。
一般的な措置としては、
- 厳重注意や指導
- 被害者への謝罪
- 配置転換や人事異動(当事者同士の引き離し)
- 懲戒解雇
等が考えられます。
ただし、処分が重すぎると企業の“権利濫用”を問われ、措置が無効になるおそれがあります。どのような処分が妥当かお悩みの際は、弁護士に相談してみるのも良いでしょう。
なお、調査の結果ハラスメント行為が確認されなかった場合も、被害者に不利益取扱いをすることは認められません。
4.休職と職場復帰への支援
労働者がメンタル不調で休職した場合、企業は“職場環境配慮義務”の一環として「職場復帰支援」を行う必要があります。
職場復帰支援の流れについては、厚生労働省が公表する「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」で以下のように示されています。
- 病気休業開始及び休業中のケア
- 職場復帰支援プラン作成の準備
- 職場復帰の可否の判断及び職場復帰支援プランの作成
- 最終的な職場復帰の決定
- 職場復帰後のフォローアップ
心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き(厚生労働省)
ただし、休職者には一層きめ細やかな対応が求められるため、産業医や弁護士の意見を聞きながら慎重に対応を進める必要があります。復帰のタイミングや休職明けの対応を誤ると、再び休職に至るおそれもあるため注意しましょう。
休職時の手続きや注意点は、以下のページで詳しく解説しています。
ハラスメントとメンタルヘルスにまつわる裁判例
事件の概要
【平24(ワ)402号 福井地方裁判所 平成26年11月28日判決、X産業事件】
高校卒業後にY社に就職したXが、上司から執拗に人格否定的な発言をされ、うつ病を発症した後、自殺した事件です。本件では、「会社を辞めた方がみんなのためになる」「死んでしまえばいい」「相手するだけ時間の無駄」といった威圧的な発言が頻繁に繰り返されていました。
Xの遺族は、Xが自殺したのは上司のパワーハラスメントが原因であり、また過重な心理的負荷をかけるY社の業務体制にも問題があったとして、上司およびY社に対して損害賠償請求を行いました。
裁判所の判断
裁判所は、上司の発言について以下のように判断しています。
- 通常の叱責の域を超える威圧的なものであり、入社後1年未満のXに対して行われていたことも踏まえると、典型的なパワーハラスメントにあたる
- Xの心理的負荷の程度や内容に照らせば、精神障害を発症させるに足りるものであり、自殺との因果関係も認められる
また、上司のパワハラ行為は“業務上の指導”として行われたものであることから、「Y社の使用者責任」についても認容されています。
これらの判断を踏まえ、裁判所は、上司およびY社に対して約7261万円の損害賠償金の支払いを命じました。
ポイントと解説
本件のポイントは、ハラスメントによりメンタル不調が生じた場合、労働者の自殺等の責任が企業にあるという判断がなされたことです。
労災認定基準においても同様の考え方が取られていますが、この裁判例では、精神障害の発症と業務上の行為に因果関係が認められる場合には、その後の自殺についても被害者自身の意思によるものとはいえず、精神障害に起因するものとして、死亡との因果関係まで認めるという考え方が取られています。
なお、本件でハラスメント行為が認定されたのは、Xが上司の発言をノートに記録していたためです。Xの記録はハラスメントの証拠として認められ、上司やY社の責任を立証する材料となりました。
ハラスメントは安易な気持ちで行われることも多いですが、本件のようにノートの記載や日記、遺書などから行為が認定される例は少なくないため注意が必要です。
ハラスメントのない職場環境を作る重要性
ハラスメントが発生すると、企業には以下のようなリスクがあります。
- メンタル不調による休職者の発生
- 生産性の低下
- 離職者の増加
- 精神障害の発症による労災認定
- 企業イメージの低下
- 安全配慮義務違反に基づく損害賠償責任
これらのリスクを回避するため、事業者は日常的にハラスメント防止策を講じることが非常に重要です。
ハラスメント防止のために企業が講ずべき対策
企業は、労働施策総合推進法および同法のガイドラインに基づき、以下のようなハラスメント防止策を講じる必要があります。
- 事業主の方針等の明確化(ハラスメントを許さない旨のトップメッセージの発信)
- ハラスメント禁止に対する周知・啓発
- 労働者の相談に対応するための窓口の整備
- 事後の迅速かつ適切な対応(調査)の実施準備
- ハラスメントに対応した懲戒規程などの再発防止策
また、弁護士に相談しながら進めることで、実際にハラスメントが発生した場合もスムーズな対応が可能となります。
ハラスメント対応の詳細や、ハラスメント発生時の対応については、以下のページをご覧ください。
職場内でのハラスメントによるメンタルヘルス問題は弁護士にご相談ください
ハラスメントが発生すると、労働者のメンタル不調や休職者の増加、労災認定など様々なリスクが生じます。そのため、使用者はハラスメントの発生を未然に抑えることが何より重要です。
しかし、いざ対策を講じようにも、自社に適した体制を整備するのは容易ではありません。
弁護士に相談・依頼すれば、ハラスメント防止策の策定、労働者のメンタルヘルス管理、ハラスメント発生後の対応など幅広くサポートを受けることができます。
弁護士法人ALGは、ハラスメントをはじめとする労働問題に精通しており、これまで数多くの事案を解決してきました。ハラスメントや労働者のメンタルヘルス管理にお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ
企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※
企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)
会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません
※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)
執筆弁護士

- 弁護士法人ALG&Associates
この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)
執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。
近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある