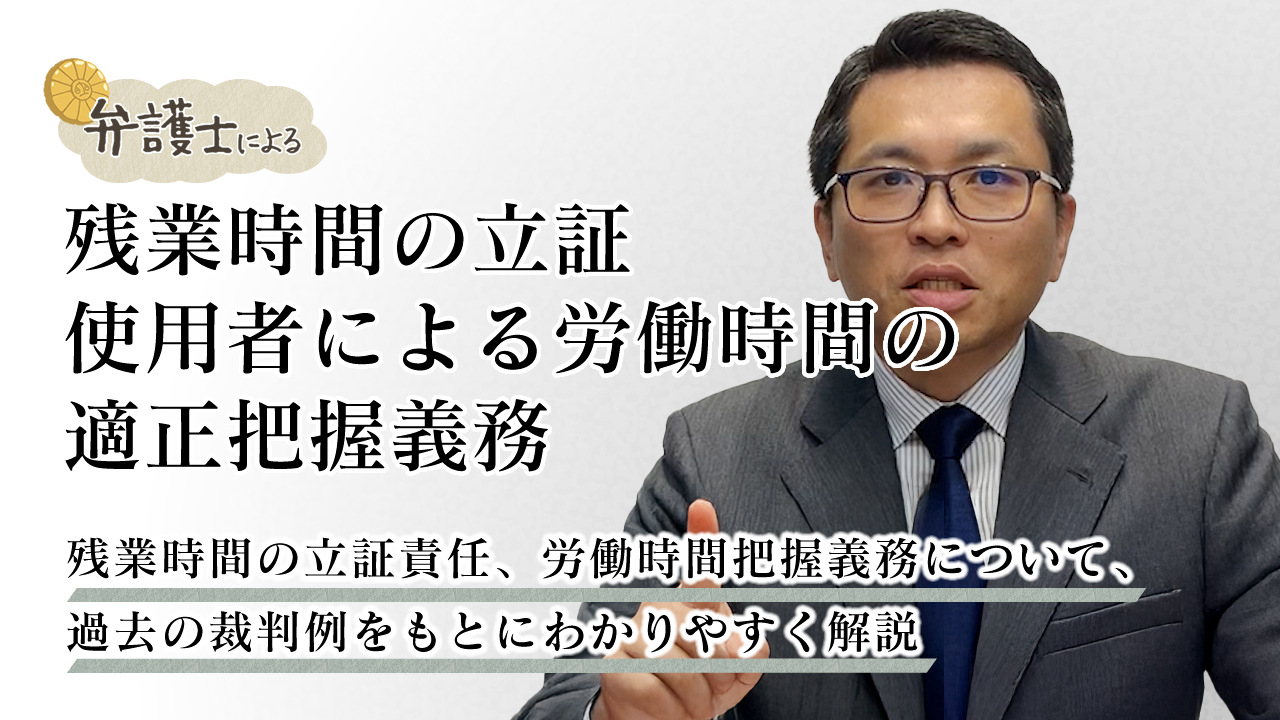監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員
会社と社員の間で、残業代に関する紛争が発生することは珍しくありません。その際の重要な争点として、「残業時間は何時間なのか」ということが問題となります。
会社が社員の残業時間を把握する方法はいくつかありますが、自己申告等の方法を用いると、後で紛争が生じた際に問題が大きくなるおそれがあります。会社も社員も、客観的に残業時間を証明できなくなってしまうため、長時間残業を行っていたと裁判等で認定されるリスクがあるからです。
ここでは、残業時間の立証責任や、労働時間把握義務等について解説します。
目次
残業代請求における残業時間の立証責任
残業代請求において、残業時間の立証責任が労働者側と使用者側のどちらにあるのかは、訴訟等で争う際に、勝敗を左右する重大な問題です。
以下で、残業時間の立証責任について解説します。
立証責任は労働者、使用者のどちらにあるのか?
残業代請求等における労働時間の立証責任は、原則として労働者側にあります。そのため、残業代が支払われていない残業を行ったことを労働者側が立証できなければ、使用者側には残業代を支払う義務が無いのが原則です。
しかしながら、訴訟等で争われた場合には、使用者側はタイムカードにおける勤怠記録等を開示することになり、そのような証拠が無い場合には、使用者側の労働時間管理に問題があったと認定されるおそれがあります。そのため、実務上は、使用者による労働時間の管理が重要だと考えられています。
残業時間の立証が争点となった裁判例
社員から未払い残業代を請求され、裁判等で争うことになった場合に、社員が詳細な労働時間の記録を残していないケースでは、会社側が有利であるように思えるかもしれません。
しかし、そのような場合であっても、会社側の労働時間管理に問題があれば、会社側の主張が認められるとは限りません。 以下で、残業時間の立証が争点となった裁判例を紹介します。
事件の概要
当該事例は、工業用ゴム製品の販売等を行う会社の従業員であった者が、会社に対し、平日の所定労働時間外勤務に対する超過勤務手当等を請求した事例です。
原告である元従業員は、1ヶ月あたり40~50時間の残業をしていましたが、上司が変わった後では残業許可願の取り扱いが厳格になり、1ヶ月あたり5~11時間程度の残業を申告していました。原告がそれ以上の残業をしていたことを示す証拠として、原告の妻が原告の帰宅時間を記載したノートがありましたが、その記載は正確性に疑問を呈されるものでした。
一方で、被告である会社は、残業許可願を提出せずに残業している従業員が多数存在していることを認識しながら黙認しており、労働基準監督署から相当長時間の超過勤務手当が支給されていない状況について是正勧告を受けたこともありました。
裁判所の判断
当該事例では、元従業員の超過勤務は明示の職務命令に基づくものではなかったこと、労働者の作業のやり方等によって残業の有無や時間が大きく左右されたこと、営業所の中で業務と関係の無い行為をしていた者が存在したこと等から、退社時刻から直ちに超過勤務時間が算出できるものではないと裁判所は認定しました。
他方、出退勤管理をしていなかったのはもっぱら会社の責任によるものとして、これを労働者にとって不利益になるように扱うべきではないという判断を示し、平均的な退社時間を認定して、元従業員が請求した未払い残業代の一部と付加金の支払いを被告会社に命じました(大阪高等裁判所 平成17年12月1日判決、ゴムノイナキ事件)。
ポイントと解説
本件では、労働者の勤務時間について、具体的な終業時刻や従事した勤務の内容が明らかではないことをもって、時間外労働の立証が全くされていないとして扱うのは相当ではないと判断されました。その上で、提出された全証拠から総合判断して、ある程度概括的に時間外労働を推認するとしているため、事実上、会社側に従業員が働いていなかったことについての立証責任が課せられたとも言える判決です。
法改正による使用者の労働時間把握義務
いわゆる働き方改革の一環として法改正が行われ、従業員の労働時間には上限が設けられました。これにより、労働時間の管理は、残業代等の金銭的な問題から、刑事罰を受けるか否かという問題になり、正確な労働時間の把握の必要性が高まりました。
労働時間の客観的把握が義務付けられた背景
平成13年、労働基準局長通達として「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」がなされました。同通達では、労働時間の適正把握が使用者の責務であることが明らかにされ、労働者の労働日ごとの始業及び終業時刻を確認し、これを記録する措置を講ずべきことが求められました。
しかし、その後も労働時間が正確に把握されていたとは言い難く、サービス残業が社会問題として認識されていました。そのような状況において、2015年に発生した過労自殺が大々的に報道され、いわゆる働き方改革の機運が大きく盛り上がり、残業時間に上限が設けられたことから、労働時間を正確に把握することが企業に求められるようになりました。
労働時間を把握すべき労働者の範囲
労働基準法に基づき、労働時間を把握すべき対象となる労働者は、いわゆる管理監督者及びみなし労働時間制が適用される労働者(事業場外労働を行う者にあっては、みなし労働時間制が適用される時間に限る。)を除くすべての労働者となっています。
労働時間を客観的に把握する方法
会社は、社員の労働時間を正確に把握しなければなりません。しかし、社員の中には、様々な理由により、労働時間を実際よりも短く申告しようとする者がいる場合があります。
このような社員を放置すると、会社から黙示の残業命令があったものとみなされて、多額の未払い残業代を支払わねばならない事態に陥りかねません。そのため、社員の労働時間は、客観的に把握する必要があります。
始業・終業時刻の厳密な記録
使用者には、労働者の労働時間を適正に把握する義務があります。労働時間の適正な把握を行うためには、労働日ごとに始業時刻や終業時刻を使用者が確認及び記録し、これをもとに労働者が何時間働いたかを把握及び確定する必要があります。
賃金台帳の記入
労働基準法第108条において、使用者は賃金台帳を作成しなければならないとされています。そして、その記載事項としては、労働日数、労働時間数、残業時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数が掲げられています。そのため、使用者は、賃金台帳にも労働時間の記録を記載しなければなりません。
労働時間に関する書類の保管
労働基準法第109条において、使用者は労働関係に関する重要な書類の保存義務を課されています。具体的には、使用者が自ら始業及び終業時刻を記録したもの、タイムカード等の記録、残業命令書及びその報告書、労働者が自ら労働時間を記録した報告書等です。
自己申告制の場合の留意点
自己申告制により始業及び終業時刻の確認や記録を行わざるを得ない場合、使用者は、労働者に対し、自己申告制の具体的内容、適正な自己申告を行ったことにより不利益な取扱いが行われることがないことなどを労働者に対して説明し、申告を阻害する措置をとらないようにする必要があります。
労働時間の把握義務における罰則
労働時間の把握は義務化されているものの、この管理を怠った会社に対する罰則はなく、あくまで努力義務となっていますが、把握せずに割増賃金の未払いが生じたときには罰則があります。また、時間外労働の上限違反については罰則も設けられたので、気付かぬうちに超過しているようなことがないように注意が必要です。
未払い残業代を請求されてお困りなら、残業問題に強い弁護士までご相談ください。
元従業員から未払い残業代等の請求をされた場合や、未払い残業代等を請求されることを予防したい場合には、専門的な知識と経験を有する弁護士に相談することをお勧めします。
会社のみの判断で対応すると、思いもよらない請求を受けて高額な残業代等を支払う事態が生じたり、元従業員との感情的な対立に発展して大きなトラブルとなってしまったりするリスクがあります。
弁護士であれば、未払い残業代の請求を予防するためのアドバイスを行うことができます。仮に請求されてしまっても、冷静に交渉し、適切な手段で対応することができますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ
企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※
企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)
会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません
※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)
執筆弁護士

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所弁護士東條 迪彦(東京弁護士会)
この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)
執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。
近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある