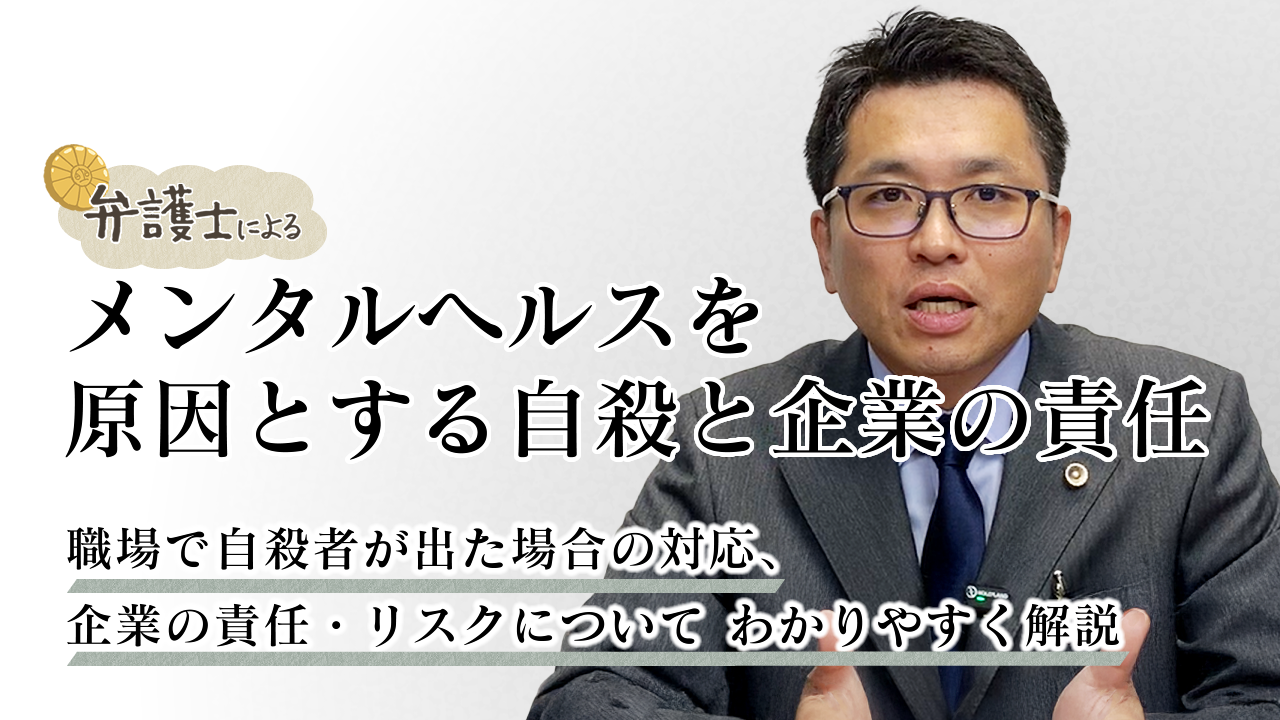監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員
従業員のメンタル不調を見逃すと、「自殺」という最悪の事態を招くおそれがあります。
従業員の自殺は非常にインパクトが強いため、企業の法的責任が問われるほか、残された従業員のケアや遺族への対応など多くの問題が生じます。
そのため企業は、従業員のメンタル不調を未然に防ぎ、生き生きと働ける環境を整備することが重要です。万が一うつ病などが発覚した場合、症状の悪化を防ぐための取り組みも徹底する必要があります。
本記事では、職場で自殺者が出た場合の企業の法的責任、自殺者が出た際に求められる対応、自殺の予防策などについて詳しく解説していきます。
目次
メンタルヘルスを原因とする自殺者の近況
厚生労働省の調査によると、令和6年度の自殺者数は2万人を超え、そのうち1万2000人以上が何らかの健康問題によって自殺していることが分かっています。
また、健康問題のなかでも「うつ病」を原因とする自殺者が最も多く、約4000人(30%以上)に上っています。
そのほか、勤務問題(職場での人間関係、役割の変化、長時間労働)を原因とする自殺者も多数いることから、職場でのストレスやメンタル不調は自殺につながりやすい深刻な問題といえます。
企業はあらためて自社のメンタルヘルス対策を見直すとともに、従業員のメンタルケアを強化することが重要です。
従業員の自殺で企業が問われる責任やリスク
従業員が自殺すると、企業も様々な責任を問われる可能性があります。
企業は従業員を雇うだけでなく、その健康や安全を守る「安全配慮義務」も負っているためです。
具体的には、以下のようなリスクが考えられます。
- 損害賠償責任
- 労災認定
損害賠償責任
従業員が自殺すると、企業は「安全配慮義務違反」による損害賠償責任を負う可能性があります。
安全配慮義務とは、従業員が安心・安全に働けるよう、職場環境に配慮しなければならないという義務です。
例えば、慢性的な長時間労働を放置し、それが原因で従業員がうつ病を発症、自殺したような場合、企業は必要な安全配慮義務を怠ったと判断される可能性があります。
遺族から損害賠償金を請求され、高額な支払いが命じられることもあるでしょう。
安全配慮義務については、以下のページで詳しく解説しています。
労災認定
うつ病が原因で自殺に至ったケースで、うつ病が労災に認定されると、「自殺の原因=仕事」だと認められることになります。そのため、企業の責任も一層大きくなると考えられます。
うつ病が労災にあたるかは、以下の要素を考慮して判断されます。
- 業務遂行性
うつ病が使用者の指揮命令下にある状態で発症したこと
例:オフィスや工場で作業していた場合、上司の許可を得てテレワークしていた場合 など - 業務起因性
うつ病と業務の間に因果関係があること
例:極度の長時間労働が続いていた場合、トラウマになるほどの嫌がらせを受けた場合 など
労災発生時の流れなどは、以下のページで解説しています。
職場で自殺者が出たときに企業が取るべき対応
職場で自殺者が出てしまった場合、企業は速やかに適切な対応をとることが求められます。また、従業員の自殺というのは非常にショッキングな出来事ですので、事務的な対応だけでなく、周囲へのケアも丁寧に行うことが重要です。
具体的には、以下の流れで対応を進めましょう。
- 初動対応
- 金銭的な清算
- 労災申請への対応
- 従業員への対応
初動対応
初動対応として、遺族への誠実な対応が求められます。葬儀に参列し、お悔やみの言葉を申し上げるなど、まずは社会人として常識的な行動をとりましょう。
なお、私物の返還や社会保険の処理など、退職にかかわる事務手続きは、初七日法要が終わった頃を目途に始めれば十分です。自殺直後は遺族も気持ちの整理がついていないため、いきなり事務的な話をするのは避けるべきといえます。
もっとも、遺族から「自殺の原因は会社にある」と訴えられる可能性はあるため、責任追及された際の備えはしておく必要があります。
具体的には、長時間労働やハラスメントの有無、自殺前の業務内容、従業員の健康状態などを把握し、自殺を予測・回避できなかったかどうか調査を進めます。
金銭的な清算
従業員が自殺すると、以下のような金銭的な問題も発生するため、漏れなく対応する必要があります。
●未払い賃金
原則として、相続人である遺族の口座に振り込みます。法定相続分に応じて支払うのが基本ですが、遺産分割協議書や遺言書の内容によっては配分率が変わることもあります。
●死亡退職金
就業規則の規定に従って支給します。受給権者の範囲や順位が相続法(民法第5編【相続】)と異なる場合も、就業規則に則って支払えば問題ありません。
●団体生命保険に基づく保険金
基本的には企業が受取人になりますが、倫理上、遺族に対して保険金の一部を支給するのが通例です。支給額について遺族と揉めるケースは多いですが、過去の判例では、会社には社内規程で定めた金額以上を支払う義務はないと判断されています。
労災申請への対応
従業員の自殺について、遺族が労災申請を行うケースは多くみられます。その場合、企業は必要書類の「事業主証明欄」に署名するなど、労災申請手続きに協力することが重要です。
署名を拒否したり、手続きを妨害したりすると、労基署に“労災隠し”などを疑われ、かえって不利になるおそれがあります。
ただし、遺族の主張に誤りがある場合、別紙に企業側の意見や調査結果などを記載し、請求書に添付するのが良いでしょう。訂正しないと遺族の主張のみが考慮され、労災認定のリスクが高まるため注意が必要です。
労災が発生した場合の初動対応については、以下のページをご覧ください。
従業員への対応
同僚や部下の自殺というのは、周囲にも多大なインパクトを与えます。それによって精神を病んだり、自殺に至ったりするケースもあるため、残された従業員のメンタルケアは非常に重要です。
特に、自殺した従業員と近しい、または親しい間柄だった者は大きなショックを受けている可能性が高いため、個別の面談を通して不安などを徐々に和らげます。面談は、産業医や臨床心理士、公認心理士などの専門家が行うのが良いでしょう。
また、自殺について社内で公表する際は、中立的な立場で冷静に事実を伝えることが重要です。
今回の事実を企業がどのように受け止めているのか、どこに課題があるのか、再発防止への取り組みなども併せて示すことで、従業員も前向きな姿勢を取り戻しやすくなります。
従業員の自殺に関する予防策
従業員の自殺を未然に防ぐには、1人1人の健康状態に応じた適切なケアを継続的に実施することが重要です。
具体的には、メンタル不調の度合いに応じて以下の3つの対策を講じることが求められます。
- ①メンタルヘルス不調の未然防止(一次予防)
- ②メンタルヘルス不調の早期発見と適切な対応(二次予防)
- ③職場復帰支援(三次予防)
厚労省『職場における心の健康づくり 労働者の心の健康の保持増進のための指針』
メンタルケアの具体例や、メンタル不調を抱えた従業員への対応については、以下のページもご覧ください。
メンタルヘルス不調の未然防止
メンタル不調を生まない、快適な職場環境を整えます。
例えば、「仕事量が多い」「プレッシャーが大きい」「人間関係が悪い」といった状況はストレスを生みやすいため、早期に発見し改善することが重要です。
また、効果的にストレス軽減を図るには、「ストレスチェック」の実施も有効です。
ストレスチェックでは、従業員が自身のストレス状態を客観的に把握できるため、積極的にセルフケアに取り組む効果が期待できます。
また、ストレスチェックの結果を集団分析することで、職場全体の環境改善にも役立つでしょう。
メンタルヘルス不調の早期発見と適切な対応
メンタル不調の早期発見を促し、悪化を防ぐための取り組みです。例えば、以下のような方法が効果的です。
- 相談窓口の設置と周知
- 定期健康診断の実施
- メンタルヘルスに関する研修や教育
これらの対策により、従業員は自分のメンタル不調にいち早く気付き、悪化防止につなげることができます。
また、企業も従業員のメンタル不調を見落とすことなく、すぐに適切な対応をとることが可能です。例えば、ストレスの程度や原因を考慮し、「配置転換」や「休職」などの措置を検討しましょう。
なお、休職などの判断にあたっては、産業医や医師の協力が不可欠です。日頃から連携をとり、いざという時すぐに対応できるようにしましょう。
また、相談窓口の担当者を「産業保健スタッフ」に任せるのも1つの方法です。
職場復帰支援
休職中の従業員がスムーズに復帰できるよう、サポート体制を整備します。また、メンタル不調の再発防止にも努める必要があります。例えば、以下のような対策が挙げられます。
- 休職者への精神的フォロー
- 時短勤務などのリハビリ出勤
- 職場復帰支援プログラムの実施
- 簡易作業への配置転換
どのような措置が必要かは、産業医や主治医に相談のうえ決定するのが基本です。復帰が早すぎたり、復帰後の仕事が合わなかったりすると、メンタル不調を再発し、すぐにまた休職に至る可能性もあるため注意が必要です。
従業員の自殺に関するよくある質問
うつ病で自殺未遂をした従業員に対し、企業はどう接するべきでしょうか?
-
企業としては、従業員が自殺未遂に至るまでの事実関係を早急に調査・確認し、うつ病の原因が企業にあると判断した場合には、従業員や家族に対して謝罪し、再発防止に向けた職場環境の整備などに速やかに取り組む必要があります。
また、場合によっては損害賠償金の支払いが必要となる場合もあるでしょう。企業の責任については、まずは事実確認をしっかり行い、従業員の自殺未遂をあらかじめ予測・回避できたかどうか検討します。例えば、タイムカードの履歴から過度な長時間労働が発覚した場合や、当事者へのヒアリングからパワハラ行為が判明した場合、企業の責任を問われる可能性が高くなります。
また、うつ病を理由に従業員が労災申請を行う場合、企業は必要書類に署名するなど協力的な姿勢をみせることも重要です。
一方、企業に責任がないと判断できる場合も、従業員や家族の気持ちに寄り添い、継続的なメンタルケアを提供するのが望ましいでしょう。
メンタルヘルス不調がみられる従業員に対し、医療機関への受診を勧めることは可能ですか?
-
医療機関への受診を勧めること自体は問題ありません。
ただし、本人が拒否した場合、受診を強制することはできないと考えられます。医療機関への受診を勧める際は、従業員のプライバシーなどに配慮し、不要なトラブルが生じないように気を付けましょう。
メンタルヘルスが原因で自殺者が出たことは公表されますか?
-
自殺者が出たからと言って、必ずしも公表されるものではありません。
ただし、極度の長時間労働が原因で自殺したような場合、「労働基準関係法令違反に係る公表事案」において、事案の概要とともに自殺者が出たことを公表されてしまう可能性があるため注意が必要です。
企業のメンタルヘルス対策については、企業労務に強い弁護士にご相談ください
従業員の自殺という最悪の事態を防ぐには、そもそもメンタル不調を生まない環境を整えるのが第一です。
仮にメンタル不調者があらわれた場合は、症状の悪化を防ぐため、速やかに適切な措置を講じなければなりません。
弁護士であれば、これら一連のメンタルヘルス対策についてトータルサポートが可能です。
また、万が一自殺未遂などが発生した際も、迅速に事実確認を進め、企業の責任の有無について法的に判断できます。従業員やその家族、遺族などへの対応についてもしっかりアドバイスできるため、トラブルとなるリスクも軽減できます。
弁護士法人ALGは、これまで数多くの企業経営をサポートしてきた実績があります。従業員のメンタルヘルス対策や、メンタル不調の従業員への対応についても熟知しているため、お悩みの方はぜひ一度ご相談ください。
企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ
企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※
企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)
会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません
※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)
執筆弁護士

- 弁護士法人ALG&Associates
この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)
執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。
近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある