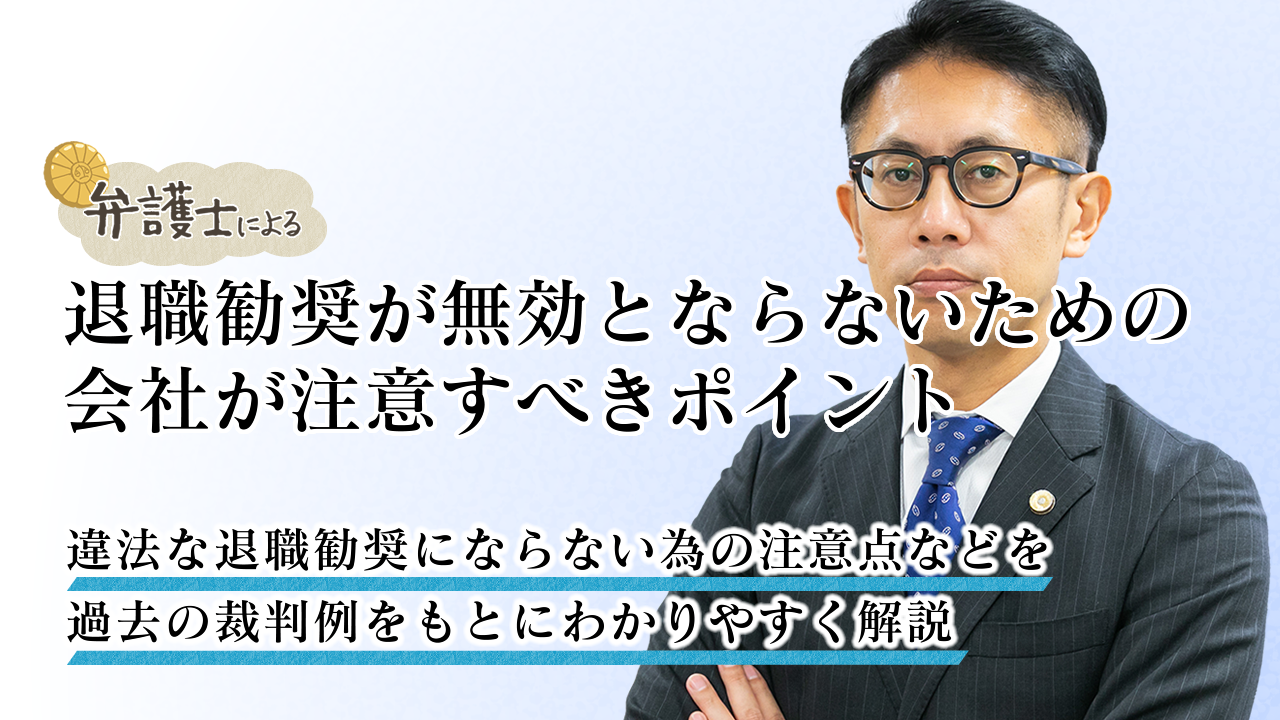監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員
会社から社員に「辞めてほしい」と伝え、退職を促す行為を「退職勧奨(たいしょくかんしょう)」といいます。退職勧奨は退職を強制するものではないので、解雇よりもトラブルになりにくいというメリットがあります。
ただし、ひとたび方法を間違えると“退職強要”とみなされ、違法になるケースもあるため対応には注意が必要です。
本記事では、退職勧奨が違法になる具体的なケース、違法とならないためのポイント、退職勧奨に応じてもらえない場合の対応などを詳しく解説していきます。
目次
退職勧奨と退職強要との違い
退職勧奨と退職強要には、次のような違いがあります。
●退職勧奨
会社から社員に対し、会社を辞めてもらうよう促す手続きです。
退職の働きかけに過ぎないため、社員は退職を断ることも可能です。また、退職に応じた場合は“合意退職”として扱われます。
●退職強要
会社が社員に対し、本人の意思にかかわらず退職を強要する手続きです。
つまり、どちらも雇用契約を終わらせるという効果は同じですが、本人の同意が必要かどうかという点に違いがあります。
退職勧奨のメリットや進め方について知りたい方は、以下のページをご覧ください。
退職勧奨が退職強要とみなされるケース
退職勧奨は、社員の自由意思による退職を促す行為です。そのため、社員に過度な心理的圧力をかけたり、本人の名誉感情を侵害したりするやり方は“退職強要”とみなされる可能性があります。
例えば、以下のようなケースは退職強要と判断される傾向があります。
- 退職勧奨を長時間、あるいは高頻度で行う
- 社員にむりやり退職を迫る
- 大人数で取り囲んで退職勧奨を行う
- 社員を侮辱したり、キャリアや人格を否定したりするような発言をする
- 退職勧奨の際に、怒鳴る、机をたたくなどして威嚇する
- 退職に追い込むことを目的とした、嫌がらせ的な配置転換や転勤命令、仕事のとりあげ
- 退職勧奨に応じなければ解雇すると伝える
違法な退職勧奨と判断されるとどのようなリスクがある?
違法な退職勧奨を行った場合、会社は以下のようなリスクを負います。
労使紛争に発展する
社員に“労働審判”や“訴訟”を起こされ、紛争に発展するおそれがあります。
特に訴訟となった場合、解決まで1年以上かかるケースも多いため、会社の手間や費用負担は大きくなると考えられます。
復職に応じなければならない
違法な退職勧奨を行った場合、退職そのものが無効になる可能性があります。その場合には、社員の希望に応じて復職を認める必要があります。また、職場を離れていた期間の賃金も全額支払わなければなりません。
社員から損害賠償請求される
違法な退職勧奨により“精神的苦痛”を負ったとして、社員に慰謝料を請求される可能性があります。慰謝料の相場は30万~100万円とされていますが、本人がうつ病などを患った場合はより高額になる傾向があります。
退職勧奨が退職強要とならないために会社が注意すべきポイント
違法な退職勧奨とみなされないよう、会社は以下の点に注意する必要があります。
- ①面談の回数・時間に配慮する
- ②面談の場所・人数に配慮する
- ③言ってはいけない言葉に注意する
- ④面談内容を記録しておく
- ⑤拒否されたらそれ以上勧めない
- ⑥条件を提示する
①面談の回数・時間に配慮する
あまりに長時間、多数回にわたる退職勧奨を行うと、社員の自由な意思を失わせる違法な退職強要と判断される可能性が高まります。
面談の回数は多くても3~4回、面談時間は1回あたり30分~1時間程度に抑えるのが安全といえます。また、適切な時間内であっても、執拗に退職を迫る言動は控えましょう。
②面談の場所・人数に配慮する
退職勧奨は、他の社員の目に入らない会議室などで行うのが適切です。他の社員の見ている前で退職勧奨を行うと、名誉棄損として訴えられる可能性があるからです。
また、狭い部屋に鍵をかけて閉じ込めるなど、社員が心理的圧迫を感じやすい環境も避ける必要があります。
さらに、会社側の人数が多いと、社員が圧迫感を感じ、本人の自由な意思決定が妨げられるおそれがあります。そのため、退職勧奨を行う担当者の人数は2人~3人程度に絞るのが適切でしょう。
③言ってはいけない言葉に注意する
退職勧奨では、以下のような発言は控える必要があります。
- 社員を侮辱する言葉
「あなたには能力がない」「他の社員の迷惑だ」「給料泥棒」など、社員の人格を否定したり、侮辱したりする発言はパワハラにあたり、違法と判断される可能性が高いです。 - 退職を強要する言葉
「退職に応じるまで部屋から出さない」「今ここで退職届を書け」「残っても仕事はない」などと退職を迫る発言は、社員の自由な意思決定を妨げる可能性が高いため、違法となります。 - 解雇をほのめかす言葉
実際には解雇できるほどの理由はないのに、「退職しなければ懲戒解雇する」「解雇になれば退職金を出さない」などと脅すような発言は認められません。これらは虚偽の説明にあたるため、たとえ社員の同意が得られても退職は無効になる可能性が高いです。 - ハラスメントにあたる言葉
多いのは、社員の妊娠や出産を理由に退職勧奨を行う「マタハラ発言」です。例えば、「育休をとられると迷惑」「妊娠中のサポートはできないから辞めてほしい」といった言葉が挙げられます。
④面談内容を記録しておく
退職勧奨の面談内容は、録音や書面により記録を残しておきましょう。いつ、誰が、どこで、どのような態様で行われたかなど具体的な記録内容を残しておくことが重要です。
記録がないと、後々社員から「退職強要された」と訴えられ、トラブルに発展するおそれがあります。また、実際には言っていないパワハラ発言や侮辱的発言も捏造され、会社の違法性を追求されかねません。
明確な記録を残すことで、労働審判や訴訟に発展した場合も、会社が適法に退職勧奨を行っていたことを証明できます。
⑤拒否されたらそれ以上勧めない
社員が退職を拒否した場合、それ以上退職を促すことは控えましょう。退職に応じるかどうかは社員の自由なので、執拗に退職を求めると違法と判断される可能性が高まります。
ただし、より社員に有利な条件を提示したうえで、再度退職を促す行為は問題ないと考えられます。例えば、退職に応じる代わりに、退職金に一定額を上乗せする方法などが一般的です。
⑥条件を提示する
退職勧奨では、退職に関する条件についても取り決める必要があります。具体的には、以下のような事項について取り決めを行います。
- 解決金の支払い(数ヶ月分の給与など)
- 退職金の上乗せ
- 退職一時金の支払い
- 退職時期
- 会社都合退職にするか、自己都合退職にするか
- 引継ぎの方法
- 有給休暇の取り扱い
なお、退職する社員にとっては、「会社都合」扱いとなる方が有利となるケースが多いです。
就業規則の定めにもよりますが、会社都合退職とすると、退職金が自己都合退職の場合よりも高額となる可能性があります。また、会社都合であればすぐに失業手当を受給できますが、自己都合では失業手当を受給できるまでに、原則3ヶ月間の給付制限があるというデメリットがあります。
社員が退職勧奨に応じない場合の対処法
社員が退職勧奨に応じない場合、「なぜ応じたくないのか」という理由を踏まえて対処法を検討することが重要です。例えば、以下のような理由が考えられます。
- 収入が途絶えることに不安がある
退職後は仕事がなくなるため、金銭面で不安を抱くのは当然です。そこで、社員が当面の生活費を確保できるよう、解決金を多めに支払う、退職金を上乗せするといった対応が求められます。
また、会社が外部企業と連携し、再就職支援を行うのもひとつの方法です。 - 退職の理由に納得がいかない
社員の能力不足などを理由に退職勧奨を行う場合、本人が自覚していないこともあります。まずは改めて注意や指導を行い、それでも改善がみられない場合は再度退職を促すのが望ましいです。
業務にどのような支障が出ているのか、具体的に説明するのも有用です。
なお、社員側に著しい問題がある場合は“解雇”も検討しなければなりません。解雇に踏み切る際の注意点などは、以下のページで解説しています。
退職勧奨の違法性について争われた裁判例
事件の概要
Y教育委員会は、私立高校教員の人事異動方針として、高年齢者に対する退職勧奨をすることを決定しました。そこで、A高校の校長は、A高校の教師であるXらに退職を打診したところ、いずれも退職する意思がない旨を表明しました。
その後、Y教育委員会はXらを呼び出し、「今年はイエスを聞くまでは時間をいくらでもかける」、「組合が要求する定員の大幅増もあなた方がいるからできない」なとど告げながら、約3ヶ月の間に十数回にわたり退職勧奨を続けていました。
また、Y教育委員会は、Xらに対し教育委員会への配置転換を内示し、Xらが退職しなければ配置転換を強行するという意向を示しました。これらを不服としたXらが、違法な退職勧奨であるとして、Y教育委員会を訴えた事案です。
裁判所の判断
【昭52(オ)405号 最高裁 昭和55年7月10日第一小法廷判決】
最高裁判所は、以下の理由から、本件の退職勧奨を違法と判断しました。
- 退職勧奨の際に、会社は退職の同意を得るために様々な説得方法を用いることができるが、社員の自発的な意思の形成を妨げたり、名誉感情を害したりするような発言をすることは許されず、そのような発言を含む退職勧奨は違法行為と判断される。
- 退職勧奨の回数や期間についての限度は、退職を求める事情等の説明や優遇措置等の退職条件の交渉などの経過によってケースバイケースであるが、説明や交渉に通常必要な限度にとどめられるべきである。
- 本件における退職勧奨は、社員の自発的な退職意思の形成のための説得の限度を超え、心理的プレッシャーを与えて退職を強要したものと認められるのが相当であり、違法である。
ポイント・解説
この事案は、退職勧奨の違法性に関する限度について、最高裁が初めて明示的に判断したものとなります。
ポイントは、退職勧奨の際、退職勧奨を受ける者の自由な意思形成を妨げていると判断されないようにするため、勧奨の回数、頻度、期間、発言内容等については気をつけなければ、退職勧奨が違法であると判断される可能性があるという判断がされている点です。
退職勧奨が違法と判断されている下級審裁判例は本事案の他にも多数ありますが、いずれも同様の考慮要素から退職勧奨の違法性を判断しています。
退職勧奨が退職強要と判断されないためにも弁護士にご相談ください
退職勧奨を行う場合は、感情的になって強い発言をしてしまう場合もあるかもしれません。
ただし、退職勧奨はあくまでお願いであり、むりやり退職を迫ったり、社員を侮辱するような発言をしたりすると、違法とされるおそれがあります。
退職勧奨を適法かつ有効に行いたいならば、弁護士への相談をご検討ください。
弁護士法人ALGは労働法務に精通する弁護士が多く在籍しています。
退職勧奨の事情をお聴きした上で、退職勧奨のタイミングや伝え方について具体的にアドバイスすることが可能です。また、退職勧奨の面談に弁護士が立ち会うこともできますので、ぜひご相談ください。
企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ
企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※
企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)
会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません
※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)
執筆弁護士

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所弁護士アイヴァソン マグナス一樹(東京弁護士会)
この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)
執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。
近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある