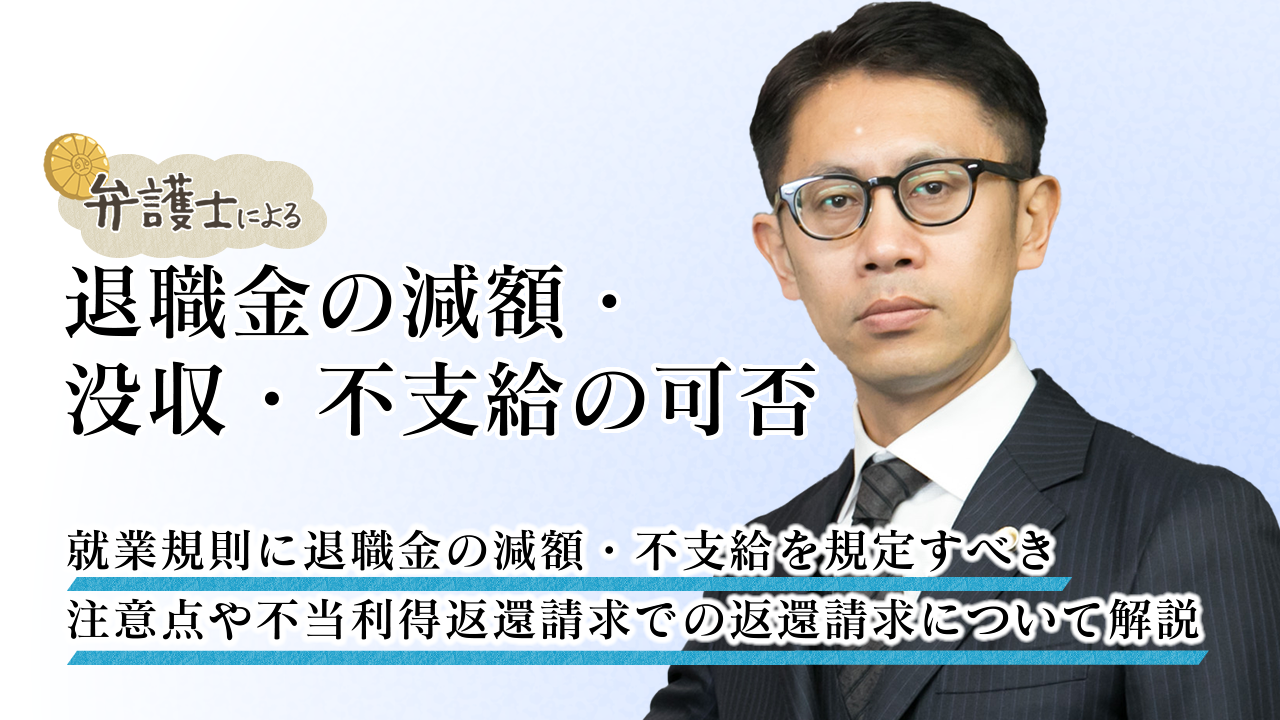監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員
就業規則に退職金規程がある場合、会社は要件を満たした社員に退職金を支払う必要があります。
しかし、社員が懲戒解雇に相当するような悪質な行為をした場合でも、退職金を全額支払わなければならないのかと疑問に思う事業主の方もいるでしょう。
そこで本ページでは、そもそも退職金の減額や不支給は認められるのか、認められるための要件などについて解説していきます。
目次
問題社員の退職金を減額・不支給とすることは可能か?
問題社員の退職金を減額・不支給とすることは可能です。そのためには、以下2つの要件を満たす必要があります。
- 就業規則や退職金規程に減額・不支給の根拠となる規定があること
- 退職金の減額・不支給が相当とされるだけの悪質な行為があること
一方、規定がない場合や、正当な理由のない減額・不支給は認められません。
なお、退職金の減額・不支給を就業規則等で定めることは、労働基準法の「賃金全額払い原則」に違反するのではないかという疑問が生じるかもしれません。
通常、退職金も賃金に含まれるため全額払いの原則は適用されますが、減額・不支給事由に当たる場合は退職金そのものが発生しないため、賃金全額払いの原則には違反しないものと考えられます。
懲戒解雇では認められる場合がある
就業規則等に、「懲戒解雇された者については、退職金を支払わないことがある」旨の定めが設けられていれば、退職金を減額・不支給とすることは可能です。
ただし、このような規定があっても、直ちに減額・不支給が認められるわけではありません。
退職金には“賃金の後払い”と“永年の功労への報償”という性質があるため、減額・不支給とするには、これまでの勤続の功績をすべて抹消してしまうか、減らしてしまうほどの悪質な行為があった場合に限定されると考えられています。
懲戒処分を行う場合の注意点や懲戒解雇についての詳細は、以下のページをご参照ください。
懲戒事由と減額・不支給の相当性について
懲戒事由に該当する行為があったからといって、必ず退職金の不支給・減額が認められるわけではありません。
判例をみても、それまでの功労を抹消・減殺するほどの著しい背信行為があった場合に限り、退職金の減額・不支給を認める傾向があります。例えば、以下のような判例が参考になります。
- 無断欠勤を理由に懲戒解雇したが、不支給には相当しないとして、一定額の退職金の支払いが命じられた事例
- 業務上横領により懲戒解雇したが、勤続年数の長さなどを考慮し、退職金の30%の支払いが命じられた事例
なお、懲戒事由に該当するものの、温情で普通解雇にとどめたというケースでは、基本的に規定通り退職金を支払う必要があります。
退職金の減額・不支給が有効と判断されるには?
退職金の減額・不支給が有効と判断されるためには、以下のような点に注意する必要があります。
- ① 退職金の減額・不支給規定を設けておく
- ② 減額・不支給の根拠となる証拠を集める
①退職金の減額・不支給規定を設けておく
退職金を減額・不支給とするには、就業規則でその要件を明確に定めておくことが重要です。減額・不支給規定がないと、懲戒解雇に相当する社員であっても、基本的に規定通り退職金を支払わなければなりません。
例えば、以下のような規定を設けるのが一般的です。
- 懲戒解雇された者には退職金を支給しない、または減額することがある
- 就業規則の服務規律に違反した者や、著しい背信行為を行った者については、退職金の減額を行うことがある
このように、実際に懲戒解雇された者だけでなく、それに準ずる行為を行った者も減額・不支給の対象としておくことでトラブルを回避しやすくなります。
また、自己都合退職の場合、退職金は満額支給しないのが一般的です。その場合も、会社都合退職と比べてどれほど減額されるのかが分かるよう、支給率を具体的に定めておく必要があります。
②減額・不支給の根拠となる証拠を集める
退職金の減額・不支給が認められるには、単に就業規則に規定を設けるだけでなく、これまでの勤続の功労を失わせてしまうほどの悪質な行為があったことを証明する必要があります。
例えば、社員が背信的行為を行ったと分かるメールや動画、横領による出入金履歴などが証拠になり得ます。また、それらの行為によって会社がどれほどの損害を被ったのか、客観的データをもとに証明できると良いでしょう。
退職後に問題行為が発覚したら退職金を没収できる?
退職後に社員の問題行為が発覚した場合、就業規則に規定があれば、退職金の返還請求が認められる可能性があります。例えば、以下のような規定を設けておく必要があります。
「退職後に懲戒解雇理由のあることが判明した場合、支払い済みの退職金の全部または一部の返還を求めることがある」
本来、懲戒解雇事由にあたる行為をした社員は退職金を受け取る権利がありません。それにもかかわらず退職金を受け取っていた場合、それは「不当利得」にあたるため、会社は返還を求めることが可能です。
ただし、退職後は当然労働契約も終了しているため、場合によっては減額・不支給(返還)が認められないこともあります。その場合は、社員の故意や過失に基づく不正行為を理由に、損害賠償請求をしていくことになるでしょう。
競業避止義務違反による退職金の没収
競業避止義務とは、退職後一定の期間、自分が勤務していた会社と競合する会社に転職したり、自ら競合会社を設立したりしてはいけないという義務です。
社員に競業避止義務を課すには、就業規則に規定を設けた上で、退職時に誓約書にサインさせるなどして個別の同意を得る必要があります。
また、競業避止義務に違反した場合の措置として、退職金の一部や全部の没収を求める条項も盛り込むのが一般的です。
競業避止義務違反による退職金の没収が認められるには、競業避止義務の定めが有効であり、かつ没収を相当とするだけの事情が求められます。退職者の在籍中の地位や職種などを踏まえて、「退職後の競業がいかなる態様で行われたか」、「会社にどれほどの損害を与えたのか」といった点を考慮し、悪質性を検討する必要があります。
競業避止義務における在職中・退職後の競業行為について知りたい方は、以下のページをご覧ください。
退職金の減額・返還をめぐる判例
競業避止義務違反を犯した場合の退職金の返還請求について、判断した判例をご紹介します。
事件の概要
A社の就業規則には、労働者が同業他社に転職する場合、退職金を減額するとの規定が存在しました。また、労働者Bは、A社を退職するに際して通常通りの金額の退職金を受け取っていました。
その後、労働者Bが同業他社に転職していることが発覚したため、A社は労働者Bに対し、退職金の半額を返還するよう求めました。
裁判所の判断
裁判所は、「退職金は功労報償的な性格をあわせもつことから、同業他社に就職した者に対する退職金を半額とすることも合理性のない措置とは言えない」と判断しました(昭和51(オ)1270号 昭和52年8月9日 最高裁 第二小法廷判決)。
ポイントと解説
当該裁判例は、制限違反の再就職をしたことにより、勤務中の功労に対する評価が減殺され、退職金の権利そのものが通常の退職と比べて半分程度しか発生しない趣旨の規定の合理性を認めています。
ただし、競業避止義務違反があったからといって直ちに退職金半額条項が有効となるわけではありません。実際のケースでは、非違・背信行為の具体的内容等に応じた減額の程度を検討する必要があります。
退職金の減額・没収・不支給でトラブルを避けるためにも弁護士法人ALGまでご相談ください
退職金を減額・不支給とすることができるか、どの程度の減額割合が適切か、退職後の退職金の没収が認められるかといった点については、過去の裁判例も参照しながら、事案ごとの個別的専門的判断が必要となります。
判断を誤ると裁判トラブルなどに発展し、後に支払いを命じられるおそれもあります。これらのリスクを回避するためには、法律の専門家である弁護士の介入が必要です。
弁護士法人ALGには労働法務に詳しい弁護士が多く在籍しており、ケースごとの最適な解決策をご提示することが可能です。問題社員の退職金でお悩みの場合は、ぜひ一度私たちにご相談ください。
企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ
企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※
企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)
会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません
※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)
執筆弁護士

- 弁護士法人ALG&Associates
この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)
執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。
近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある