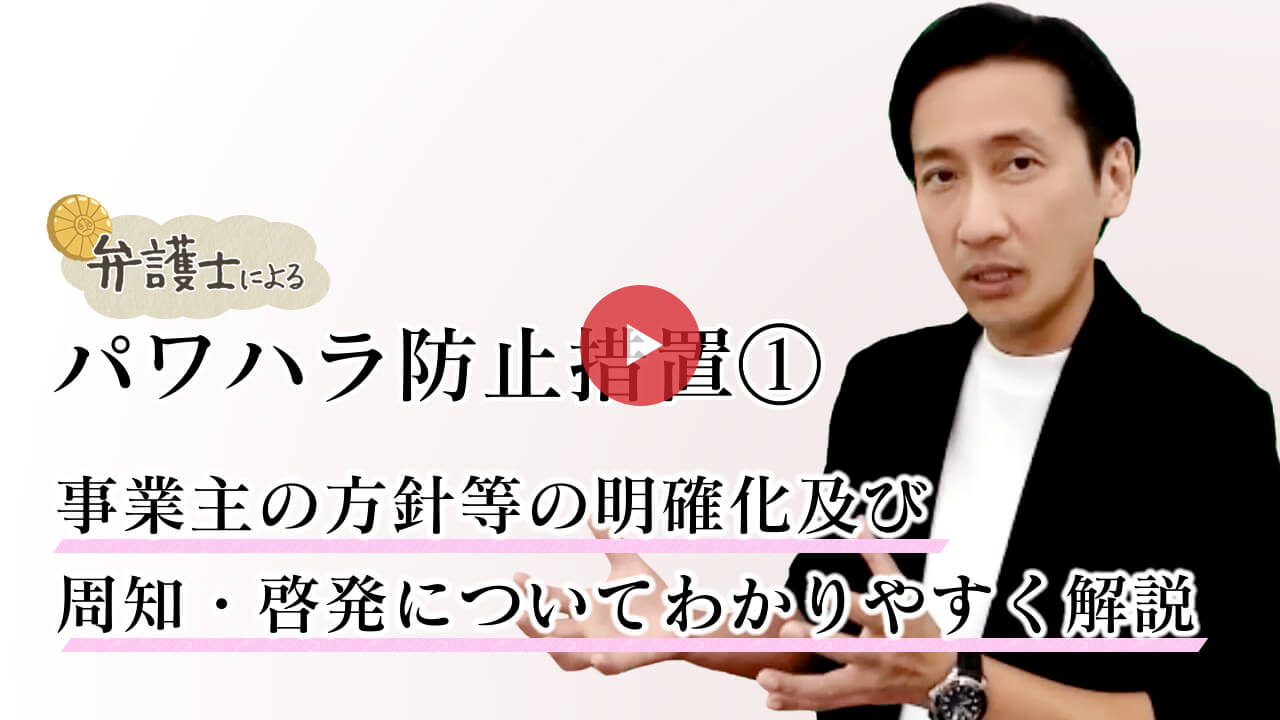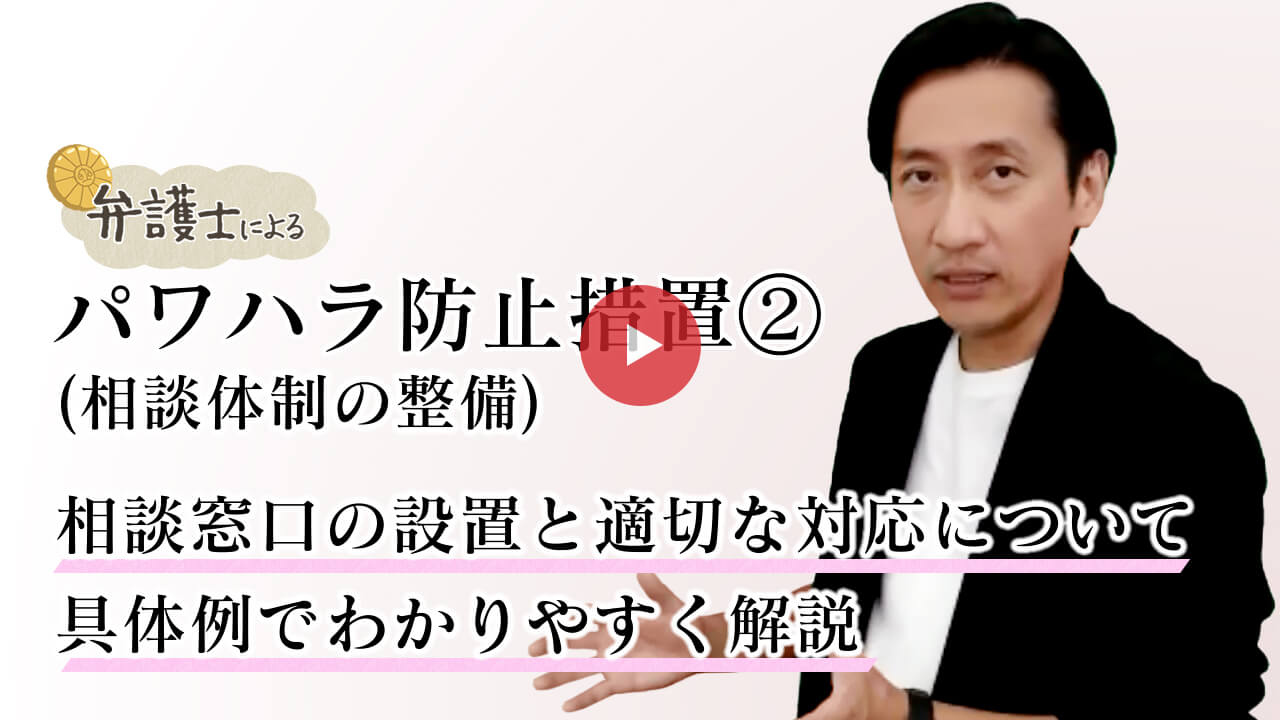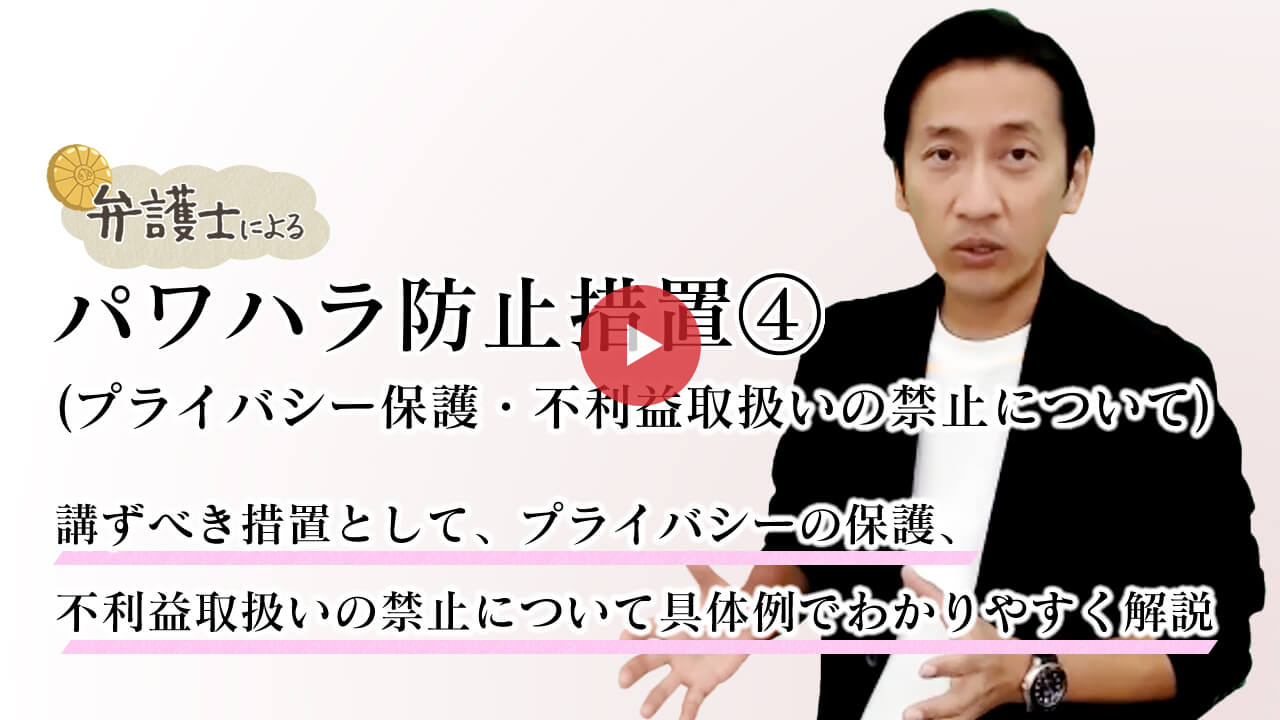パワハラ防止措置の内容についてYouTubeで配信しています。
いわゆるパワハラ防止措置の指針に基づき、企業は①事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発、②相談・苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、③職場におけるパワハラに係る事後の迅速かつ適切な対応並びに④併せて講ずべき措置をパワハラ防止措置として行わなければなりません。
動画では、これらのパワハラ防止措置の内容について、指針に沿って解説しています。

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員
2022年4月から、すべての企業に職場におけるパワーハラスメント防止対策の実施が義務付けられました。違反しても直接的な罰則はありませんが、損害賠償請求や企業イメージの悪化など、企業に多くのリスクをもたらします。
事業主が講じるべき具体的な措置は厚生労働省の指針で定められており、その内容を正しく理解し、自社に合った対策を行うことが重要です。
この記事では、企業が取り組むべきパワハラ防止措置について、わかりやすく解説します。
目次
パワハラ防止法改正によりパワハラ防止措置が義務化
2020年に施行されたパワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)により、事業主はパワハラ防止措置を講じることが義務付けられました。当初は大企業のみが対象でしたが、2022年の法改正により中小企業にも適用範囲が拡大され、現在ではすべての企業で対応が必要です。
この法律が制定された背景には、パワハラの相談件数の増加が挙げられます。
労働局へ寄せられる相談のうち、「いじめ・嫌がらせ」に関するものが急増しており、パワハラは無視できない社会問題となっています。こうした状況を受け、法整備によってパワハラ対策の強化が図られました。
パワハラ行為の具体例とは
パワハラとは、職場で⾏われる言動のうち、以下3つの要素をすべて満たすものをいいます。
【パワハラの定義】
- ① 優越的な関係を背景とした⾔動であって、
- ② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
- ③ 労働者の就業環境が害されるもの
厚生労働省は、パワハラに該当するおそれのある行為を、以下の6類型に分けて整理しています。
【パワハラの6類型】
- 身体的な攻撃
(例)叩く、足で蹴る、物を投げつける - 精神的な攻撃
(例)人前で必要以上に強く叱責する、人格を否定する発言を繰り返す - 人間関係からの切り離し
(例)労働者を仕事から外して長期間別室に隔離する、集団で無視する - 過大な要求
(例)明らかに達成不可能なノルマを課す、仕事とは無関係な私的な雑用を強制する - 過少な要求
(例)管理職を退職に追い込むため、誰でもできる業務しか与えない - 個の侵害
(例)職場外での監視、性的指向や病歴などの個人情報を本人の同意なく第三者に漏らす
パワハラの定義について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
企業に義務付けられる4つのパワハラ防止措置とは?
厚生労働省の指針では、パワハラを防止するため企業に以下の措置を講じるよう義務付けています。
- ①事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
- ②相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- ③職場におけるパワハラの事後の迅速かつ適切な対応
- ④あわせて講ずべき措置
①事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
事業主は、以下の事項について就業規則などで定め、労働者に周知・啓発する必要があります。
- パワハラの内容
- パワハラを行ってはならない旨
- パワハラを行った者に対して厳正に対処する旨
- 対処の内容
周知方法は、就業規則だけでなくパンフレット、社内報、ホームページなどの広報を利用することも可能です。また、パワハラに関する研修や講習を実施するのも有効と考えられます。
また、パワハラ行為者への対処としては、就業規則において新たに懲戒規定を設けるか、現行の懲戒処分の対象となり得る旨を明示するのが一般的です。
②相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
労働者が相談しやすい環境を作るため、事業主は以下の措置を講じることが義務付けられています。
【相談窓口の設置・周知】
- 相談に対応する担当者を定めること
- 相談に対応するための制度を設けること
- 外部の機関に相談窓口を委託すること
- 相談窓口の電話番号や担当者、利用方法について労働者に周知すること
【相談内容や状況に応じた適切な対応】
- 相談時の留意点などをまとめたマニュアルを作成すること
- 相談窓口の担当者に対し、相談に応じる姿勢や対応方法について研修を行うこと
- 相談を受けた者が、人事部などと迅速に連携できる仕組みを設けること
③職場におけるパワハラの事後の迅速かつ適切な対応
職場でのパワハラが疑われる場合、事業主は速やかに以下の措置を講じる必要があります。
【事実関係の迅速かつ正確な確認】
相談者と行為者それぞれから話を聞き、事実関係の確認を行います。双方の主張が食い違う場合、第三者へのヒアリングも行いましょう。
なお、相談者の心身の状況や当該言動が行われた際の受け止めなど、その認識にも適切に配慮する必要があります。
【パワハラ被害者への対応】
パワハラ被害者に対して、配置転換や被害者と行為者の間の関係改善に向けての援助、産業医や保健スタッフによるメンタルケアなどの配慮を行うことが求められます。
【パワハラ行為者への対処】
就業規則や服務規律に基づき、懲戒処分などを行います。また、被害者と行為者の間の関係改善に向けての援助や被害者への謝罪、被害者と引き離すための配置転換なども検討すべきでしょう。
【再発防止措置】
- パワハラを禁止する旨や、パワハラ行為は懲戒処分の対象になり得る旨を、改めて周知すること
- パワハラへの意識を高めるため、研修や講習を行うこと
パワハラ調査の進め方について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
④あわせて講ずべき措置
パワハラによる弊害を防ぐため、事業主は以下2つの措置も講じることが義務付けられています。
【プライバシー保護のための措置】
相談者や行為者のプライバシーを保護するための措置を講じる必要があります。
相談窓口の担当者へプライバシー保護に関するマニュアルを配布したり、研修を行ったりするなどして、情報管理体制を整えることが重要です。
【相談等を理由とした不利益取扱い禁止】
パワハラを相談したことや、調査への協力を理由に、解雇や降格などの不利益取扱いを受けることはない旨を定め、労働者に周知する必要があります。相談窓口の利用方法とあわせて、就業規則などに明記し、従業員が安心して声を上げられる環境を整えましょう。
法律で禁止されている不利益取扱いについての詳細は、こちらの記事をご覧ください。
パワハラの防止措置義務を怠った場合の罰則はある?
パワハラ防止法上、同法に違反したことに対して直接罰則を科す規定はありません。
ただし、厚生労働大臣は必要があると認めるときは、事業主に対する助言、指導又は勧告をすることができます(同法第33条第1項)。
同法違反に対する勧告に事業主が従わない場合には、その旨が公表される可能性もあります(同条第2項)。
また、厚生労働大臣は、事業主に対し、パワハラ防止措置の実施状況について必要な報告を求めることが可能です(同法36条第1項)。この報告要求に応じない場合や、虚偽の内容を報告した場合には、20万円以下の過料に処せられます(同法41条)。
さらに、当然ながら、パワハラ防止措置が不十分な企業ほど、パワハラが発生するリスクは相対的に高まります。パワハラが発生すると、企業は使用者責任や安全配慮義務違反を理由に、被害者から損害賠償請求を受けるおそれがある点に注意してください。
セクハラやマタハラ等の防止対策について
職場におけるセクハラや、妊娠・出産、育児休業等に関するマタハラについても、労働者の就業環境が害されないよう、防止措置を講じることが事業主に義務付けられています(男女雇用機会均等法11条、育児介護休業法25条)。
事業主に求められる対応は、基本的にパワハラ防止対策と共通しています。ハラスメントを許さない方針の明確化や相談窓口の設置、相談があった場合の迅速かつ適切な対応体制の整備などが必要です。
セクハラ・マタハラ対策について詳しく知りたい方は、以下の各ページをご覧ください。
パワハラを防ぐには職場環境の改善も重要
パワハラを防ぐには、問題発生後の対応だけでなく、職場環境そのものを改善する取組みが欠かせません。まず社内ルールを整備し、パワハラを許さない方針や、相談から調査・対応までの流れを明確にしたうえで、従業員へ周知する必要があります。あわせて、従業員や管理職を対象としたハラスメント研修を行い、パワハラへの正しい理解を深めると効果的です。さらに、定期的にパワハラに関するアンケートを行い、職場の実態や潜在的な問題を把握することで、早期対応につなぐことができます。
加えて、日頃から従業員同士で円滑なコミュニケーションを図り、意見や相談をしやすい雰囲気をつくることも必要です。これらの対策を行うことで、パワハラが起きにくい環境の実現が期待できます。
職場におけるパワハラに関する裁判例
【令和元年(ワ)第3415号 名古屋地方裁判所 令和4年12月23日判決】
事案の概要:
電車の保守業務を行うA社に勤務していた社員Xが、先輩従業員Yからパワハラを受けたとして、YとA社に損害賠償を求めた事案です。
Xは仕事上のミスを理由に、Yから日常的に「退職したほうがいい」などの暴言を浴びせられ、頭を叩くといった暴力も繰り返し受けていました。こうした行為が続いた結果、Xは目や耳にケガを負い後遺症が残ったほか、適応障害やパニック障害を発症しました。
そのためXは、Yの行為はパワハラに当たり、A社もパワハラを認識できたのに十分に対応しなかったとして、訴訟を提起しました。
裁判所の判断:
裁判所は、Yの言動について、業務上の指導という目的が一部あったとしても、暴力や退職を迫るなどの行為は行き過ぎであり、正当な指導の範囲を超える違法なパワハラであると判断しました。特に頭を叩くなどの暴力は、理由を問わず許されないと示しています。
また、裁判所は、Xの上司らが、XからYによる暴力を聞いていたことや、普段から近くで勤務していた状況から、パワハラを認識できたはずなのに、注意や是正などの対応を一切行わなかった点も問題視しました。A社は従業員が安心して働ける環境を確保すべき安全配慮義務に違反したとして、Yとともに損害賠償責任を負うと判断し、連帯して慰謝料などを支払うよう命じました。
ポイント・解説:
本判決では、上司らがパワハラの発生を把握できたにもかかわらず、十分な対応を取らなかった場合は、企業自身が安全配慮義務違反として責任を負うことが明確に示されています。
また、パワハラは上司による行為に限られないことも指摘されています。たとえ正式な役職がなくても、職場内で優位な立場にある先輩従業員の言動であれば、パワハラに該当する可能性があるため注意が必要です。パワハラを個人同士のトラブルとして片づけず、企業全体の問題として受け止め、速やかに事実を確認し、改善や再発防止に取り組むことが大切です。
パワハラ防止対策でお悩みならば弁護士にご相談ください
パワハラ防止法は大企業・中小企業すべての企業に適用されるため、措置が不十分な場合は速やかに対応する必要があります。
しかし、中小企業は人手不足などの理由から対応が遅れ、措置を講じても十分機能しないというケースが少なくありません。
企業法務に強い弁護士に依頼することで、自社に合ったパワハラ防止対策をスムーズに構築できます。また、万が一パワハラが発生しても、弁護士のサポートがあれば冷静に対処できるでしょう。
パワハラ対策についてご不安がある方は、ぜひ一度弁護士法人ALGにご相談ください。
企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ
企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※
企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)
会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません。
受付時間:平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00
平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00
※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
執筆弁護士

- 弁護士法人ALG&Associates
この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)
執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。
近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある