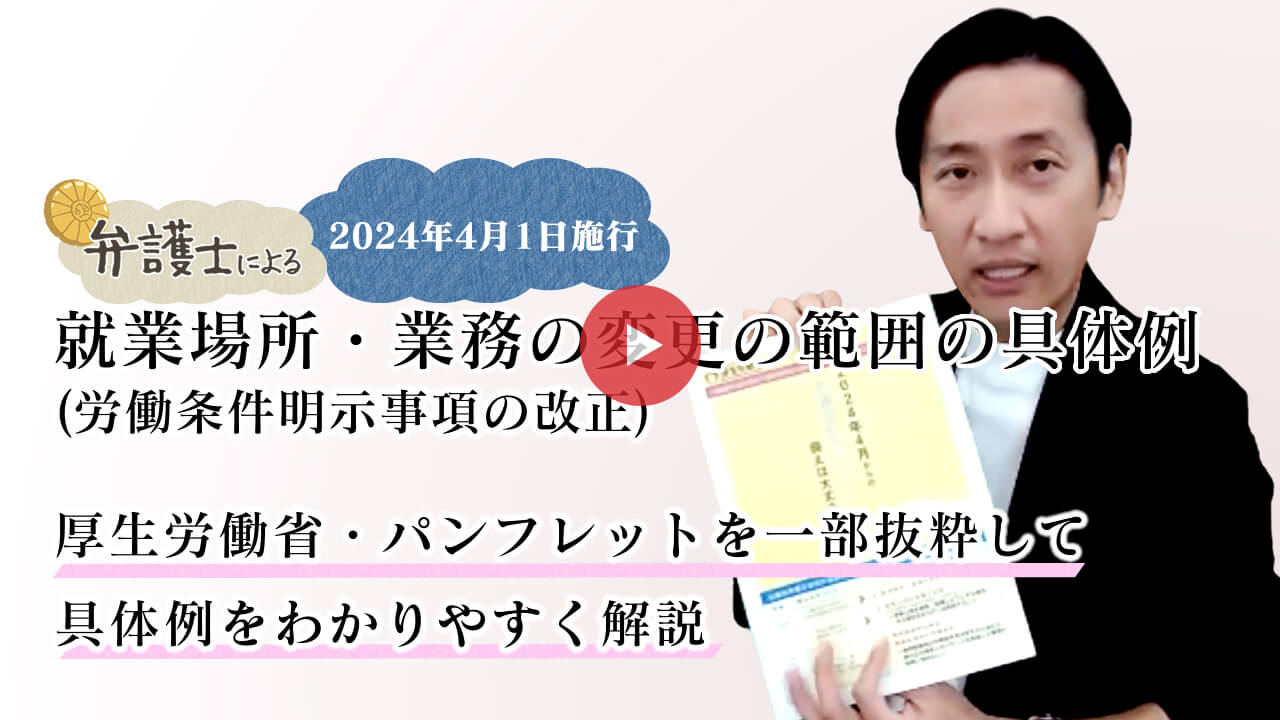労働条件の明示義務とは|明示すべき事項や方法について
労働条件明示の改正概要についてYouTubeで配信しています。
2024年4月1日以降、就業の場所について、「雇い入れ直後」のみならず「変更の範囲」についても労働契約の締結時に明示することが必要となります。また、従事すべき業務の内容についても、「雇い入れ直後」のみならず「変更の範囲」についても労働契約の締結時に明示する必要があります。
動画では、改正法の施行後にこれらの「変更の範囲」について明示しなかったリスクも含めて解説しています。

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員
会社が労働者を雇用するにあたっては、いくつかの法的規制が存在します。その中の一つが、労働者に対する労働条件明示義務です。この義務は労働者の保護などを目的としており、守らなければ罰金刑などを受けるおそれがあります。
この記事では、労働者に明示するべき内容や明示の方法、明示するべきタイミング等について解説します。
目次
労働条件の明示義務とは
労働条件の明示義務とは、労働基準法15条1項で定められている、賃金や労働時間等の労働条件を労働者に明示しなければならない義務のことです。
労働者であれば、正社員以外にも、契約社員や派遣社員、パート・アルバイト等の非正規労働者にも適用されます。
労働条件を明示する目的は、労働条件の引き下げを防いで労働者を保護することや、労働者の思い込みなどによるトラブルを回避すること等です。
労働条件の明示事項
明示するべき労働条件には、次の2種類があります。
- 法律上必ず明示しなければならない事項(絶対的明示事項)
- 使用者が定めをした場合には必ず明示しなければならない事項(相対的明示事項)
これらの明示事項について、以下で解説します。
絶対的明示事項
労働条件の絶対的明示事項は以下のとおりです。
- ①雇用契約の期間に関する事項(労働基準法施行規則5条1項1号)
- ②就業の場所、従事すべき業務に関する事項(同規則5条1項1号の2)
- ③始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項(同規則5条1項2号)
- ④賃金(退職金、賞与を除く)の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切・支払いの時期、昇給に関する事項(同規則5条1項3号)
- ⑤退職に関する事項(同規則5条1項4号)
なお、シフト勤務の場合であっても、「労働時間はシフトにより定める」等の記載をするだけでは不十分だと考えられています。始業時刻や終業時刻、休日等についての決まり方を、基本的なシフトのパターン等と併せて、なるべく明確に記載するようにしましょう。
相対的明示事項
相対的明示事項は以下のとおりになります。
- ①退職金(労働者の範囲、退職手当の決定・計算・支払の方法及び支払いの時期)に関する事項(労働基準法施行規則5条1項4号の2)
- ②臨時の賃金及び最低賃金額(同規則5条1項5号)
- ③労働者に食事、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合は、これに関する事項(同規則5条1項6号)
- ④安全及び衛生に関する定めをする場合は、これに関する事項(同規則5条1項7号)
- ⑤職業訓練に関する定めをする場合は、これに関する事項(同期毒5条1項8号)
- ⑥災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合には、これに関する事項(同規則5条1項9号)
- ⑦表彰及び制裁の定めをする場合は、種類及び程度に関する事項(同規則5条1項10号)
- ⑧休職に関する事項(同規則5条1項11号)
アルバイト・パートの労働条件の明示
正社員ではない、いわゆるパートタイマーやアルバイト等に対しても、労働者であることには変わりがないことから、労働条件の明示義務が使用者に課せられています(パートタイム労働法第6条第1項、同法施行規則第2条)。
これらの規定では、労働条件の明示を、労働契約の締結時に書面で行わなければならないことに注意が必要です。
また、労働基準法によって明示義務がある事項に追加して、次の事項について明記する義務が定められています。
- 昇給の有無
- 退職手当の有無
- 賞与の有無
- 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口
派遣労働者への労働条件の明示
派遣労働者に対しても、就労条件の明示義務が定められています(労働者派遣法34条1項)。
まず、派遣労働者に対しては、以下の書面が交付されることになっています。
- ①雇用条件(=労働条件)通知書
- ②就業条件明示書
※実務においては、両書面を実質的に1種類の書面にし、「雇用条件通知書兼就業条件明示書」を使用者が労働者に対して交付するケースが多いです
具体的に、労働基準法上の絶対的明示事項に加え、以下の内容等を記載することになります。
- 当該労働者を派遣する旨
- 派遣先での就業条件
なお、派遣労働者について全般的に知りたい方は、以下の記事を併せてご覧ください。
労働条件を明示するタイミング
労働条件を明示するべきタイミングとして、次の2つが定められています。
- ①労働契約を締結するとき
- ②契約を更新するとき(※有期労働契約の場合)
①については、基本的には採用内定のときに明示するべきだと考えられています。
また、②については、更新時に毎回明示する必要があります。
なお、労働者の募集について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
新卒採用の場合
労働条件通知書は、基本的には採用内定時に交付します。ただし、内定を出さずに即日入社とする場合等には入社日に交付すれば問題ありません。
これは、判例において、採用内定の法的性質を「労働者の労働契約の申込みに対する承諾」だと解しており、採用内定を受けたものと使用者との間に「就労の始期を大学卒業後とし、それまでの間、一定の内定取消事由に基づく解約権を留保した労働契約が成立した」と解しているからです。
なお、採用内定について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
労働条件の明示方法
労働条件を明示する方法として、昇給に関する事項を除いた絶対的明示事項は、基本的に書面での明示が必要です。書面としては、労働条件通知書や雇用契約書などが用いられます。
相対的明示事項については、口頭での明示も認められています。しかし、口頭での明示は勘違い等によるトラブルの原因になるおそれがあるため、なるべく書面に記載して明示することが望ましいでしょう。
FAX・メール・SNS等による明示
2019年4月の労働基準法施行規則の改定により、FAXや電子メールによる労働条件の明示が可能になりました。
もっとも、どのような場合でもこういった提示方法が可能なわけではありません。以下の要件を具備する必要があることに注意が必要です。
- ①労働者からの希望があること(同規則5条4項ただし書き)
- ②特定の受信者宛ての電気通信であること(同規則5条4項2号)
→特定の受信者宛てであることが必要ですので、ホームページでの公開や、ブログでの公開では意味がないことに注意が必要です。 - ③出力して書面を作成できること(同規則5条4項2号括弧書)
- ④到達を確認すること
これらの要件を満たさなければ、書面による明示と同等とみなされません。そのため、労働者から希望があったことを証明するために、記録を残してトラブルを防止しましょう。
例えば、労働者からの希望を電子メールによって受理する等の方法が考えられます。
労働条件の明示義務違反があった場合
労働条件明示義務に違反すると、労働基準法120条により30万円以下の罰金を使用者に科す旨が規定されています。また、パートタイマー等については、パートタイム労働法31条により10万円以下の過料を使用者に科す旨が規定されています。
労働条件を明示しなかったことについて、労働者が労働基準監督署に通報すると、行政指導などを受けるおそれがあります。
さらに、労働条件明示義務違反についての情報がSNS等によって拡散されてしまうと、ブラック企業だと認識されて企業イメージが低下するおそれがあります。そうなれば、消費者に避けられることによって売り上げが減少してしまうおそれがあり、求職者からの応募も減少するなど採用活動への悪影響も懸念されます。
即時解除権・帰郷旅費請求権の発生
使用者が、労働条件の明示義務違反をしている場合、労働者に契約解除権が発生します(労働基準法15条2項)。
本来、労働契約を解約するときには、解約の申入れから2週間の期限の経過が必要とされています(民法627条1項)。しかし、使用者の労働条件明示義務違反については「即時に労働契約を解除することができる」旨を規定しています(労働基準法15条2項)。
さらに、当該労働者が就業のため引っ越してきた場合、契約解除から14日以内に帰郷するのであれば、使用者はその旅費を負担しなければなりません(労働基準法15条3項)。
【2024年4月】労働条件明示ルールの改正
2024年4月に労働基準法施行規則が改正されて、以下の4つの事項についても明示義務の対象となります。
【全ての労働者に対する明示事項】
●就業場所・業務の変更の範囲の明示(労働基準法施行規則5条の改正)
雇い入れ後の就業場所や業務だけでなく、将来の配置転換などによって変わり得る就業場所や業務についても明示します。
【有期雇用労働者に対する明示事項等】
●更新上限の明示(労働基準法施行規則5条の改正)
更新する期間や回数の上限について明示します。
●無期転換申込機会の明示(労働基準法施行規則5条の改正)
無期転換の申込みができる機会ごとに、申し込めることを明示します。
●無期転換後の労働条件の明示(労働基準法施行規則5条の改正)
無期転換の申込みができる機会ごとに、申し込んだ後の労働条件を明示します。
企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ
企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※
企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)
会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません
受付時間:平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00
平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00
※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)
この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)
執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。
近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある