労働基準法の育児時間とは|基本的な考え方や労務管理上の注意点

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員
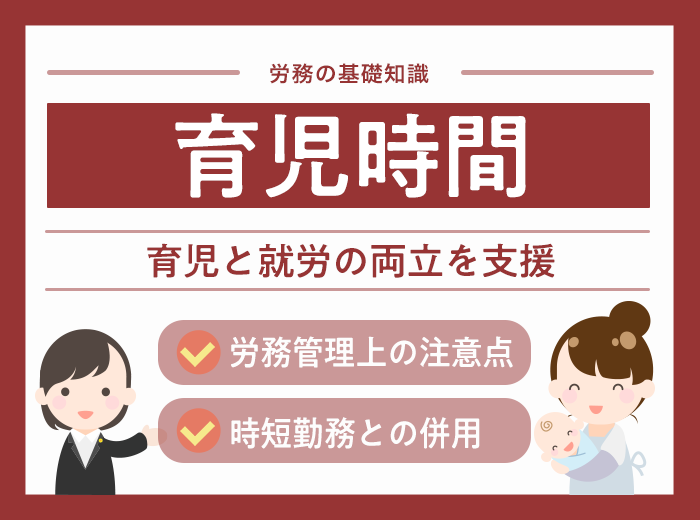
労働基準法67条には、「育児時間」という制度が規定されています。これは、特に育児の負担が大きい時期の女性労働者を対象とした、育児と就労の両立を支援する制度です。
本記事では、育児時間という制度の概要や、実際に労働者から付与するよう請求された場合の労務管理上の注意点等について解説します。
なお、育児・介護休業法で定められている「育児休業」は育児時間とは異なる制度です。下記の記事を併せてご確認ください。
目次
育児時間とは
育児時間とは、文字どおり育児を行うための時間であり、労働基準法で定められた権利です。満1歳未満の子供を育てる女性労働者から請求された使用者は、通常の休憩時間とは別に、原則として1日2回各30分以上、労働時間が4時間以内の場合は1日1回30分の育児時間を付与しなければなりません。
また、育児の対象となる子供は必ずしも実子である必要はなく、養子もその対象に含まれます。
育児時間の制度は公務員にも設けられており、その子が小学校就学の始期に達するまで、勤務時間の始め又は終りに、1日を通じて2時間以内について勤務しないことができます。
育児時間の請求は拒否できない
使用者は、対象の労働者から育児時間を請求された場合には、必ず付与しなければならないとされています(労基法67条)。これに違反し、請求を拒否した場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられるおそれがあります(労基法119条1号)。
もっとも、育児時間は、対象者となる労働者から請求されてはじめて、使用者側に付与する義務が生じるものです。そのため、対象となる労働者が特段に請求しない場合には、育児時間を与えなかったとしても、刑罰に処せられることはありません。
育児時間の対象者
育児時間の制度は、雇用形態にかかわらず、満1歳未満の子供を育てる女性労働者であれば利用できます。育児休業制度等とは異なり、なぜ男性労働者が対象とならないのかというと、育児時間の本来の制度趣旨は、授乳の機会確保や母体保護だったからです。
もっとも、「育児を行うための時間」には、授乳だけでなく、保育所への送り迎え等、その他様々な世話のための時間が含まれると解釈できます。そのため、男性も育児時間の制度の対象に含めるべきであるとする主張もなされることがあります。
労働基準法が定める内容はあくまでも最低基準であるため、1歳以上の子供のために育児時間の取得を認めることや、男性の育児時間の取得を認めることもできます。
そのためには、労使間の協議を踏まえて、就業規則に規定を設けて周知しましょう。
育児時間の回数
育児時間は、原則として1日2回、各30分以上と定められています。しかし、必ずしも2回に分けて取得させなければならないわけではなく、1回にまとめて1時間取得させる等、柔軟な運用が可能です。
パートタイム労働者の場合
使用者は、「満1歳未満の子供を養育する女性労働者」という条件を満たした労働者から請求があれば、雇用形態を問わず、育児時間を付与しなければなりません(労基法67条)。
もっとも、当該規定は、フルタイム労働者(1日の労働時間が8時間の労働者)を予定して、育児時間の回数や長さについて定めています。そのため、アルバイトやパートタイマー等で、1日の労働時間が4時間以下の場合には、1日1回30分の育児時間を付与すれば足りると解されます。
変形労働時間制の場合
変形労働時間制とは、繁忙期や閑散期などに対応して、労働時間を調整しやすくする制度のことです。1週間単位や1ヶ月単位、1年単位の変形労働時間制があります。
変形労働時間制の適用を受ける労働者であっても、当該労働者が満1歳未満の子供を育てる女性であり、育児時間を請求してきた場合には、使用者は育児時間を付与しなければなりません。
なお、変形労働時間制の適用を受ける女性労働者が、妊産婦にかかる労働時間制限(労基法66条1項)を請求せず就業を続けており、「1日の所定労働時間が8時間以上」である場合には、具体的状況に応じて法定以上の育児時間を取得させることが望ましいと考えられています(昭和63年1月1日基発第1号、婦発第1号)。
変形労働時間制について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
育児時間の付与時間帯
育児時間を取得する時間帯は、原則として請求者の自由です。そのため、例えば、使用者が一方的に「育児時間」として指定した時間帯以外での育児時間の取得を拒否することは違法となります。
実際の育児時間の取得方法としては、次のような形が一般的なようです。
- 始業と終業に30分ずつ利用し、「30分の遅出・30分の早帰り」を可能にする
- 始業または終業にまとめて1時間利用し、「1時間の遅出」または「1時間の早帰り」を可能にする
- (育児時間の事後申請が可能な場合)朝の授乳や登園等で遅刻してしまった時間や、子供の急病等で仕事を抜け出さなければならなくなった時間に充てる
育児時間の使い方
育児時間は、元は授乳を目的として定められた規定ですが、使い方はそれだけに限定されていません。そのため、使用者が育児時間の使い方を制限することはできません。
対象となる労働者は、育児時間に次のようなことができます。
- 授乳
- 子供の病気や怪我のための通院
- 保育所への送り迎え
- 子育てに必要な物の購入
育児のため往復時間
子供を保育園などに送迎するための移動時間は育児時間に含まれます。そのため、送迎にかかる時間も含めて30分以上の育児時間を与えていれば違法にはなりません。
しかし、保育園などが会社から離れた場所にある場合等には、移動時間がかかってしまうため他のことに使う時間が足りなくなってしまうおそれがあります。必要に応じて時間を延長する等、柔軟に対応することが望ましいでしょう。
育児時間に関する労務管理上の注意点
育児時間を請求されたときに、使用者はどのような点に気をつけて付与するべきなのかについて、次項より解説します。
育児時間中の給与
育児時間中の給与は、基本的に無給として扱われます。なぜなら、育児時間を有給とする規定が労働基準法等にないため、ノーワーク・ノーペイの原則が適用されるからです。
ただし、会社が育児時間を独自に有給とすることは可能です。育児時間を有給扱いにしたい場合には、あらかじめ就業規則等に定めて周知する必要があります。
育児時間の申請方法
育児時間の申請方法について、法律による規定はありません。そのため、口頭での申請を認めることもできますが、事前に申請する場合には申請書を用いるようにしましょう。
事後申請については認める義務はないものの、子供の体調不良を予測するのは難しいため、使い方の幅を広げるためにも認めるのが望ましいと考えられます。
具体的な申請手続きは、就業規則に記載しておきましょう。
就業規則の規定
育児時間は労働基準法によって定められていますが、労働者とトラブルになることを防ぐために、会社のルールを明記しておきましょう。
- 給与の有無
- 申請方法
- 1日の勤務時間が4時間以下の女性は1回30分である旨
- 1歳以上の子供の場合の取得
- 男性の取得
- 事後申請の可否
育児短時間勤務との違いと併用について
育児短時間勤務とは、3歳に満たない子を養育しており育児休業中ではない労働者が申し出た場合に、労働時間を基本的に6時間へ短縮する制度です。
育児時間と育児時短勤務とでは、対象となる年齢や男性が利用できるか等に違いがありますので表をご確認ください。
| 育児時間 | 育児時短勤務 | |
|---|---|---|
| 対象となる子供の年齢 | 1歳未満 | 3歳未満 |
| 対象者 | 女性(原則) | 男性・女性 |
| 労働者の労働時間 | 休憩を増やす | 労働時間を減らす |
育児時短勤務をしている労働者であっても育児時間を取得することが可能です。なぜなら、2つの制度は、趣旨や目的が異なると解されているからです。
育児時短勤務について、利用条件などを詳しく知りたい方は以下の記事を併せてご覧ください。
企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ
企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※
企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)
会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません。
受付時間:平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00
平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00
※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)
執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。
近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある



