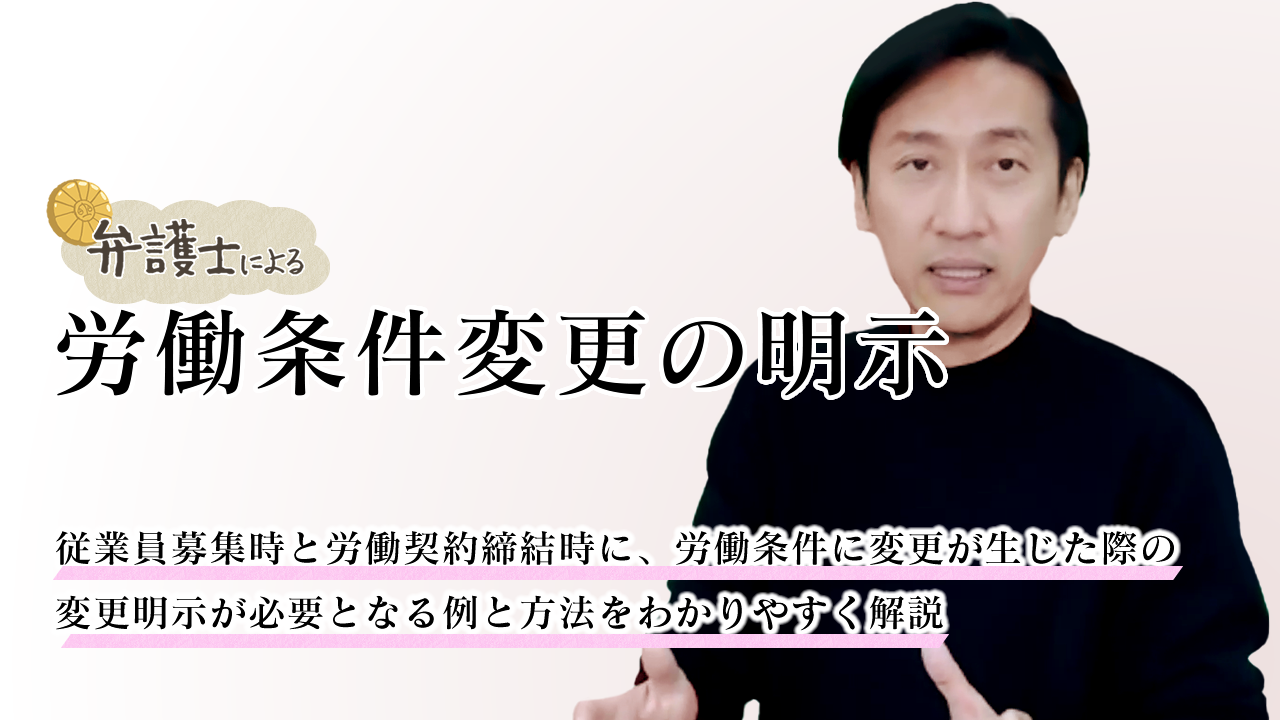労働者の採用|労働契約の成立要件や労働条件の明示義務

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員
新しく労働者を採用する場合は、労働者の業務への適性を見極めることだけでなく、労働契約の手続きについても注意しなければなりません。
採用時には、賃金や労働時間などの労働条件を書面の交付等により明示しなければならない等、法律で義務付けられているルールが多くあるため、遵守しながら、労働契約締結の手続きを進めていく必要があります。
本記事では、企業側の視点から、採用に関する法律上のルールだけでなく、労働契約はいつ成立するのか、労働契約の成立要件、採用した労働者の管理方法などについて解説していきますので、ぜひご一読下さい。
目次
採用時の労働契約と成立要件
労働契約とは、労働者が使用者の元で労働することの対価として賃金を受けとる契約であり、労働者と使用者の両者の「合意」によって成立するものです。
労働契約の成立は、必ずしも書面で交わす必要はないとされています(民法522条2項)。そのため、口頭で労働契約を成立させることも可能ですが、重要な労働条件については明示義務があり、書面を交付する等の方法で伝える義務が課せられています(労基法15条)。
それ以外の条件についても、採用した労働者との間に認識の相違があれば紛争に発展するリスクがありますので、労働契約は書面で交わすのが望ましいといえます。
労働契約について、より詳しい解説は以下のページをご覧ください。
労働条件の明示義務
使用者は、労働者と労働契約を締結する際に、正社員や契約社員、パート・アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、すべての労働者に対して、労働条件(絶対的明示事項と相対的明示事項)を明示しなければなりません。
- 絶対的明示事項:書面による明示が必要な労働条件 (メール・FAXでの明示可能)
- 相対的明示事項:定めがある場合に明示が必要な労働条件 (口頭での明示も可能)
なお、絶対的明示事項と相対的明示事項の具体的な一覧は、下表をご覧ください。
| 絶対的明示事項 | 相対的明示事項 |
|---|---|
|
|
労働条件の明示義務に関して、その他に以下のような注意事項があります。
- 使用者が労働条件の明示義務に違反した場合、労働契約自体は有効に成立するが、30万円以下の罰金が科されるおそれがある(労働基準法120条1号)
- 労働契約締結の際に明示された労働条件が、実際の労働実態と異なっている場合には、労働者は即時に労働契約を解除することが可能(同法15条2項)
- 入社のために引っ越しをした労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合は、使用者は必要な旅費を負担する必要がある(同法15条3項)
採用時の労働条件明示の義務について、さらに詳しい解説は、以下のページをご覧ください。
採用時に交付する書類
労働者を採用する際に、使用者が労働者に作成・交付するべき書類として、以下の2つが挙げられます。
- 労働条件通知書
- 労働契約書(雇用契約書)
2つの書類は同じ内容のように見えますが、発行義務や書類の持つ意味合いが異なるため注意が必要です。
以下で、詳細について見ていきましょう。
労働条件通知書
労働条件通知書とは、企業から労働者に対して、給与や契約期間、業務内容等の労働条件を通知する書面です。これは、企業が一方的に通知するものであり、労働者の署名・捺印は必要とされていません。
前述のとおり、労働条件の明示が法律上義務付けられているため、労働者を雇い入れる際は、必ず労働条件通知書を作成・交付しなければなりません。
なお、労働条件通知書は書面での交付が義務づけられていましたが、現在では、FAXや電子メール、SNS等でも通知が可能となっています。
労働条件通知書を発行するタイミングは、法律的には雇い入れ時(入社日)と決められていますが、労働者とのトラブル防止のため、「内定から入社までに」なるべく早めに通知するのが望ましいといえます。
雇用契約書 (労働契約書)
雇用契約書(労働契約書)とは、企業と労働者が労働条件について確認し合い、署名・捺印して取り交わす契約書です。内容に関しては労働条件通知書とほぼ同じで、賃金や契約期間等の労働条件が記載されています。
労働条件通知書は企業が労働者に向けて、一方的に交付するものですが、雇用契約書は双方が合意していることを証明するものという違いがあります。
雇用契約書は2枚作成し、労働者に署名・捺印してもらい、双方が1枚ずつ保管することになります。
法律上は、雇用契約書を交付する義務はなく、交付しなかったことによる罰則はありません。しかし、後で認識の違い等によりトラブルが発生するのを防ぐためにも、作成して交付するのが望ましいといえます。
雇用契約書を交付するタイミングについて、法的ルールはありませんが、一般的に「内定から入社まで」あるいは「入社日」に交付するケースが多いようです。
労働者の募集に関する定め
人材を募集する企業には、以下の法律によって、いくつかの法規制が適用されます。
- 男女雇用機会均等法(性別に関する差別の禁止)
- 雇用対策法(年齢に関する採用差別の禁止)
- 障害者雇用促進法(身体障害者や知的障害者の雇用義務)
- 労働組合法(労働組合員であることについての差別の禁止)
- 職業安定法
職業安定法により、現在定められている求人募集のルールは、以下のとおりです。
- 労働条件の明示が必要な時点
求人募集を行う際は、募集要項等に労働条件を明示する。 - 求人情報に最低限明示するべき労働条件
業務内容、契約期間、試用期間、就業場所・時間、休憩・休日、時間外労働、賃金、固定残業代、社会保険、裁量労働制、募集者の氏名と名称、派遣雇用、受動喫煙防止の取組など - 労働条件の明示における遵守事項
明示する労働条件は虚偽・誇大な内容としない、試用期間を設ける場合は、本採用後の労働条件ではなく、試用期間中の労働条件を明示するなど - 労働条件を変更する場合の明示方法
求人情報掲載中に労働条件が変更になった場合は、変更前と変更後の労働条件を明示する。
例)当初:基本給32万円 / 月 → 基本給30万円 / 月
求人票への記載事項
求人票の記載は事実でなければならず、虚偽の記載や誇張した記載はしないことが求められています。もしも、求人票に事実と反する記載をした結果、労働条件が事実と相違した場合、採用された労働者には労働契約を解除する権利が与えられるためご注意ください(労基法15条2項)。
求人票に記載すべき事項と記載してはならない事項は、下表のとおりです。
| 求人票に記載すべき事項 | 求人票に記載してはならない事項 |
|---|---|
|
|
なお、従業員を採用する際の注意点について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
採用選考に関する定め
採用選考の基本的な考え方については、厚生労働省の指針で定められています。
- 採用選考にあたっては
- 応募者の基本的人権を尊重すること
- 応募者の適性・能力に基づいて行うこと
- 公正な採用選考を行う基本は
- 応募者に広く門戸を開くこと
- 応募者の適性・能力に基づいて行うこと
以上の指針により、本人の責任によらない事情によって採用を拒否することや、求職者の能力とは直接的な関係のない事情によって採用することは望ましくないと考えられます。
なお、採用に関する事項は、就業規則に定めることは義務とされておらず、任意的記載事項とされています。しかし、後にトラブルが発生する事態を回避するために、記載しておいた方が良いといえるでしょう。
企業に認められる「採用の自由」
「採用の自由」とは、労働者を採用するときに、雇用契約を締結するか否かを選択する自由のことです。企業には、採用するかしないかの自由があります。
採用の自由については、契約締結前の段階であることから、企業が有する裁量の範囲も大きいと考えられます。しかしながら、憲法14条が人種や信条、性別、社会的身分で差別をしてはならないと定めており、法律においても、男女雇用機会均等法や労働施策総合推進法においては、性別、年齢における平等な機会の確保を義務づけられるなど、一定の制約が定められていますので、これらの事項を理由にして差別的な取扱いをすることはできません。
公正に採用選考するための基準
厚生労働省は、「公正な採用選考の基本」「採用選考自主点検資料」を公表し、以下のような応募者の適性・能力に関係のない事項を面接等で質問して把握することは、就職差別につながるおそれがあるため、配慮が必要としています。
- 本人に責任のない事項(本籍、出生地、家族に関すること、家庭環境等)
- 本来自由であるべき事項(思想・信条、宗教、支持政党、労働組合の活動歴等)
そのため、採用においては、これらに配慮した採用基準を設けるのが望ましいといえます。
例えば、介護離職のリスクを確認するために両親の年齢を質問したり、小さい子供がいる労働者を迷惑だと考えて子供の年齢を確認したりするのは、問題があると考えられています。
採用基準に関するさらに詳しい解説は、以下の記事をご覧ください。
採用選考における提出書類
採用のための提出書類は企業ごとに異なりますが、一般的には履歴書や職務経歴書、業務に必要な資格の取得に関する証明書等が挙げられます。
また、新卒であれば成績証明書や卒業見込証明書等も考えられます。
これらほとんどの提出書類は、個人情報にあたるものが多いため、あらかじめ取得目的を明示するほか、取得後の管理においても取扱いには注意が必要です。
また、採用に利用してはならない情報が記載されている書類や、退職を難しくするような書類等は提出させないようにしましょう。
| 提出を求めてよい書類 | 提出を求めてはいけない書類 |
|---|---|
|
|
採用内定から勤務開始までの労働契約
採用内定とは、「始期付解約権留保付き労働契約」とされており、労働者による労働契約の申し込み(求人への応募)に対して、企業側が労働契約を承諾した(内定を通知した)状態のことです。
始期付解約権留保付き労働契約とは、働き始める時期は決まっているが(=始期付)、入社までにやむを得ない事由が発生した場合は、会社が労働契約を解約する権利がある(=解約権留保付)労働契約であることを意味します。
採用を内定した際に、どの時点で労働契約が成立したのかは、具体的なやり取りを検討して判断する必要があるため、ケースバイケースです。しかし、一般的には、採用を内定した時点で、内定通知書を発送したり、内定承諾書を取得したりすることが多く、内定時に労働契約が成立したと判断されるケースが多いです。内定によって労働契約が成立する場合は、内定の時点で労働条件の明示が必要となります。
ただし、内定手続において労働契約が成立したとしても、すぐに働き始めるわけではないため、内定後から勤務開始までの期間は、「始期付解約留保権付き」という一定条件つきの労働契約が成立すると考えられています。
なお、採用から採用内定については、以下の記事で詳しく解説しています。
採用内定取り消しの適法性
合理的な理由がなければ、内定の取り消しは認められません。内定の取り消しは、「留保していた解約権の行使」であり、労働契約の解消である「解雇」に相当するからです。厳密には、採用後の解雇ほどの重大な解雇事由は求められませんが、簡単に内定取り消しができるわけではありません。
内定を有効に取り消すためには、「客観的かつ合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要とされます(労契法16条)。具体的には以下のようなケースが該当します。
- 経歴や学歴に重大な詐称があった場合
- 内定後に犯罪行為を行った場合
- 入社するまでに留年した場合
- 重い病気をわずらい働けなくなった場合
- 企業の業績が悪化した場合など
裁判等で内定取消が無効と判断された場合には、内定取り消しがなければ入社日以降に支払うはずだった賃金を支払う必要性が生じてしまいます。さらに、慰謝料や遅延損害金の支払いが必要となったり、悪質な場合は企業名が公表されたりするリスクがあります。
内定取り消しにおける会社側の注意点について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
試用期間中の労働契約
試用期間とは、採用した労働者を本採用する前に、自社の業務に適しているかどうかを確認するための期間です。試用期間中は「解約権留保付労働契約」が成立していると考えられ、会社側に特別な解約権が与えられている契約であるため、通常の労働契約よりは、解雇が認められやすくなっています。
ただし、試用期間中の解雇が認められるには、試用期間の目的に照らして、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められることが必要です。例えば、重大な経歴詐称が発覚したり、無断欠勤や遅刻・早退を繰り返したり、正当な理由なく長時間の離席を繰り返したりするような場合は、本採用を拒否できる可能性があります。
なお、試用期間を設ける場合は、試用期間中の労働条件を労働者に明示する必要があります。また、試用期間中の労働条件が本採用後の労働条件と異なる場合は、試用期間中と本採用後のそれぞれの労働条件を明示しなければなりません。
試用期間に関する詳しい解説は、以下のページをご覧ください。
試用期間中または試用期間満了後の本採用拒否
本採用拒否とは、試用期間中に留保した解約権の行使です。試用期間とはいえ労働契約は成立しているので、就業規則における解雇事由に該当しなければ本採用拒否はできません。
また、試用期間の途中に本採用拒否をすることも可能ですが、試用期間の満了の際に本採用を拒否する場合よりも要件が厳しいと考えられます。なぜなら、試用期間中であれば指導を行って改善する可能性があり、期間満了を待たずに本採用拒否をするためには、残りの期間の間に指導を行っても改善する可能性がないことが明らかでなければならないと考えられるからです。
なお、本採用拒否について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
採用後の労働契約の変更
労働契約は、会社と労働者の双方の合意があれば、変更できることが原則です(労働契約法8条)。
そのため、まずは変更の理由について労働者に丁寧に説明したうえで、合意書に署名・捺印をもらい、新しい雇用契約書、又は覚書を作成することになります。ただし、合意による変更の場合でも、就業規則に定める労働条件を下回ることはできないため注意が必要です。
また、労働者から合意が得られないような場合に、就業規則内で労働条件を変更するという方法もあります。しかし、使用者が一方的に就業規則を労働者の不利益に変更することは原則的に認められていません。
例外として、就業規則の労働条件を不利益に変更する場合には、①変更内容が合理的であること、②労働者に就業規則を周知させること、という2つの要件を満たすことが必要です。
内容の合理性については、労働者の受ける不利益の程度、会社側の変更の必要性、変更後の内容の相当性、代替措置などを考慮して判断されます。
企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ
企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※
企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)
会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません。
受付時間:平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00
平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00
※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)
執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。
近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある