福利厚生とは?種類やメリットなどの基礎知識を詳しく解説

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員
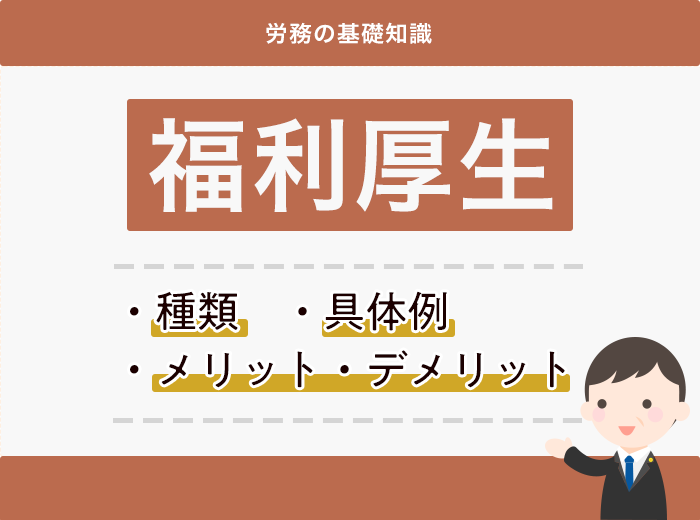
福利厚生が充実していると、従業員の満足度がアップするだけでなく、採用活動でも求職者にアピールできるため、積極的な導入をおすすめします。
ただし、導入しても、実際に従業員から利用されなければ無意味です。十分なコストパフォーマンスを得るためには、自社に合った福利厚生の選択と運用設計が必要です。
このページでは、福利厚生にはどのようなものがあるのか、その種類や具体例、導入のメリット・デメリットなどについて解説していきます。導入を検討されている企業担当者の方は、ぜひご一読ください。
目次
福利厚生とは
「福利厚生」とは、簡単にいうと、給与や賞与とは別に、会社が社員とその家族に提供する健康や生活へのサービスをいいます。
福利厚生は、法律で導入が義務付けられている「法定福利厚生」と、法律に関係なく会社が独自に導入する「法定外福利厚生」の2つに分けられます。
法定福利厚生の例として、健康保険や厚生年金、雇用保険、労災保険などが挙げられます。また、法定外福利厚生の代表例として、住宅手当や通勤費、健康診断、特別休暇などが当てはまります。
少子高齢化により働き手不足が進む現在、優秀な人材を確保するには福利厚生が有用です。
福利厚生を充実させれば、従業員の満足度が高まるとともに、優秀な人材を採用する際のアピールポイントとして活用できます。
福利厚生の対象者
福利厚生は、会社で働くすべての労働者やその家族が対象となります。
正社員だけでなく、契約社員(有期雇用労働者)、アルバイトやパートタイマー、派遣社員などの非正規社員も利用することが可能です。
2020年4月より「パートタイム・有期雇用労働法」が施行され、同一企業内における正社員と非正規社員の間で不合理な待遇差を設けることが禁止されるようになりました(同一労働同一賃金(パートタイム・有期雇用労働法第8条))。
不合理な待遇差が禁止される事項には、給与や賞与はもちろんのこと、福利厚生も含まれています。
よって、会社は労働者の福利厚生の待遇を見直し、正社員との不合理な待遇差を無くす必要があります。
福利厚生の種類・内容
それでは、福利厚生の種類や内容を確認していきましょう。法定福利厚生と法定外福利厚生に分けて解説します。
| 法定福利厚生 | 法律によって、企業に導入が義務づけられている福利厚生 |
|---|---|
| 法定外福利厚生 | 法律による規定はなく、企業が任意で導入する福利厚生 |
法定福利厚生
「法定福利厚生」とは、法律により導入が義務づけられている福利厚生です。具体的には、社会保険料の拠出を意味し、会社が保険料の一部または全部を負担しなければなりません。
なお、会社が負担する費用を「法定福利費」といい、負担率については、健康保険法や労働保険料徴収法等の法律に定められています。法定福利厚生として、以下のようなものが挙げられます。
| 健康保険 | 業務外で病気やケガをした際に、治療費の一部を負担する公的医療保険。従業員だけでなく家族も加入可能。健康保険料は会社と従業員で半額ずつ負担。 |
|---|---|
| 介護保険 | 介護が必要と認定された場合に、介護サービスを受けられる社会保険。 40歳になると、加入義務が発生。介護保険料は会社と従業員で半額ずつ負担。 |
| 厚生年金保険 | 会社員等が加入する、国民年金に上乗せして支給される公的年金。 保険料は会社と従業員で半額ずつ負担。 |
| 雇用保険 | 失業や育児、介護等による休業で収入が減った際に保険給付が行われる社会保険。雇用保険料は会社と従業員で負担するが、会社が多めに支払う。 |
| 労災保険 | 業務中、又は通勤中にケガや病気をした際に保険給付が行われる社会保険。労災保険料は会社が全額負担。 |
| 子供・子育て拠出金 | 児童手当、子育て支援事業、仕事と子育ての両立支援事業などに充てられる税金。標準報酬月額等をベースに算出し、会社が全額負担。 |
なお、企業に法定福利厚生がない場合、法定福利厚生ごとに異なりますが、例えば社会保険に未加入の場合は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
法定外福利厚生
法定外福利厚生とは、法律で義務付けられておらず、会社が独自に導入できる福利厚生です。
法定外福利厚生の種類として、以下のようなものが挙げられます。
| 住宅・通勤関連 | 住宅費や通勤費の一部を会社が負担する福利厚生 ・住宅手当の支給、持ち家援助 ・社宅、社員寮の完備 ・通勤費(定期代、ガソリン代、駐車場代)の支給など |
|---|---|
| 健康・医療関連 | 従業員の体調管理や健康増進を図るための福利厚生 ・健康診断やストレスチェックの実施 ・人間ドックの費用補助 ・メンタルヘルス相談 ・医務室やマッサージルーム等の設置 ・スポーツジムの利用料負担など |
| 育児・介護関連 | 仕事と育児・介護等の両立をサポートする福利厚生 ・法定日数以上の育児休業・介護休業・看護休暇の付与 ・短時間勤務制 ・男性社員の育児休暇取得の促進 ・託児所の設置、ベビーシッター等の利用費の補助など |
| 慶弔・災害関連 | 慶事や身内の不幸などがあった際に、従業員と家族をサポートする福利厚生。 ・結婚祝金、出産祝金、子供の入学祝金 ・昇進祝い金、永年勤続表彰 ・弔慰金、傷病見舞金、災害見舞金、遺族年金など ・慶弔休暇 |
| 財産形成関連 | 退職後の安定した生活や住宅取得のために行う貯蓄をサポートする福利厚生 ・財形貯蓄制度、確定拠出年金、確定給付企業年金 ・社内預金制度、持ち株会の実施など |
| 休暇関連 | 従業員を心身ともにリフレッシュさせるための福利厚生 ・結婚休暇、出産休暇、夏季特別休暇、年末年始特別休暇 ・療養休職 ・アニバーサリー休暇、リフレッシュ休暇など |
| 自己啓発・能力開発関連 | 従業員のスキルアップをサポートする福利厚生 ・英会話レッスン、資格取得に必要な費用の補助 ・海外研修制度、自己啓発セミナー参加費の補助 ・他社との交流会開催、図書購入費用の補助など |
| 職場環境関連 | 快適な環境で働けるよう、職場環境を整備する福利厚生 ・社員食堂やカフェの設置、食事補助サービス、社内弁当やドリンク提供 ・個別ワークスペースの設置、テレワークの導入など |
| 文化・体育・レクリエーション関連 | 従業員の保養や、従業員同士の懇親を深めることを目的とした福利厚生 ・社員旅行、歓送迎会、忘年会等の実施 ・運動会などのイベント開催、運動系・文化系のクラブ設置 ・保養所の完備、ホテルやレジャー施設の割引など |
福利厚生を導入する4つのメリット
福利厚生を導入するメリットとして、以下が挙げられます。
- 企業の社会的評価・採用力の向上
- 労働者の満足度・定着率の向上
- 労働者の健康増進
- 節税対策
企業の社会的評価・採用力の向上
入社してほしい人材が魅力を感じる制度を導入することで、優秀な人材が集まることが期待できます。
労働者を大切にしている良い会社とのイメージを与えられるため、人材不足が問題化している中小企業こそ福利厚生の充実化に注力すべきでしょう。
労働者の満足度・定着率の向上
福利厚生が充実していると、ワーク・ライフ・バランスが整うため、従業員の満足度が高まります。
その結果、仕事へのモチベーションがアップし、今の会社でより長く働きたいという意識が芽生えます。結果として、定着率の向上が見込めるでしょう。
また、気分良く、居心地の良いオフィスで働くことができれば、より仕事に集中できるようになるため、業務の効率化、業績アップなど、企業にもプラスの効果をもたらすことが期待されます。
従業員の満足度の向上が期待される福利厚生として、短時間勤務やフレックスタイム、テレワーク、ノー残業デーの導入、保育補助、介護支援などが挙げられます。
労働者の健康増進
福利厚生を充実させると、従業員の心身の健康増進を図ることが可能です。
健康増進に有効な福利厚生として、健康診断の実施、法定外の休暇の付与やメンタルヘルス相談、レクリエーション、スポーツジムの割引サービスなどが挙げられます。法定外の休暇の例としては、リフレッシュ休暇などが挙げられ、これらを取り入れることで、従業員の英気を養うという方法もあります。
従業員の健康状態が良好になると、個々の能力を十分に発揮できるようになるため、生産性の向上や休職・退職による人材不足を防止することができます。
節税対策
福利厚生費(福利厚生の充実にかけた費用)は、一定の要件を満たせば、損金として計上することができ、課税所得を減らすことができます。つまり、福利厚生費を支給することにより、会社に法人税の節税効果がもたらされることになります。
なお、健康保険や厚生年金などの「法定福利厚生」であれば、基本的に福利厚生費として認められます。
一方、会社が独自に導入する「法定外福利厚生」については、次項に挙げる要件を満たさなければ、福利厚生費として認められないため注意が必要です。場合によっては、従業員の給与又は役員の報酬にあたるとして、課税されるおそれもあります。
福利厚生費と認められるための要件
福利厚生費は損金として計上でき、節税対策として有効です。
ただし、企業が従業員のために支出する費用のうち、以下の主な要件をすべて満たすものが、福利厚生費と認められます。なお、各福利厚生によって、要件が異なることもありますので、ご注意ください。
●現金支給ではない
現金や金券など換金性の高いものを支給した場合、福利厚生費として認められない可能性が高くなります。この場合、給与として扱われ、所得税の課税対象となります。
●すべての労働者が平等に利用できる
福利厚生費として計上するには、すべての従業員が利用できるものである必要があります。
一部の従業員しか利用できないサービスの提供は福利厚生費とは認められません。
●金額・内容が常識の範囲内
高額すぎるものを支給した場合は、福利厚生費として認められません。
過剰な通勤費の支給、過剰な家賃補助、頻繁に開催する懇親会費等については、福利厚生費ではなく、給与や交際費として扱われるおそれがあります。
企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ
企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※
企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)
会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません。
受付時間:平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00
平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00
※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
福利厚生を導入する3つのデメリット
福利厚生を導入するデメリットとして、以下の3つが挙げられます。
- コストがかかる
- 管理に手間がかかる
- 全員のニーズに応えるのが難しい
コストがかかる
福利厚生の充実には、当然ながらコストがかかります。日本経済団体連合会の調査によると、2019年度に企業が負担した福利厚生費は、従業員1人1ヶ月あたり10万8517円となっており、決して安いものではありません。そのため、資金に余裕のない企業で福利厚生を充実させることは、困難であると考えられます。
また、少子高齢化社会ということもあり、法定福利厚生の社会保険料は増加傾向にあります。そのため、法定外福利厚生にかける費用を相対的に減らさざるを得ないという現状もあります。
管理に手間がかかる
福利厚生の導入にあたっては、申請書類の作成や施設の整備などのための手間や時間がかかります。
また、福利厚生導入後も、労働者からの利用受付や利用状況の把握、制度活用の促進といった管理が必要になります。
全員のニーズに応えるのが難しい
従業員のライフスタイルや嗜好はさまざまですので、全員のニーズを満たす福利厚生の提供は困難です。
また、従業員数が多くなればなるほど、利用者層に偏りが出やすくなります。その結果、利用したい福利厚生制度がないとして、不満を抱く従業員が出るおそれもあります。
これらの問題を解消するため、外部業者が提供する「カフェテリアプラン」を活用する会社が増えています。
毎年、従業員に一定額のポイントを与え、各自がポイントの範囲内で用意された福利厚生メニューの中から好きなものを選択するサービスです。自分に合ったメニューを選べるため、従業員の満足度を高め、福利厚生の無駄を削減できるという効果が期待されます。
福利厚生制度の導入方法
実際に福利厚生を導入する場合は、まず、従業員や会社にどのような利益をもたらしたいのか、導入目的を明らかにすることが重要です。また、制度を導入したとしても、従業員が実際に利用しなければ、十分な費用対効果を得られません。従業員に対しヒアリングやアンケートを行い、どのような福利厚生サービスを望んでいるのか、意見を収集する必要もあるでしょう。
導入目的や従業員のニーズ、予算などにもとづき、運用方法や利用対象者、利用条件、利用方法などを具体的に定めて、運用設計を行います。
また、導入したい福利厚生サービスを、自社で直接提供するのか、外部サービス(アウトソーシング)を利用するのか、いずれにするか決める必要もあります。
福利厚生の導入が決まったら、福利厚生規定(就業規則)を作成し、従業員に周知することが必要です。
福利厚生の導入方法については、以下のページで詳しく解説していますので、ぜひ併せてご覧ください。
企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ
企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※
企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)
会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません。
受付時間:平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00
平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00
※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)
執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。
近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある



