企業がとるべきマタハラへの対応・防止措置

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員
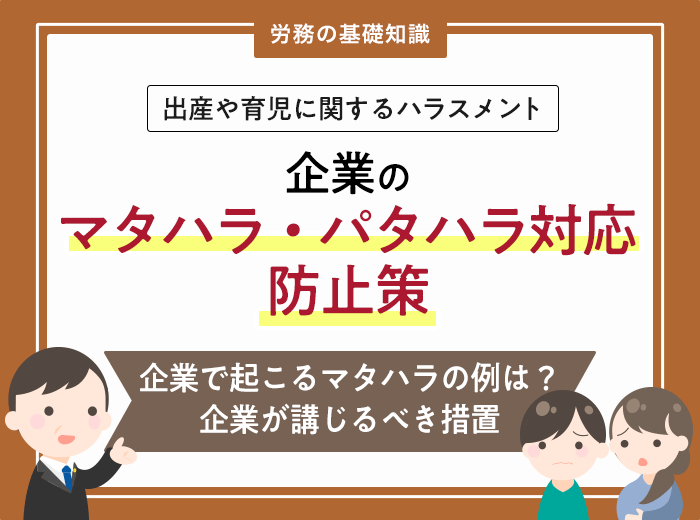
2017年より、すべての企業に対し、妊娠や出産、育児に関するマタニティハラスメント(マタハラ)防止措置を講じることが義務付けられました。
職場内におけるマタハラは労務管理上の問題であって、企業の責任が広く認められる傾向にあるため、適切なマタハラ対策を実施する必要があります。
本記事では、企業内で起こり得るマタハラについて例を挙げて説明するとともに、企業がマタハラ防止措置として具体的に何を行えば良いのか、さらに、必要な労務管理などについて解説していきます。
目次
マタハラ(マタニティハラスメント)の定義
マタニティハラスメント(マタハラ)とは、女性労働者が妊娠・出産したことや、産前産後休業・育児休業等の利用を希望した、又は取得したことを理由に、職場の上司や同僚から、不当な取り扱いや嫌がらせを受けることをいいます。
「職場」とは、労働者が業務を遂行する場所(実質的に職務の延長であるものは、飲み会等であっても職場とされます)であり、「労働者」には正社員だけでなく、契約社員やパート・アルバイト等も含まれます。また、業務上の扱いだけでなく、日常会話での発言が意図せずマタハラになることもあるため注意が必要です。
法律はマタハラを禁止するとともに、事業主に対して、マタハラが起きないよう適切な措置を講じることを義務づけています。
なお、パタニティハラスメント(パタハラ)とは、男性労働者が育児休業等の利用を希望、又は取得したことを理由に、嫌がらせ等を受けることです。パタハラも法律で禁止されており、事業主に防止措置義務が課せられています。
不利益取扱いの禁止
事業主は、妊娠・出産したことや、産前産後休業・育児休業等を希望した、又は取得したことを理由に、女性労働者に対して不利益な取扱い(マタハラ)を行うことを禁止されています(男女雇用機会均等法9条、育児・介護休業法10条等)。
不利益な取り扱いとは、以下のような行為を行うことをいいます。
- 解雇・雇止め
- 降格・減給・賞与における不利益な算定
- 契約更新回数の引き下げ
- 正社員を非正規社員とする契約内容の変更の強要
- 不利益な自宅待機の強要
- 不利益な人事考課・配置変更など
ただし、業務上の必要性や安全配慮にもとづく言動である場合は、マタハラに該当しないと判断される場合があります。
不利益取扱いの詳細については、以下の記事をご覧ください。
マタハラが生じた場合の事業主や加害者の責任
職場内でマタハラが発生した場合、事業主と加害者は、以下のような責任を負う可能性があります。
事業主の責任
事業主が妊娠・出産・育児等を理由に不利益な取り扱いをした場合
例えば、妊娠を理由に解雇した場合は、不当解雇として無効となります。
この場合、当該従業員より地位確認請求や解雇期間中の未払い給与請求、慰謝料などの損害賠償請求などを受ける可能性があります。
事業主である個人がマタハラを行った場合
被害者に対して、不法行為責任(民法709条)を負う可能性があります。
従業員のマタハラを止めさせず放置した場合
事業主は、使用者責任(同715条)、安全配慮義務違反として債務不履行責任(同415条)、不法行為責任(同709条)を負う可能性があります。
加害者の責任
マタハラを行った上司や同僚は、被害者に対し、不法行為責任(同709条)を負う可能性があります。また、会社から懲戒処分を受けることもあります。
マタハラの2つの類型と具体例
マタハラの類型には、以下の2種類があります。
- ①産休・育休制度を利用することへの嫌がらせ型
- ②妊娠・出産したことへの嫌がらせ型
なお、パタハラは①のみとなります。
次項より、それぞれ解説していきます。
産休・育休制度を利用することへの嫌がらせ型
「産休・育休制度を利用することへの嫌がらせ型」とは、雇用機会均等法や育児・介護休業法が対象とする制度・措置の利用を妨害したり、制度を利用した労働者に嫌がらせをしたりすることをいい、主に以下の3ケースに分けられます。
解雇その他不利益な取扱いの示唆
制度等の利用を請求、又は利用した労働者に対し、上司が直接的に解雇など不利益な取扱いをほのめかす場合
(例)育児休業上司に申し出たら、「休むなら辞めてもらう」と言われた。
制度等の利用の請求・利用の阻害
制度等の利用を請求、又は利用した労働者に対し、上司や同僚が請求・利用しないよう働きかける場合
(例)育児休業を請求したら、上司から「育児休業をとるなら、出世させない」と言われた。
制度等を利用したことを理由とした嫌がらせ
制度等を利用した労働者に対し、上司や同僚が嫌がらせをしたり、仕事を与えなかったりする場合
(例)同僚から「あなたの短時間勤務で周りが迷惑している」と言われた。
妊娠・出産したことへの嫌がらせ型
「妊娠・出産したことへの嫌がらせ型」とは、女性労働者が妊娠・出産したことに関する周囲の言動により、就業環境が害されるものをいい、以下の2ケースに分けられます。
解雇その他不利益な取扱いを示唆するケース
妊娠・出産をした女性労働者に対して、上司が解雇等をほのめかす場合
(例)上司に妊娠を報告したら「代わりの社員を雇うので、あなたは退職した方がいい」と言われた。
妊娠・出産をしたことを理由に嫌がらせ等をするケース
上司・同僚が妊娠等をした労働者に対し、嫌がらせをしたり、仕事を与えなかったりする場合
(例)上司が「妊婦はいつ休むかわからないから仕事を与えられない」と言い、雑務ばかりさせられた。
企業が講じるべきマタハラ防止措置
厚生労働省は、マタハラを防止するために事業主(企業)が講じるべき措置について、指針を公表しています(平成28年厚生労働省告示第312号、平成21年厚生労働省告示第509号、令和2年厚生労働省告示第6号)。
本指針は、企業が講じるべき措置として、以下の5つを挙げています。
- ①マタハラ等を防止するための方針の明確化および労働者への周知・啓発
- ②マタハラ等に関する相談窓口の設置などの体制の整備
- ③マタハラ等の相談がなされたときの迅速かつ適切な対応
- ④マタハラ等の原因・背景要因を解消するための措置を講じること
- ⑤被害者・加害者のプライバシーの保護等
ただし、派遣労働者の場合、④以外については派遣元と派遣先両方の事業主が措置を講じる必要があるため、注意が必要です。
それでは、以下で各措置の具体的な内容について、見ていきましょう。
①方針の明確化および労働者への周知・啓発
企業は、マタハラから労働者を保護するため、マタハラ禁止の方針を明確にしたうえで、以下の事項を、労働者に対して周知・啓発しなければなりません。
- マタハラに該当する言動
- マタハラの発生原因・背景
- マタハラ行為を禁止すること
- マタハラの加害者に対し、懲戒処分を行うなど厳正に対処すること
- 労働者は妊娠・出産・育児に関する制度等が利用できることなど
周知・啓発を行うには、就業規則等にマタハラの禁止規定を設けたうえで、社内報やパンフレット、会社のHP等に記載して配布する、労働者に研修を実施する等の方法が挙げられます。研修については、管理職層を中心に、階層別に実施することが望ましいでしょう。
なお、就業規則等に、懲戒処分の根拠となる規定を設けておかなければ、加害者への懲戒処分を行うことができず、加害者への処分や再発防止策が不十分になるおそれがあるため注意が必要です。
②相談窓口の設置などの体制の整備
企業は、マタハラ等に関する相談に適切に対応するための体制を整備する必要があります。具体的には、担当者を定めたうえで相談窓口を設置し、その旨を労働者に周知する方法があります。
なお、現にマタハラ等が生じている場合だけでなく、将来的に生じるおそれがある場合や、マタハラ等と認められるか微妙な場合に相談が持ち込まれることがあります。
また、職場におけるハラスメントは、複数のハラスメントが組み合わさって発生する場合もあります。そのため、相談窓口の担当者については、広く相談に応じるとともに、マタハラだけでなく様々なハラスメントについて一元的な対応ができるように研修を実施する等、内容や状況に応じた適切な対処ができるよう備えさせる必要があります。
③相談がなされたときの迅速かつ適切な対応
企業は、マタハラの被害者から相談を受けたとき、以下の措置などを講じる必要があります。
- マタハラが実際に行われたのかどうか、相談者や行為者からヒアリングを行い、事実関係を迅速かつ正確に確認すること。マタハラの事実の確認が十分にできない場合には、上司や同僚などの第三者からも事実関係を確認すること。
- 事実関係の確認の結果、マタハラの事実が認められた場合、被害者の意向に沿った適正な配慮措置を講じること(職場環境の改善、カウンセリング等)
- 加害者に対して適切な措置を行うこと(改善指導、懲戒処分等)
- 再発を防ぐため、改めて企業内にハラスメントに関する方針を周知・啓発すること
なお、マタハラが発生した際の対応や担当者が未定だと、スムーズに対応できず、事態が悪化するおそれがあります。よって、事後対応について、事前に準備しておくことが重要です。
また、事実関係の確認が難しい場合は、調停の申請や、中立な第三者機関に紛争処理を任せることを検討すべきでしょう。
④マタハラの原因・背景要因を解消するための措置
マタハラの発生原因の一つとして、妊娠等をした労働者の体調不良などにより、周りの労働者の負担が増えることが挙げられます。そのため、企業は、企業や労働者らの実情に応じて、以下の措置を講じることが必要です。
- 周囲の労働者への業務の偏りを軽減するため、業務配分の見直しを行うこと
- 日ごろから互いに業務を支え合える体制を整備すること
上記の対応を行えば、周りの労働者に不満が生じる状況を改善できます。
また、妊娠等をした労働者にも、周囲と円滑なコミュニケーションをとりながら業務を行ってもらいましょう。
なお、派遣労働者については、派遣元事業主のみが、当該措置を講じる義務を有します。
⑤被害者・加害者のプライバシーの保護
マタハラ等のハラスメントに関する相談内容や、被害者・加害者の情報はプライバシーとして保護されるべきものです。そのため、相談について対応する際や実際に事後的な対応に当たる際には、関係者のプライバシーを保護するための必要な措置を講じる必要があります。
また、相談の際にはプライバシーが守られることを企業内に広く知らせ、安心して相談できるような環境を整えましょう。
例として、プライバシー保護のためのマニュアルを作成し、マニュアルに基づいた対応をするようにしたり、相談窓口の担当者に提起的に必要な研修を行ったり、当該措置を講じていることを広報等の資料に記載して配布したりすることが挙げられます。
妊娠・出産・育児時の女性従業員に対する労務管理
妊娠・出産・育児時の女性労働者に対して、企業が行うべき労務管理を、タイミングごとに分けて解説します。
妊娠~産前産後休業前
妊娠から産前産後休業前にかけて、企業が行うべき労務管理として、主に以下が挙げられます。
- 医師の指導による勤務時間の変更等
妊娠中の労働者が医師等から指導を受けた場合は、勤務時間、作業の制限、休憩時間の延長等の措置を講じる必要があります(雇均法13条)。 - 休業制度等についての周知
妊娠・出産・育児に関する制度や給付金、社会保険料の免除の方法等について、面談等を行い周知します。 - 軽易業務への転換
妊娠中の労働者が、営業職から事務職など、負担の軽い業務への転換を希望した場合は、応じる必要があります(労基法65条3項)。 - 残業(時間外労働、休日労働、深夜労働)制限
妊産婦である労働者から残業の免除の希望があったときは、残業をさせてはいけません(労基法66条2項、3項)。 - 定期健診への協力
妊娠中の労働者が定期健診等を受診するために必要な場合は、出勤を免除するなどして時間を確保する必要があります(雇均法12条)。 - 妊娠を理由とする不利益取り扱いの禁止
妊娠を理由として、解雇、雇止め、降格、減給等の不利益処分を行うことはできません(雇均法9条3項)。
企業が講ずべき「母性健康管理措置」の詳細については、以下の記事をご覧下さい。
産前産後休業~育児休業中
産前産後休業から育児休業中にかけて、企業が行うべき労務管理として、主に以下が挙げられます。
- 産前休業の取得
出産予定日から6週間以内の女性労働者が産前休業を請求した場合は、就業させてはいけません(労基法65条1項)。 - 産後休業の取得
女性労働者の請求の有無にかかわらず、出産日の翌日から8週間は就業させてはいけません。ただし、産後6週間を経過した女性労働者が請求し、かつ、医師が支障なしと認めた業務に就業させることが可能です(労基法65条2項)。 - 解雇禁止期間
産前産後休業の期間及びその後30日間の解雇は禁止されています(労基法19条)。 - 育児休業の取得
基本的に、子が1歳に達するまでの間で労働者が申し出た期間については、育児休業を取得することが可能です。ただし、申し込みをしたものの保育園に入園できない場合等は最長2歳までの延長が可能となります。
産前産後休業の詳細については、以下の記事をご覧下さい。
復職後
労働者が職場に復職した後は、以下のような労務管理やサポートを行う必要があります。
- 育児時間の確保
生後満1歳に達しない子を養育する女性労働者が請求した場合は、1日に2回、少なくとも各30分の育児時間を与える必要があります(労基法67条)。 - 3歳未満の子を養育する労働者の両立支援
3歳未満の子を養育する男女労働者が請求した場合は、1日の所定労働時間を基本的に6時間とする短時間勤務制を設ける(育児・介護休業法23条)、また、所定労働時間外労働を制限する必要があります(同法16条の8)。 - 小学校就学前の子を養育する労働者の両立支援
小学校就学前の子を養育する男女労働者が請求した場合は、看護休暇(同法16条の2、3)を取得させ、時間外労働・深夜業の制限(同法17、19条)を行う必要があります。
マタハラに関する裁判例
最後に、マタハラの訴えが認められた判例と、認められなかった判例について、それぞれ解説します。
マタハラの訴えが認められた判例
【東京地方裁判所 平成30年7月5日判決】
(事件の概要)
X(原告)はY1(被告会社)の無期雇用の嘱託社員でしたが、Xが第1子の産休・育休を終え復帰した際、短時間勤務を希望したところ、Y2(Y1取締役)に、パート契約に転換しなければ、短時間勤務は認めないと説明されたため、パート契約を締結しました。
その後、Xは第2子を妊娠し、出産後復職したものの、契約期間の満了後、パート契約の更新を拒否されました。そのため、XはY1に対し、パート契約への変更の有効性、解雇・雇止めの有効性を争い、損害賠償請求した事案です。
(裁判所の判断)
短時間勤務を希望したことを理由に不利益取扱いをすることは禁止されているが(育介法23条の2)、使用者と労働者が合意すれば、労働条件を不利益に変更しても直ちに違法、無効とはならない。
ただし、当該合意が有効に成立したといえるには、労働者の自由な意思に基づき、当該合意がなされたと認められる合理的な理由が存在する必要がある。
本件では、パート契約への変更は、Xに大きな不利益を与えること、Xに対して会社の経営状況を詳しく説明したことはなかったこと、勤務時間を短くするためにはパート社員になるしかないと説明したのみで嘱託社員のまま時短勤務にできない理由についてそれ以上の説明をしなかったものの、実際には従前の雇用形態のままでも短時間勤務が可能であったこと、パート契約の締結により手当の不支給等の経済的不利益が生じることについて会社から十分な説明を受けたと認めるに足りる証拠はないこと、Xは他の従業員に遠慮しパート契約を結んだこと等を考慮すると、合理的な理由は存在せず、不利益取扱いにあたる。よって、パート契約は育介法23条の2に違反し、無効である。
また、本件の雇用契約の終了通知は、解雇の意思表示と認められるが、本件解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当とは認められないため、無効である。
マタハラの訴えが認められなかった判例
【広島高等裁判所 平成24年7月19日判決】
(事案の概要)
X(控訴人)はY(被控訴人)に雇用され、訪問リハビリ業務に従事していました。
Xは妊娠したため、軽易業務への転換を請求したところ、YはXに、病院のリハビリテーション科への異動を命じ、副主任の地位を免じました。
しかし、育児休業からの復帰後も、Xを副主任の地位に戻さなかったため、本件措置は均等法9条3項(妊娠・出産を理由とした不利益取扱いの禁止)、育児・介護休業法10条(育児休業を理由とした不利益取扱いの禁止)に違反し、無効であるとして、XがYに損害賠償請求した事案です。
(裁判所の判断)
本件措置は、妊娠と育児休業をきっかけに行われたものである。
しかしながら、YはXが比較的軽易な業務である病院内のリハビリ業務への転換を希望したことによって、リハビリテーション科へ異動させたのであり、副主任を免じたことについても、異動先にはすでに主任がいて、副主任を置く必要がなく、Xもこのことを同意していたと評価される。
また、Xは、副主任職については、特に行うべき職務、役割はなく、年功序列的に付与される役職であり、同一の部署に役職者が併存したとしても、とくに不都合はないと主張をするが、副主任職は、管理職務規程において、管理者の機能、任務、資質、資格、権限が定められた職位であり、行うべき職務や役割がないということはできない。そのため、その任免については、使用者の経営判断に基づきなされるものというべきである。
よって、本件措置は、均等法9条3項、育児・介護休業法10条に違反せず、人事権の濫用にもあたらない。そのため、Xの主張は採用することができない。
企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ
企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※
企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)
会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません
受付時間:平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00
平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00
※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)
この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)
執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。
近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある



