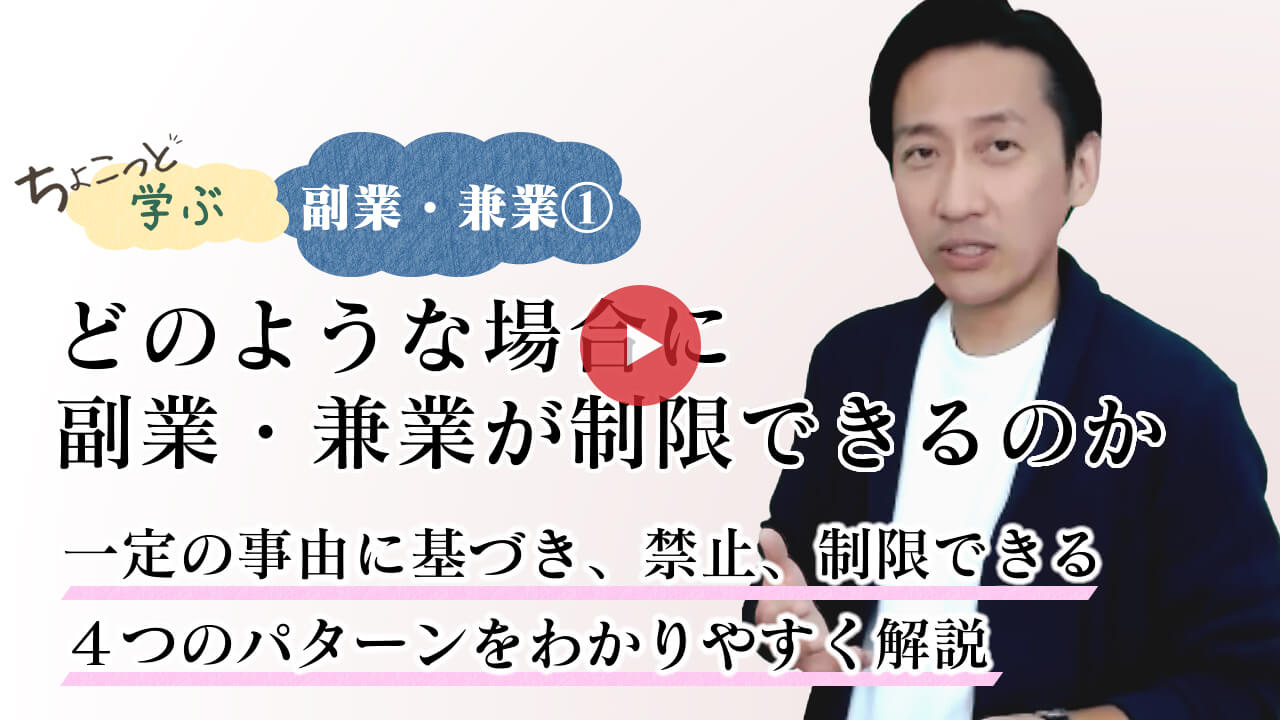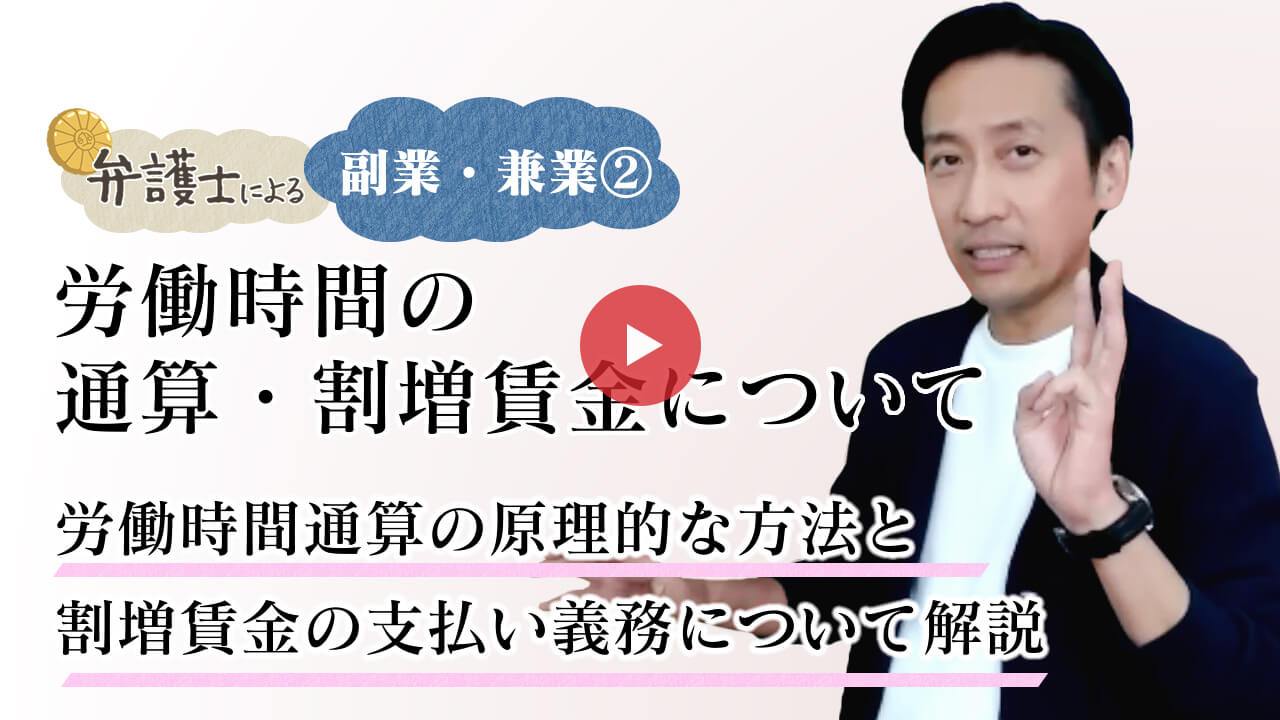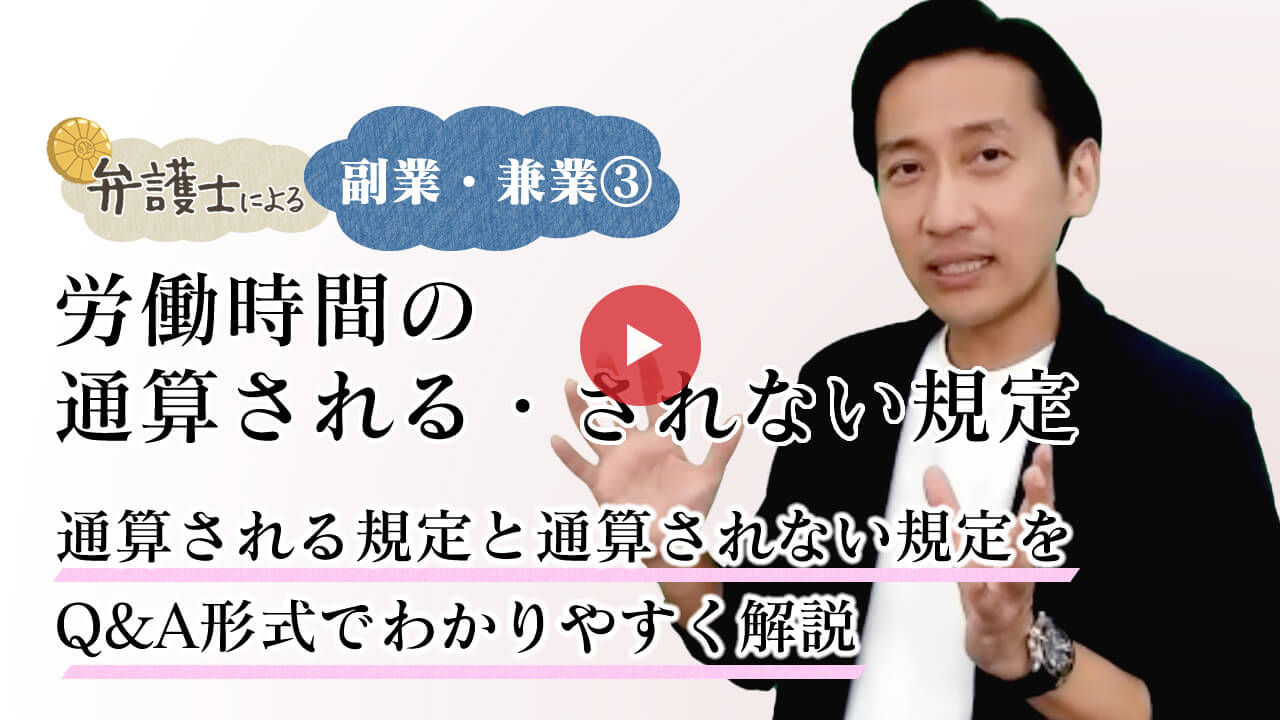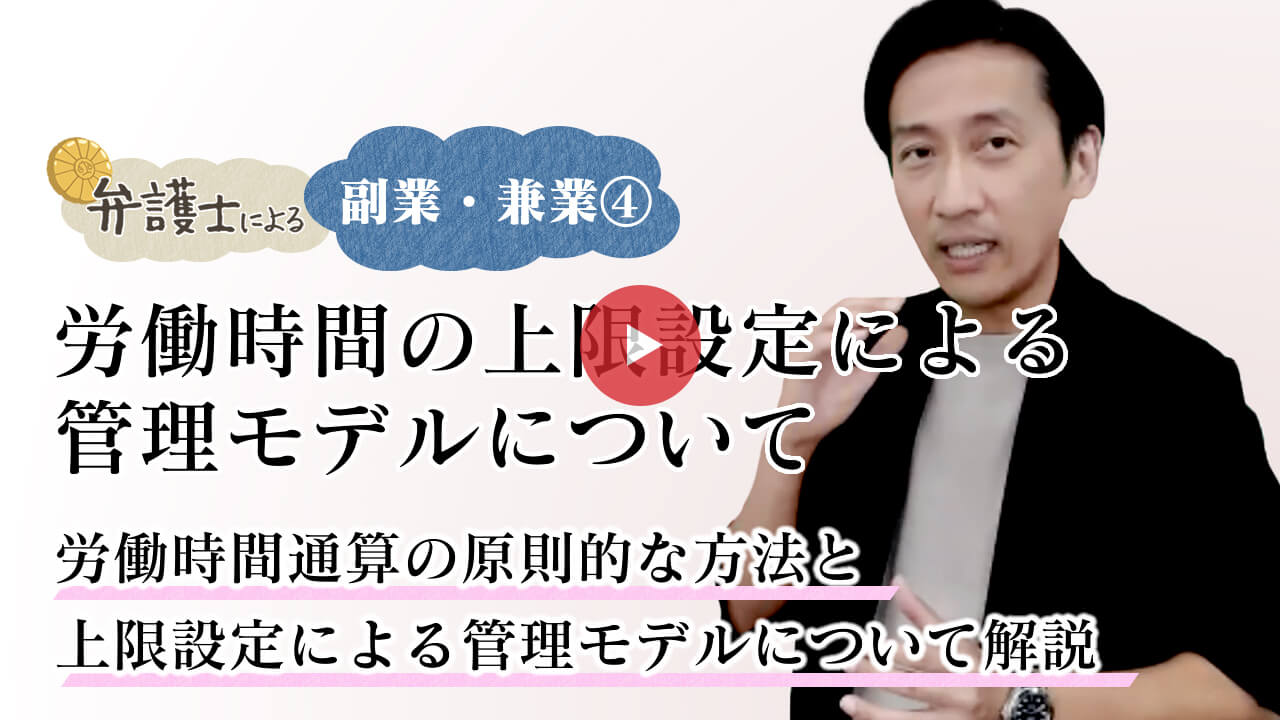副業と兼業の違い|企業側のメリットや注意点について
副業・兼業についてYouTubeで配信しています。
副業・兼業は原則自由であって、一定の事由に基づき制限できるという関係にあります。そのため、副業・兼業も原則として認めるべきということになりますが、その際、どのように労働時間を管理すれば良いのか、労働時間に関する規制について何が通算されて、何が通算されないのかといった問題も検討する必要があります。
動画では、副業・兼業がどのような場合に制限できるのか、労働時間の原則的な通算方法や何が通算されて通算されないか等、何回かに分けて解説しています。

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員
近年、労働者の副業・兼業を認める企業が増えています。この背景には、少子高齢化による人手不足の深刻化やニーズの多様化など、社会情勢の変化があります。
また、政府が副業・兼業を推進するようになったことも大きな要因です。
そこで本記事では、副業と兼業の違いや副業・兼業を解禁することのメリット・デメリット、解禁時の注意点等を詳しく解説していきます。副業・兼業を解禁するべきかお悩みの方はぜひご覧ください。
目次
副業・兼業とは
副業とは、本業と比べて収入・労働時間・仕事量などが少ない仕事をいいます。あくまでメインは本業であり、サブとして他の仕事を行っている状態を指します。
一方、兼業とは、本業と同等の労働時間・労力を必要とする仕事をいいます。つまり、2つ以上の仕事を掛け持ちしている状態を指します。
ただし、兼業や副業に明確な定義はありません。また、これらを禁止する法律もないため、「兼業を認めるかどうか」「どこまで副業を認めるか」については、企業の裁量で決める必要があります。
副業と兼業の違い
副業と兼業は、法律上は明確な定義がないものの、一般的にはその仕事量で区別されています。
副業については、あくまで「メインは本業」ですので、副業は“小遣い稼ぎ”くらいに考える人も多いでしょう。
一方、兼業については、複数の仕事を同程度の時間や労力をかけて行う点が特徴です。
| 副業 | 本業と比べて仕事量が圧倒的に少ない仕事 |
|---|---|
| 兼業 | 本業と同等の労働時間・労力を必要とする仕事 |
厚生労働省による副業・兼業の促進
厚生労働省は、2018年1月にモデル就業規則を改定し、副業・兼業ができる旨の規定を新設しました。
また、労働者の副業・兼業を促すために、経済産業省によって「副業・兼業支援補助金」が設けられています。
政府が省庁を挙げて副業・兼業を促進する背景として、労働者が経験を積み、スキルを得ることによる人材の流動化、及び国全体の生産性の向上を目指していることが挙げられます。
さらに、人手不足を補うとともに、労働者の所得を増やして経済を活性化することも目指していると考えられます。
副業・兼業の促進に関するガイドライン
厚生労働省は、副業・兼業の運用についてガイドラインを作成し、導入の流れや注意点を詳しく説明しています。
かつては、過重労働や情報漏洩等のリスクから、副業・兼業を禁止する会社がほとんどでした。
しかし、2019年4月に始まった働き方改革に伴い、政府が副業・兼業を推進する方針を明らかにしたため、モデル就業規則の改定とともにガイドラインが作成されました。
ガイドラインの内容は、以下のページでわかりやすく解説しています。ぜひご覧ください。
また、働き方改革の施策について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
副業・兼業を解禁するメリット
- 労働者のスキルアップ
他社で得た知識やノウハウは、本業にも活かされます。自社の技術不足を補ったり、作業効率を上げたりするための糸口となるでしょう。
また、労働者が自主的にスキルアップすれば、人材育成や教育にかかる費用も削減できます。 - 優秀な人材の確保
例えば、他社からオファーを受けた労働者が“転職”ではなく“兼業”を選ぶことで、優秀な人材の流出を回避できます。
また、アルバイトや業務委託など募集範囲を広げることで、人材不足の解消にもつながります。 - 事業の拡大
外部の技術や人脈を取り込めるのもメリットです。例えば、他社と協力して技術開発を行ったり、商品を共同開発したりできるようになります。 - 企業のイメージアップ
求人サイトやSNSで副業・兼業の導入を発信すれば、柔軟な働き方ができる企業だとアピールできます。自主的にスキルアップを目指す人材や、学生の注目が集まるでしょう。
副業・兼業を解禁するデメリット
- 情報漏洩のリスク
自社の技術や機密情報が外部に漏れれば、企業は多大なダメージを受けます。競争力の低下や、社会的信用の失墜は避けられないでしょう。 - 労務管理が難しい
労働時間や健康状態について、より厳格な管理が求められます。
例えば、兼業による過重労働で労災が発生した場合、どちらの会社に原因があるか争われる可能性があります。これを防ぐため、日頃から面談によって健康状態を把握したり、残業を抑制したりしておくことが重要です。 - 人材流出のリスク
人材を留めることができる一方、労働者の離職を促すおそれもあります。
例えば、労働者が「本業よりも兼業が向いている」、「兼業先の社風が合っている」と考えた場合、転職に踏み切るかもしれません。
副業・兼業の解禁における注意点
会社が労働者の副業・兼業を解禁するときには、注意しなければならない次のような点があります。
- ①労働時間・健康の管理
- ②秘密保持義務等の確保
- ③届出制度の制定
- ④就業規則への記載
注意点について、以下で解説します。
労働時間・健康の管理
副業・兼業を認める場合、労務管理の徹底や見直しが必要です。具体的には、主に次のような項目について検討しましょう。
- 労働時間の管理
- 健康状態の把握や衛生管理
- 社会保険への加入手続き
- 通勤手当の変更
例えば、時間外労働については、本業と副業・兼業の雇い主が違っていても労働基準法上の労働時間は通算されます。
そのため、それぞれの合計時間が法定労働時間(労働基準法の規定)を超えた場合、残業代(割増賃金)が発生します。
このとき、基本的に残業代の支払い義務を負うのは、後から労働契約を締結した事業主となります。
その他、休日労働の抑制や産業医との面談強化といった健康管理も必要でしょう。
それぞれの手順は、厚生労働省のガイドラインに掲載されています。
秘密保持義務等の確保
労働者は、使用者に対し、労務提供以外にもいくつか義務を負っています。しかし、副業・兼業では、これらの義務への意識が疎かになりがちであるため、使用者は注意が必要です。
具体的には、以下3つの義務について注意する必要があります。
- 秘密保持義務
自社の技術や機密情報、顧客情報などを外部に流出しないこと - 競業避止義務
自社に不利益となる競業行為(競合企業に就職すること、自ら同業のブランドを立ち上げること等)を禁止すること - 職務専念義務
就業時間中はメール・ネット閲覧等の私的行為を控え、仕事に専念すること
これらの義務については、あらかじめ就業規則で明示しておきましょう。また、副業・兼業を希望する労働者に誓約書を提出させることで、違反時に行う懲戒処分が有効と判断されやすくなることでしょう。
ただし、過度な責任を課した場合には、処分が無効となるおそれがあるため注意しましょう。
3つの義務の詳細や注意点は、以下のページでご確認ください。
届出制度の制定
副業・兼業を認めるときには、適切な労働時間管理を行ったり、情報漏洩等のトラブルを防ぐため、必ず会社に届け出る旨を規定しましょう。
届出を義務づけるべき副業・兼業先の情報として、次のようなものが挙げられます。
- 会社名
- 所在地
- 雇用形態
- 業務内容
- 勤務する曜日
- 労働時間
これらの情報の届出と同時に、本業に支障をきたさない旨を記載した誓約書を取り交わしましょう。
就業規則への記載
副業・兼業を認める場合、就業規則の変更も必要です。具体的には、次のような事項を記載して周知しなければなりません。
- 副業・兼業を認める条件
- 副業・兼業の申請手続きと届け出る内容(会社名等)
- 過労状態になる場合等には副業・兼業の中止を命じること
- 秘密保持義務・競業避止義務を守ること
- 企業の名誉や信用を損ねてはいけないこと
- 労働時間が通算されること
- 通勤手当の取り扱い
- 通勤災害・業務災害の取り扱い
副業・兼業を禁止することはできるのか?
一方的な副業・兼業の禁止は認められませんが、合理的な理由があれば別です。
企業の不利益につながる仕事は禁止すべきですし、違反行為をした場合には懲戒処分も検討する必要があります。
以下で具体的なケースをみていきましょう。
禁止が認められる副業・兼業
以下に該当する場合、副業・兼業の禁止が認められる可能性があります。
- 本業に支障が出る
- 機密情報が漏洩するおそれがある
- 企業の名誉や信用を失墜させる
- 労使間の信頼関係を破綻させる
- 競業によって企業利益を害する
これらは就業規則に明記し、労働者に周知しておく必要があります。
もっとも、就業規則は一般的な規定なので、違反行為にあたるかは事案ごとに判断されます。
過去の裁判例でも、年に数回だけ他社でアルバイトをしたケースや、休日や就業時間外に副業したケースで、本業への支障はないと判断されたものがあります。
一方、在職中に同業の会社を設立し、意図的に企業へ不利益をもたらしたケースでは、競業避止義務違反にあたると判断されています。
つまり、労働契約の付随義務に違反する場合、副業・兼業の禁止が認められると考えられます。
違反に対する懲戒処分
副業・兼業の規定に違反した労働者は、懲戒処分とすることが可能です。ただし、前提として、「就業規則違反=懲戒処分の対象」との旨を明示しておく必要があります。
また、懲戒処分は重大な手続きであり、就業規則違反にあたるかは個別に判断されるため、慎重に判断しなければなりません。
例えば、次のような事由がある場合、懲戒処分が認められる可能性があります。
- 兼業により遅刻・早退・欠勤が増えた
- 深夜にわたり長時間の副業を行った
- 企業固有の技術を漏洩した
- 企業の名前を使って副業を行った
- 違法な副業を行い、企業の品位を落とした
- 事前の申告が義務付けられているのに、無許可で副業を行った
懲戒処分の判断基準や注意点については、以下のページをご覧ください。
企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ
企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※
企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)
会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません。
受付時間:平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00
平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00
※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)
執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。
近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある