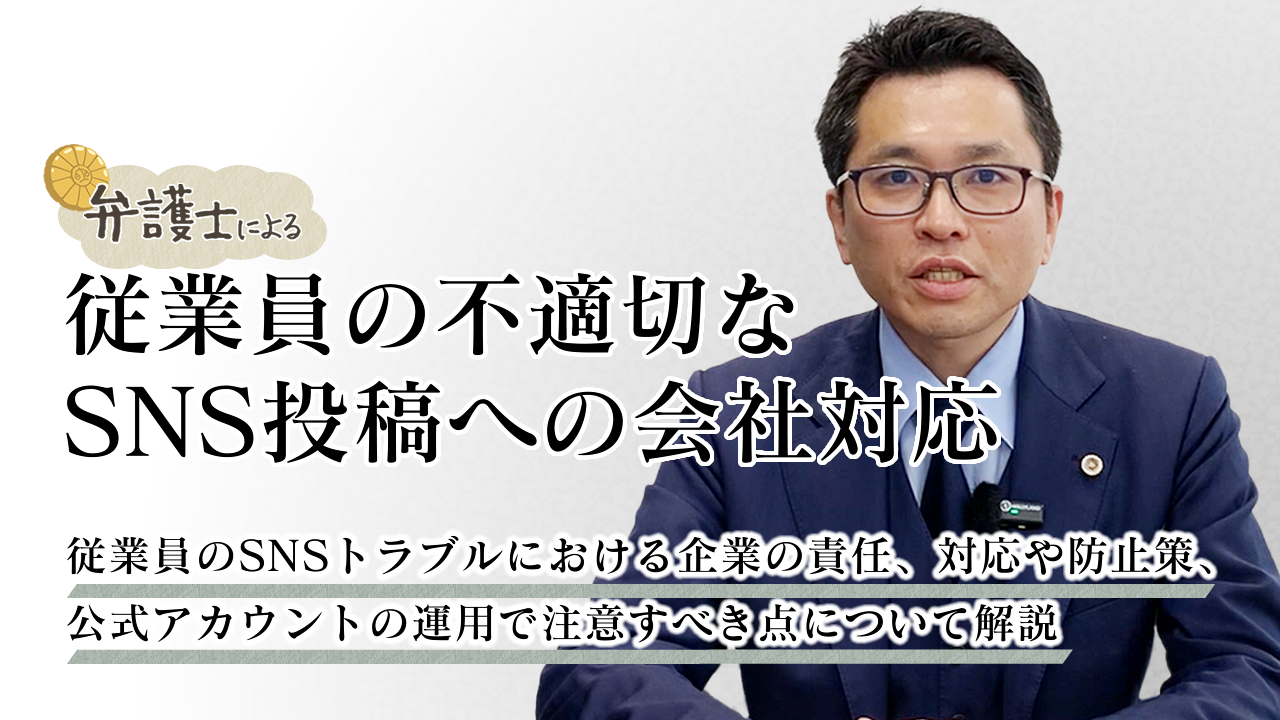監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員
近年、従業員が不適切な文章や画像をSNSに投稿することにより、会社が謝罪等の対応を迫られるケースが増えています。また、投稿内容によっては、会社の信用低下や利益減少につながるおそれもあるため、十分に注意を払うことが重要です。
そこで、本ページでは、従業員によるSNS利用に関して会社が日頃から行っておくべき措置や、従業員が不適切なSNS投稿をしてしまった場合の対応等をご紹介します。
目次
従業員の不適切なSNS投稿が企業に与えるダメージ
従業員がSNSで不適切投稿を行い、炎上する事案は後を絶ちません。一度ネットに投稿された情報は瞬く間に拡散され、取り消しはほぼ不可能となります。
不適切投稿の責任は従業員にありますが、企業へのダメージも避けられないのが現実です。
想定される企業リスクとしては、以下のようなものがあります。
- 企業イメージの悪化
- 売上減少や取引中止
- 株価の下落・暴落
- 損害賠償金の支払い
- 離職者の増加や新入社員の減少
企業に損害を与えるSNS投稿の具体例とは?
SNSへの不適切投稿で多いのは、以下のようなケースです。
- 悪ふざけ動画の投稿
食品を不衛生に扱ったり、備品で遊んだりする様子を撮影し、投稿すること - 公式アカウントでの誤投稿
従業員が、会社の公式アカウントと自身のプライベートアカウントを間違えて投稿してしまうこと - 機密情報の漏洩
未発表の商品や顧客リストなど、社外秘の情報をアップすること - 著名人のプライベート暴露
著名人がプライベートで来店している様子を撮影・投稿すること
特に企業秘密を流出されると、会社へのダメージも一層大きくなるため注意が必要です。詳しくは以下のページをご覧ください。
従業員が不適切なSNS投稿を行った際の対応
従業員の不適切投稿が発覚した場合、企業は速やかに対処し、炎上を防ぐことが重要です。
具体的には、以下の流れで対応を進めましょう。
- 投稿内容の保全と投稿者の特定
- 投稿内容の削除要請
- 公式サイト等での公表・謝罪
- 再発防止策の策定
投稿内容の保全と投稿者の特定
投稿された画像や動画は簡単に編集・削除できてしまうため、証拠保全の観点から、投稿内容を保全しておくことが重要です。スクリーンショットやキャプチャ、プリントアウト等の方法で保存しておきましょう。
併せて、投稿された店舗や投稿者についても特定します。
なお、企業アカウントで不適切投稿が行われた場合、すぐに投稿を削除することは避けましょう。慌てて削除すると証拠隠滅を疑われ、ますます批判を浴びるおそれがあります。
投稿内容の削除要請
投稿者が特定できたら、事実確認のためヒアリングや調査を行います。その後、できるだけ早く本人に投稿を削除するよう依頼しましょう。
不適切投稿のような炎上事例は拡散速度が特に速いため、被害を最小限に抑えるためにも、削除要請は早い段階で行うことが重要です。
従業員が削除要請に応じない場合、サイトの運営元やSNSプラットフォームに問い合わせて削除を依頼してみましょう。
公式サイト等での公表・謝罪
公式サイト等で公表・謝罪する場合、ユーザーからの批判や意見も踏まえて対応する必要があります。批判の原因や内容、世間がどんな説明を求めているのかしっかり把握し、的確な謝罪を行うように努めましょう。
例えば、問題点やその経緯について一切触れず、ただ謝るだけでは、「的外れだ」「本当に反省しているのか」「謝れば良いと思っている」等とさらなる批判を招くおそれがあります。
場当たり的な謝罪だと思われないよう、まずは世間の声を冷静に分析・把握することが重要です。
再発防止策の策定
不適切投稿が行われた原因を分析し、再発防止策を策定します。例えば、以下のような方法が挙げられます。
- SNSの利用方法やリスクに関する研修を行う
- SNS利用におけるガイドラインを作成する
- 不適切投稿を禁止する旨を就業規則に明記する
従業員の中には、ガイドラインや社内規程の内容を把握していない者もいると考えられます。そのため、入社時や定期研修等でしっかり説明するのが望ましいでしょう。
また、再発防止策の内容をホームページで公表することで、早期の信用回復につながる可能性もあります。
不適切なSNS投稿を行った従業員を解雇できるのか?
従業員の不適切投稿によって会社が損失を受けた場合、懲戒解雇の対象になり得ます。ただし、懲戒解雇が認められるのは以下2つの要件を満たすケースに限られます。
- ①就業規則上の懲戒事由に該当すること
従業員の不適切投稿が、就業規則上の「懲戒事由」に該当する必要があります。SNSへの投稿の場合、会社の名誉や信用の毀損、秘密保持義務違反、倫理規定違反などに該当するケースが多くみられます。 - ②解雇権の濫用にあたらないこと
解雇に「客観的合理性」と「社会的相当性」が認められない場合、当該解雇は無効になります。
よって、就業規則の懲戒事由にあたる場合であっても、実際に懲戒解雇できるかは投稿内容の重大性、会社が被った損害の大きさなどを踏まえて個別的に判断されます。
懲戒解雇の流れや注意点は、以下のページで詳しく解説しています。
従業員の不適切なSNS投稿に対する法的措置について
従業員の不適切投稿によって会社が大きな損失を受けた場合、法的措置を講じることも検討しなければなりません。考えられる法的措置としては、以下の2つです。
- 民事上の損害賠償請求
- 刑事告訴・告発
民事上の損害賠償請求
不適切投稿を行った従業員に対しては、不法行為に基づく損害賠償請求をできる可能性があります。
損害賠償請求の流れは、
- 従業員の処分を決定する
- 損害賠償請求を行う(内容証明郵便などで請求書を送付する)
- 支払いがなされない場合、裁判を検討する
となります。
ただし、会社から従業員に対する損害賠償請求や求償請求は制限される傾向があるため、ある程度減額されるのが一般的です。これは、会社と従業員との経済力の格差、使用者責任などを踏まえ、従業員にすべての責任を負わせるのは適切ではないと考えられるためです。
刑事告訴・告発
従業員のSNS投稿が刑事責任に問われる可能性がある場合には、刑事告訴や告発を視野に入れる必要があります。SNS投稿で成立しやすいのは、以下のような犯罪です。
- 名誉棄損罪(230条)
- 侮辱罪(231条)
- 信用棄損罪(233条)
- 業務妨害罪(234条)
例えば、「○○社は不良品ばかり売っている」「詐欺集団だ」などと嘘の情報を大量に書き込み、会社の社会的信用を傷つけた場合、名誉棄損罪が成立する可能性があります。
ただし、刑事告訴や告発を行うかどうかは、弁護士に相談のうえ慎重に検討することをおすすめします。
従業員のSNSトラブルを未然に防ぐには
従業員の不適切投稿を未然に防ぐには、平常時から以下のような対策を講じておくことが重要です。
- 就業規則・SNSガイドラインの策定
- 従業員に向けた教育・研修の実施
- 誓約書の提出を求める
- 社内体制の整備
SNSへの投稿は軽い気持ちで行われることが多いですが、一度炎上すると収拾をつけるのは困難です。そのため、不適切投稿は未然に防ぐことが何より重要といえます。
就業規則・SNSガイドラインの策定
SNS利用のルールについては、就業規則で明確に定めておくことが重要です。また、違反時は懲戒処分の対象となる旨も明示することで、不適切投稿を抑止する効果が期待できます。
さらに、SNSガイドラインやSNSポリシーを新たに策定し、社内で周知する方法もおすすめです。
このように明確なルールがあると、従業員も理解しやすく、安心して働くことができます。また、規律遵守の意識が高まり、適正なSNS利用を促すことにもつながります。
就業規則の作成ポイントは、以下のページで解説しています。
従業員に向けた教育・研修の実施
社内でSNS教育や研修を実施することも有効です。研修では、以下のような事項について説明を行います。
- SNSの概要
- 投稿時の注意点
- 炎上した場合のリスク
- 炎上事例
- 炎上した場合の対処法
もっとも、一般的な情報のみを伝えても従業員には響きません。
実効的な研修を行うには、不適切投稿によって従業員本人がどれほど大きな不利益を被るのかしっかり説明することが重要です。
例えば、
- 個人的な投稿であっても、会社の経営危機や倒産につながるおそれがあること
- 投稿内容は瞬時に世界中に拡散され、削除は困難であること
- 投稿者の氏名や住所が特定され、バッシングを受ける可能性が高いこと
- 損害賠償責任や刑事責任を負う可能性があること
などを強調すると効果的でしょう。
誓約書の提出を求める
従業員はSNS利用に伴うリスクについて無自覚な場合があるため、SNS利用に関する誓約書を提出させることで、自覚を促す方法も有効です。
また、あらかじめ誓約書を提出させておくことは、懲戒処分として具体的にどのような処分を行うことができるか、当該懲戒処分が相当性を有するものであるかという判断にも影響する可能性があります。
なお、従業員の秘密保持義務や秘密保持契約書については以下のページでも解説しています。是非ご覧ください。
社内体制の整備
会社への誹謗中傷は、給与や待遇への不満、会社への不信感等がきっかけで行われることも多いです。
そのため、従業員との信頼関係を築き、会社への愛着や信用度を高めることも、不適切投稿を防止するために有効な方法です。
例えば、基本給の底上げ、福利厚生の充実、人事評価制度の見直しといった“労働条件の改善”は、従業員満足度を高めるために特に効果的です。
また、社員間のコミュニケーションを活性化させることで、不満のはけ口ができ、SNSへの投稿を抑える効果が期待できます。
自社の公式アカウントの運用で注意すべき点
会社の公式アカウントを運用している場合、投稿内容が企業イメージに直結するため注意が必要です。特にアカウント管理を社員に任せる場合、以下のような点に留意しましょう。
- 公式アカウントを私物化しない
プライベートアカウントとの混同を防ぐため、アカウントの管理は複数人で行うことをおすすめします。 - 投稿時の言葉や表現に注意する
差別的な表現や偏見を含む内容を投稿すると、炎上リスクが高まります。投稿時のマニュアルやガイドラインを策定し、基準を統一しておくことが重要です。 - ダブルチェックを行う
無意識のうちに機密情報等を流出させてしまう可能性もあるため、投稿前にダブルチェックを行うと安心です。
従業員のSNS利用に関する裁判例
従業員のSNS利用については、未だ裁判例の蓄積が少ないことから、ここでは社内での誹謗中傷メールに対する調査が問題となった事例をご紹介します。
【平成12年(ワ)11282号 東京地方裁判所 平成14年2月26日判決】
事件の概要
会社Aの従業員に対して誹謗中傷メールが送られてきたことから、その調査過程で、会社Aがパソコンサーバーを確認したところ、従業員Bが多量の私用メールを送受信していることが明らかとなりました。
事情聴取を受けた従業員Bは最終的に退職したうえで、会社Aに対して、「無断で通信記録を確認したことはプライバシー侵害に該当する」などとして損害賠償を求めました。
裁判所の判断
裁判所は、「企業秩序に違反する行為があった場合には、違反行為の内容等を明らかにするなどの目的のため、事実関係の調査を行うことができる一方で、その調査は、必要かつ合理的なものに限られること」などを示した上で、損害賠償請求を棄却しました。
ポイント・解説
本判決は、会社のファイルサーバーに保存されていた従業員の通信データを調査したことなどは、違法とはいえないと判断しています。
ファイルサーバーの調査については、会社は常に行うことができるというわけではありません。その必要性と合理性を吟味する必要があります。本件では、誹謗中傷メールが企業秩序違反行為であり、その調査を目的としていることや、従業員Bを疑うべき合理的な理由があったことから、調査を実施したことは違法とはいえないと判断しています。
従業員による不適切なSNS投稿への対応・対策は弁護士にご相談ください
従業員によるSNSトラブルを防止するためには、事前に規程・ガイドラインを整備しておくことや、研修を実施しておくことが重要となります。また、SNSトラブルが起こってしまった場合には、迅速かつ適切な対応をとり、被害の拡大を抑える必要があります。
企業法務のプロである弁護士であれば、より有効な防止策の整備やトラブル後の対応についてサポートをすることができます。従業員のSNSトラブルでお悩みの方は、是非弁護士へご相談ください。
企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ
企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※
企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)
会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません。
受付時間:平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00
平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00
※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
執筆弁護士

- 弁護士法人ALG&Associates
この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)
執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。
近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある